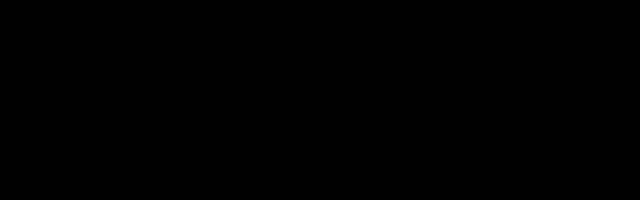�f��L���_�čl
�N���X�`�����E���b�c�̑�A���ƃ~�b�V�F���E�R�����ɂ��u��A���čl�v�̎˒�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�X���@���I
�͂��߂�
�@�P�X�U�O�N�㏉���ɂ͂��܂�������w�Ɖf��̏o��́A�f�挤���ɂƂ��Ă���߂ďd�v�Ȏ��ł������Ƃ�����B�t�����X�̋L���w�ҁA�f��w�҃N���X�`�����E���b�c1���P�X�U�S�N�Ɂu�f��\�\����̌n�����ꊈ�����H�v2���������̂́A���̎����ł���A����̓��b�c�̌���w�Ɖf��Ƃ̏����̌������ʂł���Ƃ�����B���b�c�̌����͌�̉f�挤���ɑ���ȉe�����y�ڂ����B�����ă��b�c�̌�������S�O�N�߂����������A�l�X�ȕ��@�ʼnf�挤��������Ă��钆�A�ނ̌����͉f�挤���҂ɂ���ĂЂ������Ȃ���Ă���B�f�悪�a�����Ă���P�O�O�N�]��A���̒��ł̂S�O�N�ԂɁA���b�c�̌������f�挤���҂ɂ���ĂЂ��������グ���閣�͉͂��ł��낤���B�P�X�U�T�N����P�X�U�X�N�Ƃ����Z�����ԂŔ��W�����A���b�c�̍l�Ă����ÓT�I����f��ɂ�����u��A���v3�Ƃ��̌����ɏœ_���i��A���̗L�����Ɩ��͂�{�e�ŒT�����Ă݂����B�_���WThe Film Spectator: From Sign to Mind4���A�P�X�X�R�N�ɖv�����N���X�`�����E���b�c�̃I�}�[�W���Ƃ��āA�����Ă܂��f��̋L���_�͏I�������̂ł͂Ȃ��p������A�����V�����L���_�Ƃ��Ĕ��W�����悤�Ǝ��݂Ă��邱�Ƃ�錾���邽�߂ɁA�P�X�X�T�N�ɏo�ł��ꂽ�B���̒��Ń��b�c�̑�A���������������M���ׂ��_���Ƃ��āA�~�b�V�F���E�R�����́u��A���čl�v5�������邱�Ƃ��ł���B���̃~�b�V�F���E�R�����̘_���͂��Ȃ���A���b�c�̑�A���Ƃ��̍čl�̗L������T��̂��{�e�̖ړI�ł���B��A���Ƃ��̍čl�̗L������T��O�ɁA���b�c�̑�A�����̂��̂��Љ�����B�����Ď��Ƀ��b�c�̉f��ɑ��鋳��_�ƃ~�b�V�F����R�����̑�A���čl�̗��R�Ƃ��Ƃ炵���킹�čl����B�Ō�ɑ�A���̋�̓I�ȃ~�b�V�F���E�R�����ɂ��čl�Ƃ��̌��ʂ�������A���Ƃ��̍čl�̗L�����ɂ��čl�@���Ă����B
���b�c�̑�A���Ƃ�
�@����ɉ��p�����u�͗�v��u�A���v�Ƃ������T�O���A���t�ȊO�ɂ����p�ł���Ƃ������Ƃ͊m���Ȃ��Ƃ̂悤�ł��������A�����̊T�O�́A����w��c�Ƃ��邽�߂ɁA����ȊO�ւ̓K�p�́A���̗L���������O����Ă����B���b�c�͂��������T�O��Ŕj���A�L���_�I�L�q���f��։��p�����B���̌`����A���ł���Ƃ�����B���b�c�́A�܂���̉f��I�R�[�h��I�т�������������B��̓I�ɂ́A�f���̔z��A�܂�A�ÓT�I����f��ɂ�����V���b�g�Ԃ̊W�̌����ł������B���̌�������A���ƌĂ����̂ł���B��A���ɂ���āA����Ԃ̗���ɏ]�����V���b�g�̔z��́A���Ɍ��i�ȋK���ɂ���ĕ��ׂ��Ă���Ƃ������Ƃ����������ꂽ�B���b�c�́A�����̃V���b�g�̕��ѕ��̑g�����ɕ������B���ꂪ�ȉ��̐}�ł���B
���b�c�̘A�����ވꗗ�\6
�܂����b�c�́A��̉f��������I���߂ɋ�����B�����I���߂́A��ʂɁA�t�F�C�h�E�C��/�A�E�g�ȂǂƂ������f��̋�ǖ@�ɂ���ċ��ꂽ��̃��j�b�g�ƒ�`�����B���̃��j�b�g�́A�ꏊ�̕ω��A�o������s���̏I���ɂ���ċ���邱�Ƃ���ʓI�ł���B���Ɏ����I���߂́A�����I�V���b�g���A���ɕ�������B�����I�V���b�g�́A�O��̃V���b�g�Ɩ��W�ȃV���b�g�ł���A�A���́A�O��̃V���b�g�ƊW������V���b�g�ł���B��̐}�Ŏ�����Ă���悤�ɁA�����I�V���b�g�ɂ́A��������}�����ꂷ����̂͂Ȃ��A�����ŏI�����A���ꂾ���œƗ����đ��݂���B���������̓_�ɂ����āA���b�c���g�����_�������Ă���B����́A�����I�V���b�g�́A���ꂾ���ŏI�����A�Ɨ��������̂Ƃ������́A���ʗތ^���������^�C�v�ł���A�K�����������I�V���b�g���I�����A�Ɨ��������̂ł���K�v�͂Ȃ��Ƃ������Ƃł���7�B�@�����I�V���b�g�̉��ʗތ^�ɂ́A�V�[�N�G���X�E�V���b�g�Ǝl��ނ��V���b�g���܂܂�Ă��邱�Ƃ����b�c�͎����Ă���8�B���̘A���^�C�v�͔ԏ������ԏ����ɂ���ċ敪�����B�@�ԏ��A���Ǝ��ԏ��A���́A���ꂼ���̘A���^�C�v�A�O�҂����s�A���Ɗ��ʓ���A���ɁA��҂͋L�q�A���ƕ���A���ɋ敪�����B���ɁA����A���́A�����I�ɕ���邩�ۂ��ŋ敪�����B������̕���A���͘A���I���ۂ��Ƃ����v�f�ŁA�V�[�����V�[�N�G���X�ɋ敪�����B�����čŌ�ɁA�V�[�N�G���X�́A�g�D����Ă��邩�ۂ��ŁA�}�b�I�V�[�N�G���X�Ƃӂ��̃V�[�N�G���X�ɋ敪�����B���̂悤�ɂ��Ď����I���߂́A�����I�V���b�g����ӂ��̃V�[�N�G���X�Ɏ��锪�̃^�C�v�ɋ敪�����B���̋敪�̉ߒ��́A��㈓I��(��}�ł���������E�̏���)�s����B���b�c�����y���Ă���悤�ɁA���̑�A���ɂ͖������Ȗ�肪�c���Ă���8�B�������A����ł����b�c�̑�A���͉f��̋L���_�ɍł��e�����y�ڂ��A�v�������Ƃ�����̂ł͂Ȃ����낤���B
�Ȃ���A���čl�Ȃ̂�
�@�~�b�V�F���E�R�����́u��A���čl�v�̘_���ɂ���āA���b�c�̑�A���̖��_�������A���̂��������������Ă���B�R�����ɂ�郁�b�c�́u��A���čl�v����̓I�Ɍ����Ă����O�ɁA�R�������g���u��A���čl�v�������ɂ������Ă̈Ӑ}�������Ă��������B�R�����́A��A�������ꎩ�̂ɖ�肪���낤���Ȃ��낤���A�f��������铹��Ƃ��č������g�p����Ă��邱�Ƃ��w�E���Ă���B�R�����͌ÓT�I����f��ɂ������A���������铹��Ƃ��Ďg�p���邽�߂ɂ́A��A���̌����̂�������������A���̉ߒ��ŏo�Ă��鏔�����������Ƃ����߂���̂��Əq�ׂĂ���B���̖ړI�̂��߂ɏ����ꂽ�̂��R�����́u��A���čl�v�ł���B�����铹��Ƃ��đ�A����p����ɂ́A��A���̌��������K�v�ł���Əq�ׂĂ���̂ł��邪�A��A�����������Ă܂Ŏg�p���鉿�l�͂ǂ��ɂ���̂ł��낤���B�@��A���̗L�����́A�u��A���čl�v�̌��_���ɂ����Č��o�����ł��낤���A�������ł�����̂́A��A���̉��߂Ƃ��̏����̉���������Ȃ�f��̋���ɂȂ���ƃR�������l���Ă���Ƃ������Ƃł���B���b�c���g���f��̋���ɂ��ďq�ׂĂ���A��A���쐬�̓��b�c�̖ڎw���Ă����f��̋���̖ړI�ɖ𗧂悤�Ɏv����B���b�c�́A�u�f���̎��Ɓv�̍ő�̌��т͎q�������ɘb������Ƃ������Ƃɂ���Əq�ׂĂ���9�B�f��̋Z�@�̈Ӗ����w�q���́A���̋Z�@���Ȃ��������킩��̂��Ƃ������Ƃ�����ɗ�������B�����ĕ���I�f���̎��R�̂܂܂̂���܂ł̗����ɉ����āA����f��̎d�g�݂𗝉�����悤�ɂȂ�B�������������ɂ���Ďq�������́A���ꊈ���ł���f���ɂ��āA����ŏ����ꂽ����ꂽ�e�N�X�g�ȏ�ɁA�b�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ�ƃ��b�c�͏q�ׂĂ���B�f���̎d�g�݂͂܂��ɑ�A���Ő����ł���ł��낤�B���b�c�̋���̖ړI�́A�܂��w�Ԏ҂ɋZ�@�𗝉������������ŁA�����̉f��ɑ��闝���̎d�g�݂͂����A��点�邱�Ƃɂ���B�����ăR�����̂�����A��A���čl�A�܂��A���̖����������邱�ƂŁA����ɉf���ɂ��Č�邱�Ƃ��ł���Ƃ������̂ł���B���b�c�̖ړI�ł���A��A����ʂ��Ċw���ɉf���ɂ��Ęb�����邱�Ƃ��ł���Ƃ����_�́A�R���������ӂ��Ă���悤�ł���B����䂦�R�����́A��A����K�v�Ƃ��A�čl���ꂽ��A����ʂ��āA�w���ɉf���ɂ��Č�点�悤�Ƃ��Ă���B
���b�c��A���̏����
�@�ȏ�q�ׂ��悤�ɁA��A���̎g�p���A���čl�ɂ���Ċw���ɉf���ɂ��Ęb�����邱�Ƃ��ł���Ƃ����_�ɂ����āA��A���Ƃ��̍čl�͗L���ł���Ƃ�����B�������A���ꂾ���ł͑�A���Ƃ��̍čl�̗L�����͋����Ƃ͂����Ȃ��B���̗L������T�邽�߂ɁA�{�߂ŁA�R�������u��A���čl�v�̒��ŋ������������̗���������Ă��������B
�@�R�����ɂ��ƁA���b�c�̑�A���͉�㈓I�ɓǂ܂��̂ŁA���ꂼ��̘A���^�C�v�̌�����������ŁA�����ɖ�肪������B��㈓I�ȑ�A���̓ǂݕ��ɑ��āA�R�����͋A�[�I�ɑ�A����ǂނ��Ƃɂ���āA���ꂼ��̘A���^�C�v�̓�������������B���b�c�̑�A���̎��`�}�ɂ�����āA�R�����́A���I�ȕ\���쐬����11�B����ɂ���Ă��ꂼ��̘A���^�C�v�̓������N���ɕ\����A�A���^�C�v���������₷���Ȃ�B�R�����́u��A���čl�v�ɂ����ĉ�㈓I�ȓǂݕ����A�[�I�ɓǂݒ������̍�Ƃ́A��A������₷�����������łȂ��A�f��̕��͂ɂ����Ă��L��������������B
�@�܂��A���b�c�̃V�[���ƃV�[�N�G���X�̋�ʂ������A���ɃR�����̑�A���̋A�[�I�ǂݕ���������B���b�c�̑�A���ɂ����ẮA�V�[���ƃV�[�N�G���X�̋�ʂ́A�A���I���ۂ��ŋ�ʂ��ꂽ�B���b�c�́A���̋�ʂ����̂悤�ɐ������Ă���B���b�c�ɂ��A�V�[���́A�u�����I�v�ł���Ɩ����Ɍo��������̃��j�b�g���A�č\��������̂ł���B�u�����I�v�Ƃ́A�ꏊ�₠�鎞�Ԃ̒��̂ЂƂƂ��A�����čs�����Ȍ��ɂ܂Ƃ܂��Ă��邱�Ƃ������B�V�[���̒��ł́A�V�j�t�B�A��(�Ӗ��������)�́A�f�ГI�ɑ��݂���B�܂�A���̃V�[���̒��̃V���b�g�S�ẮA�P�ɕ����I�ȁu���ʁv(��ʓI�W���̂̒�������o���ꂽ����)�ł���B�������A���̃V�[���̒��̃V�j�t�B�G(�Ӗ���������)�́A���ꂳ��A�A���I�ł���B���Ƃ������b�̃V�[���ɂ����āA���Ƃ��V���b�g���l�X�ɕς�낤�Ƃ��A��b�����Ă��鉹���A�����Ă��邱�ƂŁA���̃V�[���͘A���I���Ɗ�����ł��낤12�B���̂悤�Ƀ��b�c�͘A���I�Ƃ����T�O��������A�V�[�����`���Ă���B�R�����́A���̘A���I�Ƃ����T�O���A��A���̋A�[�I�ȓǂݕ���p���āA����ɕ�����₷����̓I�ɐ������A�V�[���ƃV�[�N�G���X�̋�ʂ�������Ă���B���Ƃ��V�[���ƃV�[�N�G���X�̓����͈ȉ��̂悤�Ɏ������13�B

�R�����ɂ��A�V�[���ƃV�[�N�G���X�̋�ʂ͊ܗL�I���ۂ��ōs���Ă���B�ܗL�I�Ƃ́A�����߂�ꂽ�Œ肵����Ԃ̒��ɑΏە����u�����(�܂܂��)����Ƃ������Ƃł���B�V�[���ɂ����đΏە��́A�Œ肳�ꂽ��ԓ��ł����������Ƃ��ł����A����i��ŋ�Ԃ���肾�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂�A�Ώە��͋�ԂɎx�z�����B���̌Œ肳�ꂽ��Ԃ̒��ł́A�Ώە��̓���͘A���I�ɍs�����Ƃ��ł���Ɖ��߂ł���B���b�c����������b�̃V�[���̗�������ɂ����Ă͂߂邱�Ƃ��ł���B�V�[���ł̉�b�͂���Œ肳�ꂽ��ԂŘA���I�ɍs����B���Ƃ���b�̃V�[���ŁA��b�ɂ܂��f��(���Ƃ��A�t���b�V���o�b�N�ł̉ߋ��̃V���b�g)�����̃V�[���ɐD�肱�܂�Ă��悤�Ƃ�����̈���ʼn�b���s���Ă���A����̓V�[���ł���ƒ�`�ł���B
�@��ܗL�I�ł��邱�Ƃ́A�V�[�N�G���X�̗v�f�ł���B����͌Œ肳��Ă����Ԃ̒��ɑΏە����u�����(�܂܂��)���Ȃ����Ƃ��Ӗ�����B�V�[�N�G���X�ɂ����ẮA�Ώە��̓����ɂ���ċ�Ԃ���肾�����B�Ώە��������Ƃ��̋�Ԃ������̂ŁA��Ԃ͌Œ肳��Ă���̂ł͂Ȃ��A�Ώە��̓����ɂ���Ė����ɍL���肤��B�܂�A�Ώە�����Ԃ��x�z����B�Œ肳��Ă��Ȃ��L����̂����Ԃł́A�Ώە��̓���͒f���I�ɂȂ�B�R�����͓��S�̃V�[�N�G���X���ɂ����āA��Ԃƒf�����̊W��������Ă���14�B���S�ƒǐՂɂ����āA�Ώە��̓�������Ԃ���肾���A���̋�Ԃ͌Œ肳��Ă��Ȃ��B���S�͒ǐՂ̈ꕔ���ł���A���S�ƒǐՂ̈Ⴂ�́A�O�҂͑Ώە����ǂ���҂ŁA��҂͂��ꂪ�ǂ��҂ł���B���S�������ɂ͒ǐՂ������K�v�����邪�A���S�҂����ɒ��ڂ���A���S�҂̍s���́A�ǐՎ҂̍s���ƍ������āA�f���I�ɉf���o����邱�Ƃ��킩��B���̂悤�ɁA���S�҂��A�f���I�ɗ̈�̒�߂��Ă��Ȃ���Ԃł����������̂́A�V�[�N�G���X�ł���Ƃ�����B
�@�R�����́A���b�c�̍l�Ă����A���I���ۂ��Ƃ����v�f���A��Ԃ��g�p���邱�Ƃł�蕪����₷���������A�V�[���ƃV�[�N�G���X�̑�����������Ƃ�����B�����āA�������邱�ƂŃ��b�c�̒�Ăɂ���ɍL����������炵���B�ϋq�͎��R�ƌÓT�I����f������邱�ƂɊ���Ă��܂��āA��A�̉f�����A���I���ۂ��Ƃ������Ƃ͂��܂�ӎ����ĂȂ��B���������ۂɁA����f����A���ɂ��Ă͂߂Ă݂邱�ƂŘA���I�ł���Ƃ́A�ǂ��������Ƃ����l���邱�Ƃ��ł���B�R�����̎������悤�ɁA�A���I�̊T�O�́A��ԂƏƂ炵���킹�邱�ƂŐ����ł���B���b�c���u���j�I�ɂ́A�c���̃R�[�h[��A��]�̗L�����́A�����w�ÓT�I�x�f��ƌĂԂ��̂������������邱�ƂɂȂ�v�Əq�ׂĂ���悤��15�A��A�����l�@���邱�Ǝ��́A�ÓT�I����f��̍l�@�ɂȂ���A�������ϋq�������ɌÓT�I����f��Ɋ���Ă��܂��Ă��邩�Ƃ������Ƃ�����������̂ł���B���̂悤�ɂ��đ�A�����čl���邱�ƂŁA�ÓT�I����f��̕��͂ɂ���Ȃ�L���肪������B
�@�A�[�I�ɑ�A�����čl���邱�Ƃɂ���āA�A���^�C�v�̓���������ɖ��m�ɂ����R�����̘_�_��������_�����Ō������Ă��������B���b�c�̒�`�����ԏ������ԏ����Ƃ����v�f�Ŕ��ʂ�����s�A���ƌ�֘A�������邪�A���̗v�f�Ɉ�ʓI������I���Ƃ����v�f�����������ɗ��A���̔��ʂ��e�ՂɂȂ�ƃR�����͎w�E����B�ԏ��ŁA����I�ł���̂����s�A���ŁA���ԏ��ŁA��ʓI�Ȃ̂���֘A���ł���B�R�����͂����ł�������₷����������Ă���̂ł�����Љ��16�B����e���r�ԑg�̗�ł���B���郉�O�r�[�I����Љ��ۂɁA���̑I�肪�Q�����Ă��������̃V���[�Y�ƁA���̗����ɍs��ꂽ�ł��낤���O�r�[�����̃V���[�Y����ւł����������B�����̓�́A�Ⴄ�ꏊ�œ��l���ɂ��Č���Ă���Ƃ����_�ŁA���݂��Ɋ֘A���Ă��āA��̘A���^�C�v�ɂȂ��Ă���B���̘A���^�C�v���\���Ă���A��̃V���[�Y�̌�ւ́A���O�r�[�I��̎Ќ�I�Ȗ�̐����ƁA���j�̌ߌ�̌������^���̗��K�Ƃ̑ΏƂ�\���̂��ړI�ł���B�������A���̓�̍s���͗����ł��Ȃ��ƕ��ʂ͍l����B���̂��Ƃ́A���̓�̘A���^�C�v�������Ă��邱�Ƃł���B��́A���s�A���ł����āA���ꐢ�E����v�f�Ɏ����Ȃ��A���ł���A���̃��O�r�[�I��ɂ́A���O�r�[(�^���ȃX�|�[�c����)�Ɩ�̎Ќ�I�Ȑ����͗����s�\�ł���Ƃ����T�O�Ŋ֘A�Â����Ă���A���ł���B��������́A��֘A���ł���A���ԏ��ł�����I�v�f�������Ă���ƃ��b�c���w�E���Ă���A���ł���B��֘A���ł́A��̃V���[�Y�������̗v�f�ŁA���̃��O�r�[�I��͓�\�l���Ԉȓ��ɖ�̎Ќ�I�ȏ�ւ̎Q���ƃ��O�r�[�̎����̓�����Ȃ����̂��Ɗ֘A�Â��邱�Ƃ��ł���B�����ŃR�����͎��̂悤�Ɏw�E���Ă���B���̓�̘A���́A���b�c�̎������ԏ������ԏ����Ƃ����v�f���A�ނ����ʓI������I���Ƃ����v�f�Ō���Â�����B���O�r�[�̎����O�ɖ�̎����ɂ͕��ʂ͎Q�����Ȃ��Ƃ�����ʓI�ȗv�f�ŁA��̃V���[�Y����s�A�����ƌ���Â��A��������́A����l�͎����O��ł��A��̎����ɎQ������̂��Ƃ�������I�ȗv�f�ŁA��̃V���[�Y����֘A�����ƌ���Â���B�m���ɃR�����̎w�E������ʓI������I���Ƃ����v�f�͘A���^�C�v�̕��ʂɖ𗧂��A���̗v�f�����ł͕s�\���ł���B�R�����̎w�E�����v�f�́A���b�c�̔ԏ������ԏ����Ƃ����v�f���m�F����̂ɓK���Ă���悤�ł���B���b�c�̔ԓI�����ԏ��I���Ƃ����v�f�ɉ����āA�R�����̈�ʓI������I���Ƃ����v�f�ŁA�A���^�C�v�͂���ɕ��ʂ��₷���Ȃ�ł��낤�B�@
�@��A���̋A�[�I���͌��ʂ̈�Ƃ��āA�R�����́A��A�����čl���邤���ŁA���b�c����̓I�Ɏ����Ȃ������A���^�C�v�̉��ʕ��ނ�\���Ă���17�B

(1)�ł́A����A�����A�A���ł��邩�ۂ��A�����ĕ��ꐢ�E�����ۂ��Ƃ������ʕ��ނ������Ă���Ƃ����̂������Ă���B(2)�ł́A(1)�̘A���͒����I���ۂ��Ƃ������ʕ��ނ����邱�Ƃ������B(3)�ɂ����āA(1)�̕��ꐢ�E���ɂ́A���ꂪ����I���ۂ��A����I���ۂ��A�ܗL�I���ۂ��Ƃ������ʕ��ނ�����Ǝ����Ă���B���̉��ʕ��ނ̓��b�c�̎��`�}�ł͕\�����Ƃ��s�\�ȕ��ނł���A���`�}���������̘A���^�C�v�̓�����\�������ł���B���Ƃ��A�R�����͎��̂悤�ȘA���^�C�v�������Ă���18�B
�@
�A�����A���A���ꐢ�E���A�����I[��ʓI]�A���I��
���I�ł���Ƃ����v�f�͕��s�A���ƌ�֘A���������Ă��邪�A���s�A���͔ꐢ�E���Ƃ����v�f�������A��֘A���͓���I�Ƃ����v�f�����̂ŏ�̂悤�ȘA���^�C�v�̓��b�c�̎��`�}�ɂ��锪�̘A���̂�����ł��Ȃ��B���̂��Ƃ́A��A���������ɍL�͈͂ɂ킽���Ă��邩�Ƃ������Ƃ������ł���ƃR�����͎w�E���Ă��邪�A����ł��̕\�����S�Ă̘A���^�C�v��ԗ��\���Ƃ͂����Ȃ��Ƃ��w�E���Ă���B�������A���̕\���́A�R���������b�c�̑�A�����A�[�I�ɍčl�������ʂ��Ȍ��ɕ\���������Ƃ������Ă���A��A���̓�����m��̂ɓK���Ă���Ƃ�����ł��낤�B
�R�����ɂ��f���敪
�C���e�̔������N���[�X�E�A�b�v�ő}�������B�D��l����������Ɍ������B