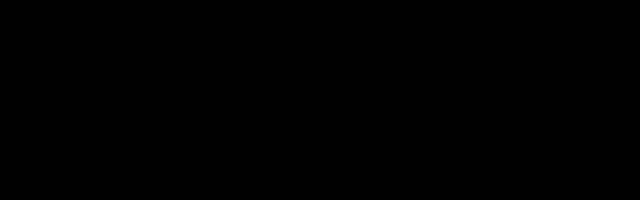
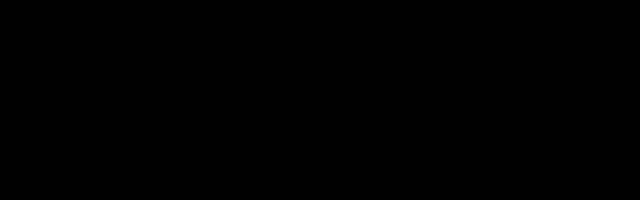
メロドラマ映画と盲目性 ―『ステラ・ダラス』をめぐって
吉澤泰輝
以下の論考においては、メロドラマ映画というジャンルの諸特徴について包括的に
論じるのではなく、その一特徴を中心に限定的な議論がおこなわれる。具体的に述べ
るならば、メロドラマ映画と盲目性(視覚喪失)との関わりについての考察がおこな
われ、その特徴を切り口にメロドラマ映画『ステラ・ダラス』(キング・ヴィダー監
督、1937年)の特異性が論じられていくことになる。
1. 発話能力の喪失と視覚の喪失
メロドラマ映画とはどのような特徴を有するジャンルなのか。ピーター・ブルック
スはメロドラマ分析に大きな影響を及ぼしている著作『メロドラマ的想像力』のなか
で興味深い指摘をおこなっている。「各種の劇にはそれぞれ特有の交流能力の喪失が
存在しているように思われる。悲劇にとって、それは盲目である。なぜなら、悲劇と
は洞察(insight)や啓示(illumination)に関係しているからである。喜劇にとっ
ては、聾であることである。なぜなら、喜劇はコミュニケーション上の諸問題や誤解
とその結末に関係しているからである。そして、メロドラマにとっては唖であること
である。なぜなら、メロドラマは表現に関係しているからである1」。悲劇とは視覚
の喪失に関わる。『オイディプス王』を思い出せば明らかなように、真理を見る視覚
(sight)を喪失しているがゆえに洞察(insight)を求めるジャンルこそが悲劇であ
ると言える。すなわち悲劇とは「見ること(sight)と知ること(insight)」に関わ
るジャンルである。そして、喜劇とは聴覚の喪失に関わる。このことは例えばマルク
ス兄弟の映画でも思い出せば明らかであろう。そこでは人の言うことを聞かず、話の
文脈を徹底的に誤解・逸脱していくことが滑稽さが生み出している。では、メロドラ
マはどうなのか? ブルックスによればメロドラマとは発話能力の喪失に関わるジャ
ンルである。メロドラマにおいては、主人公(多くは女性である)は外圧のために表
現が抑圧され、自らの欲望を口にすることができない。その結果として、彼女たちは
沈黙したまま立ち去っていくことになる(黙って身を引く女性はメロドラマ映画の典
型的モチーフである)。
では、このような発話能力の喪失は『ステラ・ダラス』においてどのように現われ
ているのだろうか? 奇妙なことに、この代表的な母子メロドラマにおいて、主人公
ステラ(バーバラ・スタンウィック)は当初まったく表現が抑圧されていない。逆に、
ステラは上昇志向が強く、自らが所属する下層階級を抜け出し上流階級へ参入したい
という欲望を積極的に語っている。そして思惑通りに彼女は上流階級の紳士スティー
ヴン・ダラスとの結婚に成功することになるのである。このように能動的な女性像は
決してメロドラマ的ではない。したがって、映画はステラをメロドラマにふさわしい
人物へと変化させることになるだろう。事実、ステラが抑圧され、発話能力を喪失す
る瞬間が訪れる。まずはこの瞬間に注目する形で議論を進めていく。
下層階級出身であるステラは結婚によって上流社会に参入した後も、下層的で洗練
されない女性として描かれる(そのため、夫ともすぐに別居することになる)。彼女
の言動は上流社会にとっては過剰なものであり、視覚的な違和を引き起こさずにはい
ない。映画は彼女の人付き合いのやり方、服装、マナーなどを上流階級のまなざしを
媒介に下品で不適切なものとして表象していく。そして、彼女は自分の行動に注がれ
る周囲のこうしたまなざしに対してまったく気がつかないのである。しかし、ステラ
が上流階級の人々にとっての自らのイメージを「正しく」理解する瞬間が訪れる。そ
の瞬間は視覚的認識として訪れはしない。悲劇の登場人物と同様に、ステラは「真理」
を見る能力が欠如していために自らの「正しい」イメージを誤認していたのである以
上、「真理」は聴覚的認識という形で訪れることになる。
ステラの娘ローレルはステラとの旅行のシークエンスにおいて、ステラの服装や行
動が滑稽であると知覚するようになり、彼女が自分の母親であることを恋人や友達に
気付かれないように、母を連れて慌てて家に帰ろうとする。そして、この帰りの列車
のなかで決定的瞬間が訪れるのである。画面奥から寝台のあいだをローレルが歩いて
くる。彼女が下の寝台のカーテンを開けてなかを覗くと、そこにはステラが眠ってい
る。乗務員が持ってきてくれた脚立を使い、ローレルはステラの上の寝台に上がり込
む。すると、横の廊下をローレルの友人たちが通りかかるのである。友人たちは二人
の寝台のすぐそばで、昼間の派手な女性がローレルの母親だという噂話を始める。寝
台のカーテンの内側では彼女たちに気付いたローレルが体を起こし、話に耳を傾ける。
そして、その話し声にステラまでもが目を覚ましてしまうのである。ステラはついに
自分がどのように見られているのかということを知る。更にはそうした自分の存在が
ローレルと恋人との関係にも影響を及ぼすだろうということを聞いて反応し、体を起
こしてじっと話に耳を傾ける。カメラはステラに向かってゆっくりと寄っていく。自
分が娘の幸せにとって障害となっていることを知った彼女の、目に涙を浮かべる表情
が強調されていく。彼女は寝台のカーテンの内側にいるという視覚を制限された状態
で、初めて自らの「正しい」イメージを認識したのである。この後、彼女は娘のため
に黙って身を引くメロドラマ的な登場人物へと変化することになるだろう。事実、ス
テラが娘には何も語らずに彼女を自分から引き離そうとしていくプロセスこそが以降
の物語となる。このように『ステラ・ダラス』においても発話能力の喪失は決定的で
ある。自らの欲望を積極的に語る非メロドラマ的なヒロインであったステラでさえも、
決定的な瞬間に直面し、その結果として黙って身を引いていくメロドラマ的な人物へ
と変化させられることになるのだから。
だがここで少し立ち止まり、ステラがメロドラマ的な人物へと変化する契機となっ
た瞬間について、もう一度、今度は形式的側面から考察してみたい。先述したように
カメラは決定的瞬間を迎えたステラの表情に向かって寄っていき、その瞬間の彼女の
在りようを微細に表象する。このクローズアップ。決定的瞬間において現われてくる
このようなクローズアップこそ古典的なメロドラマ映画においては不可欠なショット
であり、これを見ることによって観客はヒロインに対する抗い難い感情移入へと傾斜
していくことになるのである。メロドラマ映画の成否はこのクローズアップをどのよ
うに組織化して繰り出すかということにかかっている言ってもよい。そして、そうで
あるがゆえにこのクローズアップが孕む過剰さをメロドラマ映画における重要な特徴
として議論してみたい。
例えば、ピーター・ブルックスの上記メロドラマ論を引用する形でタニア・モドゥ
レスキーはスティーヴン・ヒースを批判している2。彼が『忘れじの面影』(マック
ス・オフュルス監督、1948年)の、そして物語映画一般の全問題を「見ることと知る
こと」の問題として特徴づけ、表現の抑圧というメロドラマが本質的に関わっている
問題を見落としてしまっているというわけである。「見ることと知ること」とは本質
的に男性的なジャンルである悲劇のパラダイムなのだと。だが、そうしたモドゥレス
キーの批判を認めつつも、それを更にもう一度転倒させて次のように主張してみたい。
ピーター・ブルックスが悲劇の特徴として述べていた視覚の喪失、すなわち盲目性こ
そがメロドラマ映画においても重要な特徴であるのだと。だが、これはヒースのよう
な主張をしたいわけではない。ヒースはローラ・マルヴィの影響下で『忘れじの面影』
を論じるなかで、男性が女性を光景(sight)へと押し込めてしまうこと、自らを脅
かすことのない無害な存在へと変容させることによって所有・内面化を図っている状
況を分析している3。そして、彼はその光景化された女性の唯一の意味とは男性の人
生についての洞察(insight)にすぎないのだと告発する。こうしたヒースの分析は
確かに視覚(sight)の獲得による真理の洞察(insight)というブルックスの述べる
悲劇的なパラダイムであるとは言えるだろう。だが、このような主張を単に悲劇的な
考え方であるという理由でメロドラマ映画論から排除するべきではない。メロドラマ
がそもそも大衆化された悲劇であるということ、そしてそれ以上に映画が視覚的表象
を扱うジャンルにほかならないということからも、「見ることと知ること」という視
覚的な問題設定は必然的につきまとうことになるのだから。しかし、このような真理
に対する盲目性をメロドラマ映画の特徴としてここで指摘したいわけではない。そう
ではなく、メロドラマ映画の構造的必然として要請されるクローズアップの決定的な
特徴として盲目性が立ち現われてくるということを論じたいのである。ステラのこの
クローズアップにおいて、ステラは何も見ていない。これは彼女がいる寝台がカーテ
ンに仕切られているために、自分の噂話をしている人たちを彼女が見ることができな
い状況にいるということを意味しているのではない。このクローズアップのステラは
外界を何も知覚していない。耳から入ってきた会話による「真理」の認識に伴うあま
りの衝撃のために、彼女には何も見えていない。そのまなざしはただ内部から湧き出
る激しい感情の強度を内側に留めているだけのまなざしである。内側から突き上げて
くる強烈な情動のために、その視覚は破壊され、盲目となっている。
こうして盲目性はメロドラマ映画において特権的な感覚喪失となる。しかも、この
ことは更に広い意味を持っている。この盲目の映像が孕む過剰さはそれに抗うことが
困難なものであるために、観客もまた登場人物同様に情動の強度にただ身を任せるだ
けの存在と化してしまい、視覚が剥奪されてしまうのである。すなわち、観客は視覚
を喪失した登場人物の感情をそのまま模倣してしまい、同時に自らも盲目となってし
まう。観客も画面を見ていると同時に見ていない。自らの内側から突き上げてくる激
しい情動のために、その視覚もまた一瞬のあいだ破壊されてしまっている。そして、
このような距離化の不可能性こそがメロドラマ映画がおとしめられてきた理由であっ
たはずである4。メロドラマが感情の過剰さを特徴とする以上、そしてその表象のた
めにメロドラマ映画にクローズアップが構造的に要請される以上、盲目性(登場人物
の、更には観客の)は不可避的に特権的な感覚の喪失となる。
2. 母娘関係と盲目の連鎖
自分に注がれる上流階級のまなざしを洞察できないという事態を累積させていった
結果、ステラは視覚を喪失するほどの強烈な衝撃を受けることになった。そしてそれ
を代償に自らの「正しい」イメージを獲得し、ここに完全なメロドラマ映画のヒロイ
ンとして存在している。彼女は自らの過剰さを理解し、自分が結局のところ上流社会
において徹底的に場違いな存在にすぎないということを認識する。更には、そのため
に最愛の娘が恋人を失うことになるかもしれないということまで知ることになる。こ
うした状況において、娘のために自分ができることは自らを消しさることだけである
とステラは考える。
列車の直後のシークエンスで、ステラはさっそく夫の恋人であるモリソン夫人(彼
女の夫は既に亡くなっている)のもとを訪れている。ステラはモリソン夫人に向かっ
て、涙を湛え言葉をつまらせながら懸命に自分の思いを伝える。自分がスティーヴン
と離婚した後に彼と再婚するつもりでいるのならば、娘を引き取ってほしい、これか
らのローレルにはあなたのような母親が必要なのだ、自分ではなにもしてやれない、
あなたなら誰もが自慢する母親だ……。ここでもステラはほとんど盲目である。モリ
ソン夫人の顔に視線を向けても彼女の顔を見てはおらず、ただ自分の思いを理解して
もらおうと話すことのみに専念している。実際、ステラの視線のほとんどは宙を漂う
だけであり、特定のものに投錨されることはない。そして、モリソン夫人の方も次第
にただ熱心に聴くことのみに専念していき、視線はステラから逸れることが多くなり、
宙を漂い始めるのである。二人の視線が交わる瞬間はほとんどないにもかかわらず、
ただ思いを伝えようとすることとただ思いを理解しようとすることにおいて、二人の
心理的距離は無化されていく。このようなモリソン夫人のポジションはある意味で観
客のポジションに等しい。ステラの盲目のまなざしに抗うことができず、自らも盲目
となってしまっているのだから。そして、観客も彼女と同様に内部から沸き起こって
くる情動のために視覚を喪失している。
次のシークエンスでは早くもステラとローレルの駅での別れが描かれる。いつもの
ように父親のもとへ遊びにいくだけだと思っているローレルと、最愛の娘を夫とモリ
ソン夫人のもとへ完全に委ねてしまうことになると知っているステラとの認識のずれ。
こうした視点と認識の不均衡(見ることと知ること)はメロドラマの基本的な物語構
造でもある。このことをスティーヴ・ニールはイタリアの文学者フランコ・モレッティ
の議論を踏まえ、論文「メロドラマと涙」のなかで、「視点構造を横断する視線の交
換と目線の一致との拒絶に加えて、視覚的な視点と登場人物の認識とが互いに区別さ
れているという物語戦略も痛烈さが生じる原因なのである5」と論じている。このス
テラとローレルとの別れのシークエンスにおいては視線は交換されているが、互いの
認識が異なっていることによって痛烈さが生じることの典型例である。このシークエ
ンスでは切り返しが用いられることによって互いの視線は交わっている。すなわち、
視覚的な意味での視点は一致している。だが、別れに関するステラとローレルの認識
はまったく異なっており、心的な意味での視点にはずれが生じている。こうした不一
致が哀切さを生みだし、メロドラマ的な物語を紡ぎ出しているのである。ローレルは
これから始まる楽しい旅行の喜びにあふれており、列車の窓からステラに向かって元
気よく別れの挨拶をしている。だが、これが旅行などではないことを知っているステ
ラは哀しみを隠しながら娘と言葉を交している。ステラは走り出した列車の窓から身
を乗り出すローレルに向かい、私のことは心配するな、今夜はあの青いドレスを着る
のよ、私が心のなかで見ることができるようにと語りかける。二度とローレルを見る
ことはできないと分かっているステラには、ローレルを心のなかで見ること、心的イ
メージとして眺めることしか残されていない。手を振り、投げキッスを送るステラの
映像。切り返されたステラの視点ショットでは、列車が遠ざかっていき、ローレルは
見えなくなっていく。そして、さらに切り返された時に、ステラのクローズアップが
現われる。まなざしの対象を失ってしまったステラの視線は曖昧になっていき、目に
は耐え切れなくなった涙が浮かび始める。ステラにはもはや何も見えなくなる。フェ
イドアウトが掛かり、画面が見えなくなっていく一瞬のなかで、ステラは誰にともな
く顔を背ける。その微かな身振りのなかには、ローレルへの表現を抑圧された哀しみ
が現われている。
だが、この映画はここで終わりではない。更に、この視点と認識の不均衡が是正さ
れる瞬間が訪れるのである。前出の論文でスティーヴ・ニールは『忘れじの面影』や
『悲しみは空の彼方に』(ダグラス・サーク監督、1959年)などを例に引きながら視
点と認識の一致のタイミングが遅すぎる場合(登場人物が死ぬ場合)を、そして『神
が許し給うものすべて』(ダグラス・サーク監督、1955年)や『ビッグ・パレード』
(キング・ヴィダー監督、1925年)などを例に引きながら視点と認識の一致のタイミ
ングが遅すぎるわけではない場合(登場人物が死なない場合)を論じている6。そこ
で述べられているように、知っている者と知らない者との認識の一致の瞬間の組織化
が観客を泣かせることに大きく影響するのは間違いない。そして、知るタイミングの
遅れが致命的なものになるかもしれないという可能性において、観客の涙が流される
のである。だが、『ステラ・ダラス』においては、こうした構造は様相を異にしてい
る。ローレルが知る瞬間はステラの生死とは無関係であり、その知る瞬間自体もステ
ラとローレルの別れのすぐ直後に訪れる。自分が父親とモリソン夫人のもとに引き取
られることになっていると知ったローレルは、私の暮らす家は母親のいる家だと拒絶
する。だが、その母親が自分を預けることを提案しに来ていた事実を告げられると、
ローレルは即座にすべてを悟るのである。自分に対する母親の愛情と自分を失う母親
の悲しみとに動かされ、湧き出てくる言葉が次々と語られる。母親は列車のなかでの
友人たちの言葉を聞いていたのだ、なんて素晴しい母親だ、なんてかわいそうな母親
だ……。既にローレルは周囲にまったく注意を払っていない。母親が自分を愛してく
れていることを知っている彼女は母親の自己犠牲をすぐさま理解し、ステラの抑圧さ
れていた表現を補填しようするかのように語り続ける。家に帰らなければならない、
すぐに帰らなければならない……。この瞬間は認識の一致点であり、メロドラマにお
いて一つの頂点を形作る瞬間である。直前のシークエンスのステラと同様に、フェイ
ドアウトが掛かりつつあるなかでローレルは泣きはじめる。
しかし、この映画にはさらに逆転がある。認識の一致点を形作ったにもかかわらず、
その一致がもう一度破壊されるのである。ローレルが家に戻ってくることをモリソン
夫人からの電報で知ったステラは決断し、その電報を丸めて投げ捨てる。そして、彼
女は自分が娘との生活など望んではおらず、男との情事にこそ興味がある振りを装お
うとするだろう。帰ってきたローレルを前に彼女は享楽的な生活への偽りの欲望を語
り、その結果としてローレルは悲しみのためにステラから顔を逸らせ、画面から立ち
去っていくことになるのである。そして、ステラは画面から消え去ってしまった娘の
方をいつまでもじっと見つめ続ける。そして、またもフェイドアウトに消えていくな
かで、ステラは両手を顔に上げていき、泣き出してしまう。
このように、この映画の後半には、各シークエンスごとに内部の情動にただ囚われ
ているだけの人物のクローズアップ、すなわち視覚を喪失した盲者の映像が配置され、
締めくくられていく。母と娘のあいだで連鎖的な化学反応を起こしたかのように、交
互に視覚を喪失する事態が引き起こされる。もちろん、これはステラの自らによる表
現の抑圧、すなわち娘を自分から引き離すために真実の感情を隠蔽するという行為に
起因した連鎖反応である。娘を父親とモリソン夫人のもとへ送り出した時の駅でのス
テラの映像。そして、ステラの気持ちを直観的に理解したローレルの映像。更には、
もう一度娘を送り出した時のステラの映像。母娘の一体感ある関係を断念し娘を上流
社会へと送り出すためには、これほどの情動の連鎖的喚起を供物とする必要があった
のだと言えるだろうか。
ローラ・マルヴィが告発するように、通常、クローズアップは女性を見せるために
用いられることになり7、男性の表情がクローズアップで描き出されることは少ない。
したがって、通常の恋愛メロドラマ映画においてはもう一方の主人公である男性のク
ローズアップの使用が制限され、受難の女性のクローズアップだけが特権的な形象と
して立ち現われる。だが、この『ステラ・ダラス』においては母と娘という二人の女
性をめぐる受難の物語が語られているために、両者ともにクローズアップが用いられ
ることになる。しかも、両者間の感情の葛藤が描かれる以上、必然的にそれぞれのク
ローズアップが交互に現われることになる。ステラとローレルは互いの悲しみに反応
し合うように、連鎖的に視覚を喪失していく。そして、交互に現われてくる、視覚を
喪失した母娘のクローズアップの連鎖のあいだに観客は取り込まれることになる。合
わせ鏡のような盲目の映像のあいだで、光の乱反射のように激しく飛び交う哀切さの
圧倒的な強度に、めまいのような感覚を覚えながら抗いようなく巻き込まれていく。
3. 感情移入の不可能性
第1章ではメロドラマ映画の特徴としての盲目性について、第2章ではこの盲目性
が連鎖的化学反応が引き起こしていくという『ステラ・ダラス』の特異性について論
じた。最後に以下においてこの映画の結末に現われる盲目の映像が孕む別の特異性に
ついて簡単に触れることで論考を閉じたい。この映画の結末においても母と娘の二つ
の盲目のクローズアップが現われる。まずはそのクローズアップの様態を記述するこ
とから始める。
ローレルは母親の仕打ちに心を痛めながらも、恋人との関係に大きな期待を抱きな
がら上流階級へと参入していく。そして、最後にローレルは恋人と「幸せな」結婚式
を迎えることになる。これこそステラが望んだことであり、こうして上流階級へと参
入させるためにこそステラは身を切るような悲しみにも耐えたのである。だが、ラカ
ン風にまとめるならば、このように象徴秩序の参入にともなう去勢の痛みは痕跡を残
さずにはいない。結婚衣装に身を包み、大きな白いヴェールをかぶったローレルが結
婚式の直前に裏窓の前に呆然と立ち尽くし、外の暗い夜のなかに雨が降っているのを
眺めている後姿が映し出される。どうしたのかと問いかけるモリソン夫人に対して、
ローレルは本当の母親なら娘の結婚式にはどんなに遠くからでも来るはずだと、無表
情な顔に一筋だけ涙を流しながらあたかも自動人形のように答えるのである8。この
ローレルの映像はこれまでに論じてきたような視覚喪失の映像とは異なっている。こ
のローレルのまなざしも確かに何も見えてはいない。だが、これまでのように自ら制
御不可能なほどに内側からほとばしる情動のために、視覚が破壊されているわけでは
ない。逆に、自らの内側にぽっかりと空虚が開いているために外界を知覚できなくなっ
ているのである。ステラだけでなくローレルも当然望んでいたはずの愛する人との結
婚式の直前に、こうした空虚なまなざしが現われているという事態にはかなりの異様
さがある。このために観客はローレルが幸せであるとは思えなくなる
一方、外の雨のなかでは、落ちぶれてみすぼらしい格好をしたステラが結婚式に駆
けつけ、自分の娘を何とか一目見ようと濡れながら探し回っている。そして、モリソ
ン夫人がステラの気持ちを察してカーテンを開けておいてくれた窓越しに、ローレル
の結婚式を遠く眺めるのである。ステラは外のフェンスにしがみつき、ただひたすら
に見つめるのである。見つめ続けるステラと窓越しのローレルの姿は交互に切り返さ
れるたびに大きくなっていき、ステラによる娘への感情移入の度合が大きくなる様が
表現される。また、それらのあいだに巧みにロングショットが混ぜ合わされることで
両者のあいだの身体的、物理的、そして社会的距離までもが表象されていく。警官に
立ち止まるなと警告されながらも、ステラはただじっとローレルを見つめ続ける。顔
に掛かる白い大きなヴェールを上げてローレルが幸せそうにキスをする情景が窓枠越
しに大きく映し出される。そして切り返されると、ハンカチの端を噛みながら目に涙
を浮かべ、幸せそうにローレルをじっと見つめるステラのクローズアップが現われる
のである。その顔には涙が現われ、頬をつたって流れはじめる。ステラは目を下に向
け、自らの思いに更ける。そして、すぐにまた目を上げてきたときには、もうその目
には何も見えていない。窓のほうを向いたまま、じっと動かないステラの後ろ姿が映
し出される。もういいだろうと声を掛ける警官に促されるように、ステラはこちらを
振り向いて歩きはじめる。ローレルたちが楽しんでいるであろう光景は、歩いてくる
ステラの後ろでどんどん小さくなりながらも窓越しに見え続けている。ステラはハン
カチを噛むのを止め、顔を少し上向きにして歩きつづけている。カメラに近づいてく
る彼女の顔には微笑みが浮かんでいる。彼女はただローレルの幸せを噛みしめている
だけであり、その視覚は機能していない。
このように最後のシークエンスにおいても娘と母親の盲目の映像が現われている。
娘のクローズアップの特徴については既に簡単に述べた。だが、盲目を導いた情動の
過剰さが正か負かという違いはあるにせよ、それが観客を感情移入へと誘うという点
においては変わりがない。しかし、最後のステラのクローズアップは様子が異なる。
ステラは微笑みを浮かべながら匿名性の闇のなかへと消えていく。だが、ここではス
テラの望み(娘の幸せな結婚)が成就したという以上に、彼女の境遇の哀れさが突出
している。また、観客は結婚式直前のローレルの異様な盲目の映像を見てしまってい
るために、ステラのように手放しでこの結婚を喜ぶことができない。すなわち、ステ
ラと観客とのあいだに視点と認識の不均衡が現われているのである。カメラの方に近
寄ってくるステラの、視覚を喪失させながら微笑む最後のクローズアップ9。これは
この映画がほんのわずかだが通常のメロドラマ映画に対して軋みを生じさせている瞬
間である。観客はこの盲目の映像をそのまま模倣しえなくなっているのである。ステ
ラと観客のあいだに生じるこの感情のずれは縫合がされきれなかった場所であり、通
常のメロドラマ映画に対してこの映画が図らずも生み出してしまった小さな綻びであ
る。そして、このことは象徴秩序は転移的に生み出す過剰さを供物に延命を企て続け
るが、常に脆さを抱えていることの証でもある10。だが、この問題に関するこれ以上
の考察は本稿の範囲を超えている。機会を改めておこなうことにしたい。
1 Peter Brooks,The Melodramatic Imagination(New Haven:Yale Univ.
Press,1995),pp.56-57.
2 Tania Modleski,"Time and Desire in the Woman's Film" Virginia Wright,
ed.,Letter From an Unknown Woman(New Brunswick NJ:Rutgers Univ.
Press,1986),pp.252.
3 スティーヴン・ヒース「映画のセクシャル・ポリティクス」加藤幹郎訳、『GS』
21/2号、冬樹社、1985年、pp.331-347.
4 Linda Williamsはホラー映画やポルノ映画と並べてメロドラマ映画を論じており、
これら三つのジャンルにおいては登場人物の感情を観客がそのまま模倣してしまうこ
とになるため下等な映画と見なされてきたのだと分析している。ホラー映画において、
恐怖に顔を引きつらせる登場人物を模倣するように観客も恐怖に顔を引きつらせる。
ポルノ映画においては、快楽に溺れる登場人物を模倣するように観客も快楽に身を委
ねようとする。そして、メロドラマにおいては、悲しみに涙を流す登場人物を模倣す
るように観客もまた顔を涙で濡らすというわけである。だが、ウィリアムズはこれら
のジャンルが美学的鑑賞に必要とされる適切な距離の確保を不可能にしてしまうのは、
ハリウッドの古典的な映画ジャンルには収まりきらない過剰さを視覚化しているから
であると主張する。その過剰さとはホラーにおいては暴力、ポルノグラフィにおいて
はセックス、そしてメロドラマにおいては感情にほかならない。Linda
Williams,"Film Bodies: Gender,Genre,and Excess", Film
Quarterly,vol.15,no2(Summer 1991),pp.2-13.
5 Steve Neal,"Melodrama and Tears",Screen,vol.27,1986,pp.10.
6 Ibid.,pp.10-11.
7 ローラ・マルヴィ「視覚的快楽と物語映画」斎藤綾子訳、『イマーゴ』、青土社、
1992年2月号、pp.40-53
8 自動人形に関しては以下の拙論を参照。「盲目性の政治学」、『映像学』(日本映
像学会)第58号、1997年、pp.66-80.
9 メアリー・アン・ドーンはこのシーンを観客の感情移入を前提に論じている。「彼
女が微笑みつつその場を去り、カメラの方に向かって進み、クローズアップになると
き、彼女は、彼女の運命に感情移入している観客のためのあのクローズアップになる」
。だが、私がここで分析しているのはもちろんこの感情移入の綻びについてである。
メアリー・アン・ドーン『欲望への欲望』松田英男訳、勁草書房、1994、pp.122
10 メロドラマ映画は過剰さをどのように処理するのかという問題に関しては以下の
論文、特に「ヒステリーと過剰」という章を参照。ジェフリー・ノウェル=スミス
「メロドラマとは何か」米塚真治訳、『イマーゴ』、青土社、1992年11月号、
pp.34-39.