|
書評 |
|
|
大傍正規
|
||
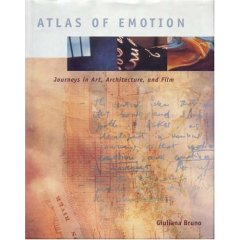 |
||
| ジュリアーナ�・ブルーノの大著『情動のアトラス(Atlas of Emotion)』は、芸術と映画の理論化において「触覚」がはたしてきた役割を検証し、映画理論/映画史における「触覚」の潜在的可能性を(再)発見した都市映画論である。従来の映画理論は、映画における映像と音響のダイナミズムや、その歴史的過程の多様性をフォルマリスティックなテクスト分析、あるいは実証主義的な観客の受容/言説分析などによって解明してきた。それに対して本書の著者ブルーノは、美術史家アロイス�・リーグルを経由してヴァルター�・ベンヤミンが練りあげたイメージの「記憶」と「触覚」という概念を援用し、映像テクスト上の情動の痕跡をモンタージュ写真のように貼りあわせることで、都市映画をはじめとする「場所」に関わる諸芸術を横断的に論じている。 今日の映画理論の文脈において、「触覚」という用語/概念の使用は、映画学者ノエル�・バーチが「触覚的空間の構築」[1] において検討するまで長いあいだ忘却されてきた。リーグルが明らかにしたように、芸術の基礎には触覚的-視覚的という知覚の両極があり、「視覚には遠くへのまなざし、深さ、あるいは表面の膨らみが結びつき、触覚には近くを見ること、表面、あるいは平面の存在が結びついていた」[2]。しかしながらベンヤミンのいう「空間と時間から織りなされた不思議な織物」、「ある遠さが一回的に現れているもの」としての触覚性をもつアウラとは、視覚と遠さ、触覚と近さという二元論的問題機制をこえたものである[3] 。まさに「触覚性」とは、われわれが建築を受容するさいに感じるような「時間を含み、多元的であり、何よりも経験であり、かつ再現できないもの」[4] である。にもかかわらずバーチにとっての「触覚性」とは、中世における絵画の受容のように、平面から立体へという空間の深度に対するイリュージョンとしての知覚の漸進的獲得を意味した。すなわち肩越しのショットや、カメラの運動、あるいは登場人物の配置/構図などによって、平面から立体的空間へと空間の深度を逓増させることで「触覚的空間」が知覚できるというのだ [5]。要するにバーチにとっての「触覚性」とは、観者が被写体に接触できると感じるような、あくまでも視覚的イリュージョンの問題にとどまるものであった。それに対してブルーノは、多義的な意味をもつ「触覚」を重視し、その意味で古典的映画においてはじめて触覚の概念が生じたのではなく、初期映画期においても十分に触覚的なフィルムが存在したと述べている。われわれが建築を経験するように、映画において表象される空間を「住む場所」として経験しようとするブルーノの方法論が明らかになる。 「情動的映像のアーカイヴ」と題された本書の理論的中枢である第八章において、ブルーノは諸芸術と映画の文化的相互作用を古今東西の「空間の触覚性」の実体化に焦点を当てて考察し、その成果は芸術理論と映画理論を横断するものとなる。われわれは実際に手にとったことのない物を視認しただけで知覚することには困難をおぼえる。かりに人間に触覚がそなわっていなければ、空間という概念すら認識することはできなかっただろう。このように空間とは、身体的な知覚よってはじめて発見されるものであり、実際の日常的な経験にもとづくものである。触れることによってはじめて欲望、好奇心、喜びが喚起され、それはわれわれに日常的な時間の経験をも開示するだろう。そうした時間の流れのなかで、知覚の変質をうながす触覚がイメージの痕跡にまつわる記憶をよびさまし、記憶は触覚によって生気を吹きこまれることで運動しはじめ、空間のなかを移動する「身体の運動能力」と関連をもちはじめる。すなわち映画における空間の触覚的側面は、イメージの痕跡からなる情動の地図を通じて、身体や人文諸学の交通=コミュニケーションの場として構築されるのである。 こうして著者ブルーノは、マドレーヌ�・ド�・スキュデリのバロック小説「クレリー」(1654年)の登場人物さながら、窃視者(voyeur)であり、なかつ旅行者(voyageur)である身となって、「旅」において自らの内面を凝視する。映画館という「場所」に愛着を覚えること(「トポフィリア」[6] )、スクリーンに映った場所に愛情をいだくこと、その場所に過去の映画史の痕跡を見いだすこと、そうしたことを通じて、ブルーノは芸術史、医学的言説、建築、写真、文学といった諸分野を横断し、最終的に本書は「わたしの《イタリアへの旅》」(第十二章)において自らの出自とその内面を発見する「旅」という体裁をとって幕を閉じることになる。一見すると、ある特定の場所に情動を見いだす彼女の言説は、今日まで連綿と続く物語を抒情的に解するロマン主義的なものに見えかねないだろう。しかしながら、われわれはそこに、地図帳(Atlas)に情動(Emotion)を見いだすこと、すなわち実証的かつ数学的な地理学に対して、精神分析が示唆した欲望/情動のメカニズムを接合するという偽装の背後にある、既存の映画史の権威=男性性を脱臼/切断するというフェミニズム的戦略を見落としてはならない。さまざまな映像テクストにあらわれる「旅する女性」の姿は、そのような既存の枠組みを破壊するものとしてくりかえし言及される。とはいえ本書をたんなるフェミニズムの書物として、あるいは触覚の書物として読むだけでは不十分である。本書は、「記憶のアーカイヴ」としての映画であり、物語の筋と登場人物という文学的伝統とは無縁の「マッピング」からなる「映像に映像を対立」[7]させたゴダールの『(複数の)映画史』(1998年)に比肩されるべきモンタージュとしての書物なのである。 本書『情動のアトラス』が喚起する「場所」の情動には、リーグルらヴィーン派の美学者たちがとらえそこなった社会変動を把握する歴史感覚が付帯していることも見逃せない。ミシェル�・フーコーは、1967年の建築サークルでの講演のさい「19世紀を覆っていた大きな強迫観念とは、周知の通り、歴史であった。�・�・�・それに対して現代は、むしろ空間の時代ということができるであろう。われわれは同時的連関の中に生きている。それは、並列性、距離の遠近、場所の移動、分散といったものがみられる時代である」[8]と切り出し、時間や言説を中心とした歴史学と、空間を中心とした地理学との交錯を論じ、いまだに私空間と公空間、家族空間と社会空間などといった超越的な空間の神聖化が存在していることを批判した。このように世界を「さまざまな地点を結びつけ、さまざまな縺れを交錯させる空間的ネットワーク」[9] としてとらえるフーコーの態度は、スクリーンをさまざまなヴェクトルが交錯する「地図」としてとらえるブルーノが共有しているものでもある。フーコーが監獄や植民地などの権力が介在する外的空間を問題化したように、本書はヴェンダース、ゴダール、アントニオーニ、グリーナウェイをはじめとして、ゲルハルト�・リヒター、ビル�・ヴィオラらの旅(移動)に関わる映像作品をモンタージュ的に貼りあわせることで、超越的で、自己充足的な映像作品の意味を解体し、各映像作家が単独ではなしえなかった新たな意味の付加に成功している。換言すれば、われわれに驚きをあたえるような一本の作品をめぐる具体的かつ詳細なテクスト分析が不在であるにもかかわらず、本書は何度となく読みかえしても新しい発見を得られる類稀な良書となっている。 最後に、「場所」が喚起する情動のなかで、喪の情動がはたしている役割についても瞥見しておこう。フロイトのいうように喪は「愛する者を失ったための反応であるか、あるいは祖国、自由、理想などのような、愛する者のかわりになった抽象物の喪失に対する反応である」[10] 。愛する対象を失ったことによって生じる喪/悲哀は、『ベルリン�・天使の詩』(ヴェンダース、1987年)の冒頭で、第二次大戦の傷跡ののこるカイザー・ヴィルヘルム教会から都市景観を俯瞰する天使(ブルーノ�・ガンツ)が感じているものである。ブルーノは『ベルリン�・天使の詩』における建築が、まるで女性の似姿のように「歴史的鏡像」になっているという。大都市ベルリンが戦争によって蹂躙された「廃墟のような女性」であるというのだ。クレリーのように、家庭という閉域を無効化することに成功しえた女性旅行家たちは、それまでの平凡な生活を想起し、きたるべき旅立ちの日に心踊らせ、旅先で何度鏡を覗きこんだことだろうか。『カラビニエ』(ゴダール、1963年)において、二人の女性が覗きこんだのは「旅先」から投函された、あるいは土産物/戦利品たる絵葉書であった。アントニオーニ映画のさすらう女性たちは、外界への興味そのものを喪失している。覗きこむ対象としての鏡像としての都市、それはまさに都市の痕跡=「廃墟のような女性」が「自己表現をする場所、すなわち主観と客観の絶えざる置換の空間として読解可能な場所」であるだろう。「諸連関の総体を宙吊りにし、無効化し、逆転させてしまう」[11]この鏡のような空間を、フーコーは非現実空間=ユートピアと、反=場、すなわちすべての場所の外部にある空間=ヘテロトピアと命名した。それは映画館のスクリーンのように、「互いに相容れない複数の空間ないし指定用地をひとつの現実の場所に並置させる力をもつ」[12] 場所でもあり、「雑多で、異質で、われわれの生活空間に対して神秘的かつ現実的な意義申立てを突きつける」[13] 場所である。その意味で本書は「情動の地図」を形づくることになる痕跡=イメージの諸断片をモンタージュすることによって、それまで不在であったヘテロトピアなる鏡像としての/複数の空間を模索しているだけでなく、地理学あるいは他の人文諸学に対して開かれたコラージュとしての書物であるといえるだろう。 |
||
| 注 | ||
|
[1] Noel Burch,“ Building a Haptic Space”, in Ben Brewster ed. and trans., Life to Those Shadows (University of California Press, 1990), pp. 162-185. |
||
