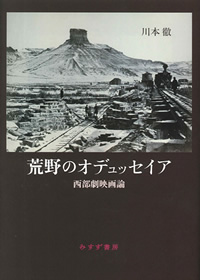|
伊藤 弘了
註 [1]京都大学大学院教授で映画学者=批評家の加藤幹郎氏によれば、ジャンル映画とは「スタジオ・システム下で製作配給公開されたフィルムのこと」であり、それはつまり「古典的ハリウッド映画の別名」だということになる。(西部劇をも当然そのなかに内包する)ジャンル映画に関する総体的かつ本質的議論に関しては加藤氏の『映画ジャンル論―ハリウッド的快楽のスタイル』(平凡社、1996年)が必読である。 [2]ヘイルズ・ツアーズや映画館/観客論の詳細については加藤幹郎氏の『映画館と観客の文化史』(中公新書、2006年)を参照されたい。 [3]また、この章では議論の前提として、西部の文明化のプロセスの中で歴史的に馬/駅馬車から列車へと移動媒体が変化したことや、西部劇映画においても駅馬車や列車が主要な運動媒体として特権的な表象に与ってきたことをジョン・フォードの『リバティ・バランスを射った男』(1962年)などの重要な映画に触れながら的確に整理している。ちなみに、映画における馬および列車の表象問題に関しては、加藤幹郎氏の『映画とは何か』(みすず書房、2001年)の第2部第Ⅳ章「列車の映画あるいは映画の列車―モーション・ピクチュアの文化史」や『列車映画史特別講義―芸術の条件』(岩波書店、2012年)に詳しい。 [4]映画における風景表象の問題を早くから強調してきた加藤幹郎氏は「アニメーションと実写とを問わず、映画における風景の表象の問題は、これまでほとんど閉じられつづけてきた」(『表象と批評―映画・アニメーション・漫画』)と指摘している。著者の問題意識は明らかにこの加藤氏の姿勢から影響を受けており、本書はそのすぐれた実践の成果ともなっている。 [5]加藤幹郎氏の『映画の領分―映像と音響のポイエーシス』(フィルムアート社、2002年、294頁)からの引用。著者を含め、多くの読者が加藤氏のこの言葉に勇気づけられたものと思われるし、言うまでもなく筆者もそのうちの一人である。
|