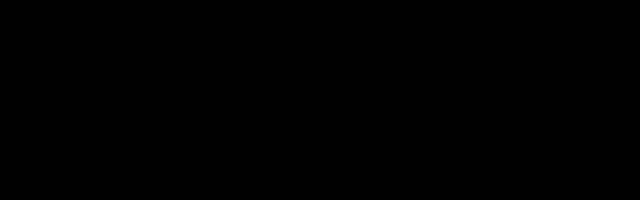顔の強度/手の軌跡
――クリント・イーストウッド『マディソン郡の橋』
藤井 仁子
“I have a photographic
memory.”
――True Crime (1999)
1
女の仕事とは、手を酷使することである。料理をすること、洗濯をすること、掃除をすること、庭の植木の世話をすること――いずれもさまざまに手を酷使することによってなされる。だからあかぎれの手は、彼女が家事労働に熱心にいそしんでいることの証しとなりうる。
田舎の平凡な主婦と都会から来た写真家との束の間の恋と別れを描いた『マディソン郡の橋』(クリント・イーストウッド監督・主演、1995年)において、家庭の留守をあずかる女主人公の存在は、純粋な手の運動にまで還元されている。その多様な手の運動を、老いを重ねることでいっそうの凄味をおびるに至った、クリント・イーストウッドその人の圧倒的な顔の強度の周囲に配すること。『マディソン郡の橋』とは、そのように目論まれた映画だとひとまずいうことができる。
実際、派手なイタリア訛りで農場の主婦を「熱演」する、ここでのメリル・ストリープの手の動きのせわしなさは、リアリズムの自然な要求をほとんど超えているというべきだ。それを単なるオーヴァーアクトと見なし、これだからオスカーなど獲るような「名女優」は困ると、したり顔でつぶやいてみてもはじまらないだろう。述べたように、この映画でのメリル・ストリープは、なによりもまず、〈手〉として現れているからだ。メリル・ストリープ演じるヒロインがわれわれの前に姿を現す、最初のシーンから見ていこう。
ある夏の日曜の午後、これから四日にわたって家を空けようとしている家族のために、ただ独り留守番をつとめることになっているメリル・ストリープが食事の準備に追われている。一家は、イリノイの州祭りで開催される品評会に自慢の子牛を出そうというのだ。彼女――フランチェスカは、ミトンをはめた左手でフライパンの柄を握りしめ、右手で料理をかきまわしては時折外の様子をうかがいつつ、マリア・カラスの歌声が流れるラジオのヴォリュームを上げるため、右手を大きく伸ばしてもみせる(イタリア出身の彼女にとって、ラジオ放送のイタリア・オペラは、なつかしい故郷と幻滅と倦怠に彩られたこのアイオワの農場とを結びつけてくれる唯一の紐帯なのだが、無惨にもその歌声は、やがて食堂に入ってきた娘によって流行りのポップ・ミュージックへと変えられてしまうだろう)。イーストウッドの指示によっていつもより十キロほど増量したらしいメリル・ストリープのここでの一連の動作は、ガニ股気味のだらしない姿勢で野暮ったい田舎のおばさんになりきってみせているせいもあり、せわしないことこのうえない。できあがった料理の皿を並べるため、台所と食卓とをあわただしく往復するあいだもおどけるように両手を拡げてみせるといった調子で、やがて家族が食卓についた後も、食前の祈りもそこそこに料理に手をつける家族を見守りながら、手で十字を切って膝にナプキンを拡げ、それでもまだ自分の食事には手をつけることなく、やれやれといったようにテーブルに両肘をつき、両の掌のなかに頬をうずめる。一息ついたのも束の間、今度は夫のために冷蔵庫へとソースを取りにいき、扉は去り際にひょいと足で閉めてみせ、再び着席すると食卓にたかる蝿を手ではらいのけ、また頬杖をつきかけるが、なぜか思いなおしたように掌を頬に押しあてるのはやめ、自分の食事に集中する家族の一人一人を愛情と疲労のないまぜになった複雑な面持ちで眺め渡しながら、それでも手だけは落ち着きなく、後れ毛を指でなぞっているところでこのシーンは終わる。……この家庭では、来る日も来る日も、おおかたの家庭がそうであるように、こうした情景が際限もなくくり返されているのだろう。かといって、これ以上の「幸福」を想像することも現時点でのわれわれにとっては難しい――そんな情景を見つめながら、われわれは女の労働がなによりもまず手の労働であることを確認し、その手が家事労働における一個の部品として、台所なら台所に隷属しつつ、精妙に作動するさまに目を見張るのだ。
先ほどこのシーンが、われわれの前にメリル・ストリープが姿を見せる最初のシーンだと書いたが、これは正確には間違っている。この映画の物語は、フランチェスカの死後、葬儀のために子どもたちが実家に駆けつけてくるところからはじまっており、彼らが遺された手記を読み進むうちに、貞淑そのものに見えた母親に秘密の愛人が存在したことを知らされ、はじめは反発をおぼえるのだが、やがてその真情を汲むに至るという構成をとっている。それ自体としては救いがたく凡庸な筋立てだが、ここで重要なのは、われわれがこの映画ではじめてメリル・ストリープの姿を眼にするのは、子どもたちが遺品のなかに発見する肖像写真としてだということである。それが、彼女の「運命の恋人」であった写真家によって撮影されたものだということはすぐにあきらかになるのだが、貸し金庫にあずけられた一九六五年付けの封筒に収められたこの写真のなかで、屋根付き橋のたもとにたたずむフランチェスカは、はにかんだように、やはり両手を頬に押しあてて立っているのである。回想形式をとるこの映画で、すでにこの世の人ではなくなっている女主人公を観客に提示する最初の映像において、彼女の両手がわざわざ頬に押しあてられていることからも、この映画において彼女の手がいかに重要な役割を果たすことになるかはあきらかであろう。しかも、それが彼女の最愛の写真家によって撮られたものであるからには、そこには彼女の、夫や子どもにも見せたことのないような、もっとも活き活きとした姿が定着されていなければならないはずだ。その写真において、もっとも雄弁に自らの存在を主張している身体的部位が手であるということ――それが重要でないはずがあろうか?
こうして、『マディソン郡の橋』を見るにあたっては、日常空間のなかで女の手が描き出す多様な運動の軌跡を注視する必要のあることがわかる。しかもその、単調で報われない家事労働における隷属的な部品としての女の手が、そこから逃れたくとも至当なる逃げ場を見いだすことのできないまま、ついに行き場を失って自身の頬へと自閉的に押しあてられるしかない状況に置かれていることを見逃さなかった者であれば、今後この映画が、女の手の行く末を描き切ることに意を注ぐであろうことは容易に想像しうるはずだ。それを見逃したとき、映画『マディソン郡の橋』は凡俗な「ハーレクィン・ロマンス」へと堕する。同時に、そうした手の運動は、いわゆる「アクターズ・ステュディオ系」の心理的な演技とも区別されるべきであろう。半ば口元を隠すようにあごのあたりにやった手を神経質に這いまわらせ、上目づかいの眼差しに孤独の翳りをおびさせながら、シニカルに唇の片端でももちあげてみせれば立派なアクターズ・ステュディオ系俳優のできあがりだが、ここでメリル・ストリープがくりひろげてみせる手の運動は、その滑稽さすれすれの執拗な反復において、ついには心理の自然な表現であることをやめるというべきである。むろん多くの場合、彼女の手が心理の表現として機能していることは否定できない(後れ毛をなぞる指が彼女の倦怠の表現であるように)。にもかかわらず、彼女の手がこのフィルムで描き出す運動の軌跡は、女の手が家事労働における隷属的な部品の地位にまでおとしめられている事実を一方で暴きたて、また他方では――後述するように――手のもつ新たな可能性を彼女自身に向けて提示してさえいるのである。やがて彼女は、自分の手がすることに自分で驚くことになるだろう。先行するなにものかの表現として手が後につづくのではなく、手こそが彼女を新たな関係へと導いてゆくのだ。あって当然のように思われている手が、それ自体で奇跡のように思われはじめるのはこのときである。その限りにおいてではあるが、『マディソン郡の橋』と比較されるべきなのは、類似したプロットをもつ『逢びき』(デイヴィッド・リーン監督、1945年)のようなよろめき型の恋愛メロドラマというよりも、ロベール・ブレッソンの一連の作品であるかもしれない。