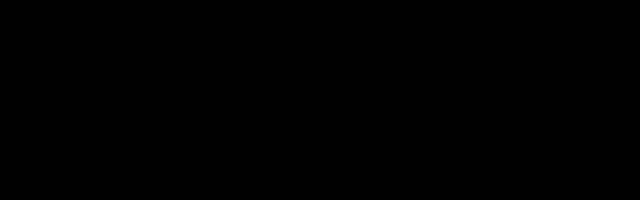5
はたしてあの退屈と倦怠とが帰ってくる。これといった不満のなにもないことが最大の不満――そんな日々の暮らしのなかで、あるときは台所に、またあるときは洗濯機にその手を隷属させるうち、いつか体験したはずの手の冒険は、早くも遠い日の思い出へと変わりはじめている。確かに耳にしたように思われた物質への誘いの声など、あの夜虫たちが教えてくれたように、一時の幻聴にすぎなかったのだろう。家庭を築き、その平和を維持すること――それが人間の勤めというものだ……。
数日後、叩きつけるような激しい雨の降るなか、フランチェスカは夫とともに車で町に買い出しに来ている。夫が戻るのを独り車のなかで待っている彼女の視線の先で、水滴が伝う窓ガラスの向こうに徐々に見えはじめたものはなんだったろう? あの男が――あの顔が、傘もささずにずぶ濡れになってそこに立っているのだ。顔の皺は苦悩からか、いっそう深く刻まれていよいよ傷のように見え、薄くなった頭髪は濡れて額に貼りついている。この顔を見て絶句しない者があろうか。男は、〈顔〉としてのおのれの存在のすべてを賭けて、もう一度だけ女を〈外〉へ――だが、どこの?――誘おうとしているのだ。
雷鳴が轟き、運転席に夫が帰ってくる。ゆっくりと車が進みはじめたそのすぐ先を、あの男の乗る青緑色のトラックがゆく。リア・ウィンドウ越しに見える男は、すでに〈顔〉であることの可能性を使い切り、後ろ姿だけになっている。交叉点の信号が赤に変わり、二台の車は縦に並んで停止する。フロント・ガラスを幾筋もの水滴が伝って流れ、あふれる涙をぬぐうかのように眼の前をワイパーが往復しつづける。その往復運動の向こうで、すでに思い出の彼方へとにじみはじめたかに見える輪郭の定まらない後ろ姿は、なにかを取り出しかと思うと、それをバックミラーにそっとからませる――フランチェスカが贈った十字架のペンダントだ。信号が青に変わっても、前の車は一向に発車する気配を見せない。運転席の夫は苛立ち、助手席の女はドアの把手を握りしめる。前の車の助手席に滑り込むまでほんの数歩で充分だろう――把手を握る手に力がこもる。女はもう一度だけ、手を日常の仕事以外の目的に使おうとしているのだ。ニンジンを削ぐのでも、カーペットのほこりをはたくのでも、トウモロコシ畑の手入れをするのでもなく、そこから自分を解き放つため、愛する男のほうへ差し伸べるために自らの手を使おうとしているのだ。女もまた、最後の力をふりしぼって全身を〈手〉にする……。
けたたましく鳴るクラクションの音にようやく動きはじめた前の車は、テール・ランプの赤い光だけを残し、交叉点を左に折れて――もはや軌跡を共有することなく――遠ざかってゆく。左折した瞬間に、窓ガラスからのぞく男の顔が一瞬こちらを振り返ったように見えたが、使い切られたかのようなその顔の表情は判然とせず、降りしきる雨ににじんで消えた。
*
監督=俳優としてのクリント・イーストウッドは、老いを重ねるごとに、ますます純粋な〈顔〉へと還元されてゆくように思われる。顔こそ、時が物質的な痕跡として残酷に刻まれてゆく場にほかならないからだ。イーストウッドの顔は、恐るべき忍耐と強靭さによって、その持続にただじっと耐えている。クリント・イーストウッドの顔とは、そこで記憶の総体が絶えず結晶しつづける力動的な場である。