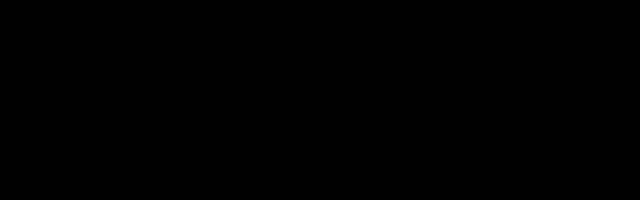
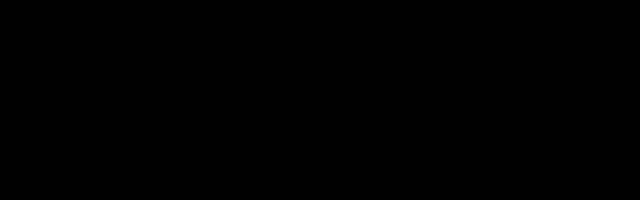
風に舞う女たち 女優論
加藤幹郎
| 1 アイダ・ルピノ | 2 デルフィーヌ・セイリグ | 3 ジーナ・ローランズ | |
| 4 キャサリン・ヘップバーン | 5 テレサ・ラッセル | 6 オリヴィア・デ・ハヴィランド | 7 ヴェロニカ・レイク |
| 8 ジュリエット・ビノシュ | 9 ロザンナ・アークェット | 10 イザベラ・ロッセリーニ |
| 11 マルーシュカ・デートメルス | 12 ハッティ・マクダニエル | 13 ハンナ・シグラ | 14 ベティ・デイヴィス |
| 15 ジェーン・バーキン | 16 ジョーン・フォンテイン | 17 ミシェル・ファイファー | 18 グロリア・グレアム |
| 19 マリア・シュナイダー | 20 アンナ・マニャーニ | 21 フェイ・ダナウェイ | 22 アリダ・ヴァッリ |
アイダ・ルピノはいわば忘れられた女優である。ジャン=リュック・ゴダールをのぞけば、映画人がしかるべき敬意をもって彼女にオマージュを捧げた例をわたしはしらない。彼女が映画史からわすれられたのには、それなりの理由があるにちがいないが、おもうに、それはルピノが男のために演技しながら、男を喰ってしまうからである。つまり男たちにとっては、どうにも我慢のならない実力を、この女優(兼監督)はもってしまったのだ。
ハンフリー・ボガートもジョージ・ラフトも、彼女の情熱的な愛情表現をまえにすると、とたんに神通力をうしなってしまう。ルピノの奇跡のような表情は、こうした男性スターたちの演技力を去勢する。ギャング映画を撮っているはずの男性監督の統御をすりぬけ、ルピノは、男のための映画を女のための悲劇にしてしまう。つまりギャング映画としてはじまったはずの映画を、彼女はそのたぐいまれな演技力によって、ギャングを愛した女の悲恋物語としておわらせるのである。彼女の演技力は男優や男性監督、あるいは男性プロデューサーの思惑をこえて、ジャンル映画の限界を拡張する。こうしたことは映画史上そうめったに起きるものではない。男を誘惑し破滅させるリタ・ヘイワースやバーバラ・スタンウィックのような妖婦系ですら、フィルム・ノワールのなかで男優を喰ってしまうようなことはついになかったのだから、ルピノの演技力が、いかにハリウッドの男性優位社会をゆるがすものであったかが想像できようというものだ。たとえばハリウッド黄金期に撮られた二本の傑作を思いだしていただきたい。『夜までドライブ』(40年)と『ハイ・シエラ(終身犯の賭け)』(41年)である。ともにラオール・ウォルシュの演出らしく、一見タフガイたちのアクション映画のようにみえる。実際『夜までドライブ』の前半部は、道をあらそうトラック運転手たちの荒っぽいアクション映画以外のなにものでもない。
ところが後半部からはアイダ・ルピノの独壇場である。嫉妬にくるった彼女が神経症的情熱で男にせまるとき、映画はその首尾一貫性を見失う。映画のなかの男たちは彼女の情熱をまえに後退し、映画そのものがルピノの狂乱にうろたえる。ひとりの悪女の狂気に、登場人物ばかりか、映画それじたいまで巻きこまれてしまうのである。こんな事態は、男性プロデューサーの強権によってたつハリウッド映画では、本来ありえないことなのだ。 『ハイ・シエラ』のエンディングはどうだろうか。銃弾にたおれるギャング、ハンフリー・ボガート。彼の遺体にとりすがる情婦アイダ・ルピノ。ここまでなら『ガラスの墓標』(ピエール・コラルニック監督70年)のセルジュ・ゲンズブールとジェーン・バーキンの、あの身を切るようなエンディングとたいして変わりはなかったろう。それは愛人を失った女の悲しみを最上級でうたいあげるが、それ以上のものではない。アイダ・ルピノがジェーン・バーキンを凌駕するのは、ここからである。
泣きさけんでいたルピノが、やがて警官に抱きかかえられるようにしてボガートの遺体からはなれるとき、彼女は男のつぶやいたことばの意味を噛みしめている。そのときキャメラがクロースアップでルピノの顔をとらえ、その顔の表情が映画史上最大のスペクタクルとなる。彼女の顔のうえには、最愛の男をうしなった女の悲しみと最愛の男を理解した女の喜びの両方が書きこまれているのだ。おそすぎた理解と最大級の悲嘆。かつていかなる女優のクロースアップが、こうした複雑で困難な表情をスクリーンにとどめることができただろうか。
スタジオ・システムが法的に崩壊する一九四九年以降、アイダ・ルピノは主演をこなしながら、みずから製作、脚本、監督にのりだす。そしてハリウッド映画史上初の男性メロドラマをものし、ハリウッドの男性支配体制にひびをいれるのだが、この話はまた別の機会にゆずらねばならない。
感性と知性と美貌において群をぬき、それゆえ世界の超一流監督に重用された女優。それゆえ映画史上に燦然とかがやくべき女優。にもかかわらず、ラディカルな、あまりにもラディカルな映画作家と組むことが多かったために、そしてその繊細な演技ゆえに、あまりにも評価されることのない女優。もっとも重要でありながら、もっとも知られることのない女優。それがデルフィーヌ・セイリグだ。
わたしが最後に銀幕にデルフィーヌをみたのは、『ゴールデン・エイティーズ』(シャンタル・アケルマン監督85年)だったから、そのとき彼女はもう五三歳だったことになる。その十一年前、彼女はゴダール以来もっとも先鋭的な作家シャンタル・アッケルマンと組んで、映画史上屈指の女性映画『ジャンヌ・ディールマン』(74年)でタイトルロールを演じていた。そしてそれが同じ女優と同じ女性監督によるものとはにわかに信じがたい透明さで、ミュージカル映画『ゴールデン・エイティーズ』のデルフィーヌは、何十年もまえに別れた男との再会の歓びにうちふるえる人妻の歓喜の歌を、官能的な表情と艶のある声で歌ってみせたのである。まるで少女のように。
それから五年後の一九九〇年、彼女は五八歳の若さでひとしれず逝ってしまった。
実際、女優としての彼女の影の薄さこそ、ここで特筆せねばならないデルフィーヌ最大の特質であろう。彼女はおおげさな身振り、激情的なせりふまわし、ようするにハリウッド・メロドラマ的な演技をいっさい拒絶した女優だった。
それは、あの狂気の女優マリア・シュナイダーにすら真似のできなかったことである。デルフィーヌに比肩しうる女優はといえば、グレタ・ガルボくらいしかおもいあたらない。じっさいデルフィーヌはサイレント期の女優のように寡黙だ。
出世作『去年マリエンバートで』(アラン・レネ監督61年)から名高い『インディア・ソング』(マルグリット・デュラス監督75年)まで、デルフィーヌはまるでもの言わぬアンドロイドのように鏡の迷宮を彷徨した。鏡面のように静謐な彼女の演技をまえに、観客は無限の鏡像のなかに逃げさってゆくデルフィーヌを、ものぐるおしくみおくるしかなかった。じっさい恋とはにげさるものであるとすれば、デルフィーヌ・セイリグが生涯演じつづけた女は、永遠の恋愛対象だった。
ほんとうにそこにいるとはおもえない希薄な存在感で、彼女は逆説的に映画女優の存在感とはどのようなものであるかをしめしえた最初の女優である。映画(モーション・ピクチュア)が運動(モーション)を再現する機械であるとすれば、デルフィーヌがその身体で記録したものは、生が死にいたるまでの長い長いスリップ状態であった。車輪は回転をとめているのに、車体は永遠に滑走しつづけている。停止までの漸近線的スローモーション。それが彼女の演技だった。それをみた多くの観客は、後部座席から外に放りなげだされてしまったのだ。
一九六〇年代から七〇年代にかけて、物語映画が実験の頂点をきわめるとき、彼女は多くの映画作家たちに多大なインスピレーションをあたえ、映画の歴史をうごかす原動力であった。以下にあげるのは、そのデルフィーヌ・セイリグに惑溺した錚錚たる映画作家の一覧である。アラン・レネ(『去年マリエンバートで』と『ミュリエル』63年)、ジョセフ・ロージー(『できごと』67年と『人形の家』73年)、ルイス・ブニュエル(『銀河』70年と『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』73年)、マルグリット・デュラス(『インディア・ソング』と『ヴェネツィア時代の彼女の名前』76年)、そしてシャンタル・アケルマン(『ジャンヌ・ディールマン』と『ゴールデン・エイティーズ』)。このほかにもデルフィーヌ・セイリグは、『最後の叫び』(74年)でマニエリスト作家ロベルト・ファン・アカレンと組み、先頃ようやく日本でも公開された幻の映画『フリーク・オルランド』(81年)ではウルリケ・オッティンガーと、『アイドリング』(79年)ではパトリシア・モラーズと組んだこともある。
六〇年代以降の映画史で、もっとも先端的な特集上映プログラムを組もうとするフィルム・アーキヴィストは、その特集がデルフィーヌ・セイリグへのオマージュにほかならないことを発見するだろう。
もっとも現代的な女、もっとも今日的な女を演じた女優をひとり選ぶとしたら、ジーナ・ローランズに一票を投じない映画ファンはちょっといないのではなかろうか。 むろん彼女に票をいれるということは、彼女が主演した映画の監督にして夫のジョン・カサヴェテスに票を投じるということでもある。
つまりそれはジーナが主演したジョン・カサヴェテスの三大傑作映画『こわれゆく女』(74年)、『グロリア』(80年)、『ラヴ・ストリームズ』(84年)の抒情的ラディカリズムに、しかるべき敬意をはらうということでもある。これらの映画が撮られた一九七〇年代から八〇年代は、アメリカの個人主義とフェミニズムが家庭夫婦生活の完全なる破綻を宣言した時代だった。そういう困難な時代に、ジーナ・ローランズはいかなる女性を演じてきただろうか。
おどろくべきことに、彼女は妻であり母であることを前面におしだしながら、にもかかわらず、過去のハリウッド・メロドラマ的遺産からいっさい自由な女性を演じてきた。そんな離れ業が可能な女優は、ジーナ・ローランズをおいてほかにはいまい。じっさい男にいかなる助言も仰ぐことなく我が道をゆく彼女のタフガイぶりは、その困難性ゆえにしばしば小さな狂気に彩られてきた。まるで伝統的ファミリー・メロドラマからも、流行のロマンス神話からも無縁な女は神経症を患わねばならないかのように。 しかしジーナ・ローランズは、個人主義に立脚したある種の神経症がいささかも脆弱なものではなく、むしろ猥雑な日常と日々の燃焼のなかで真摯な熱情となることを証明してみせた。
彼女の強迫的な愛情表現、その緩やかな「精神の病い」は周囲の者たちを困惑させながらも、かれらに魂の拠りどころを再考させてきた。たとえば八〇年代映画のベストワンというべき『ラヴ・ストリームズ』はどうか。
この映画は愛と孤独とエゴイズムについての省察であり、カリフォルニアの明るい陽光のもとで撮られたアンチメロドラマである。じっさいのところ、この映画は、ひとが親子夫婦姉弟友達として築きあげるさまざまな人間関係のあらゆる切断面に、シュークリームの皮のようにかぶさってくる日常的澱をめぐる物語である。
そしてジーナ・ローランズは、日々の澱を押し流すいわば海流のような女であるひとびとが澱のなかに安息しようというときに、彼女のあふれんばかりの愛情がすべての澱を押し流してしまう。しかもジーナには、自分の愛情がなぜ家族には受け容れがたいのかがわからない。洪水のような愛情がなぜ家族を窒息させてしまうのかが、彼女にはどうしても理解できないのだ。
彼女は犀のように我が道を突きすすみ、その愛情の角で家族を突き刺す。ジーナの四角い顔は彼女のその迷いのなさを物語っている。その意味で彼女はハードボイルドな女である。彼女が家族を過剰に愛するのは、けっして彼女の愛が対象に固着しているからでも、また周囲がそう信じたがるように、彼女が精神に異常をきたしているからでもあるまい。
ジーナが家族を過剰な愛情でつつみこむのは、彼女が信念をまげない女だからである。彼女は、愛とは海流のようにとめどなく流れるものだと信じて、翻意することがない。その不動の信念においてハードボイルドなのである。
うつむくジーナ、目をむき、まくしたてるジーン、ひとを説得しようするジーナ、うんざりするジーン、ころがるように走りだすジーナ、ふたたび説得を試みるジーン、そして失神し、放心するジーナ。
そこには今日的なアメリカ女の自由な感情と運動の奔流が、そして過去のいかなる映画的約束事にも束縛されないカサヴェテスの天才的なきらめきが満ちている。
4 キャサリン・ヘップバーン スフィンクスのように考え、豹のように飛びかかる
コーエン兄弟のフィルムはいつも古典ジャンル映画のみごとなマニエリスム的模倣である。『未来は今』(ジョエル・コーエン監督94年)も例外ではなく、ヒロインの演技は古典映画にふたつの参照系をもっている。ひとつは人民喜劇『群衆』(フランク・キャプラ監督41年)のバーバラ・スタンウィックであり、いまひとつはスクリューボール・コメディ『赤ちゃん教育』(ハワード・ホークス監督38年)のキャサリン・ヘプバーンである。『未来は今』の痩せ形のヒロインが体型以外のなにをキャサリン・ヘプバーンに倣ったかといえば、それは彼女の歌うような早口である。ころころと転がりながれるヘップバーンのエロキューションは、彼女の自由奔放な生きざまをそのまま要約するかのようにとどまることをしらない。
じっさいキャサリン・ヘプバーンの声は、サイレーンの魔女の歌声のように執拗に男たちにまといつき、かれらの自己同一性をいちまいいちまい剥ぎとっては、喜劇的谷底へとつきおとす。男たちはその谷底から這いあがると、ようやくキャサリン・ヘプバーンの嵐のような求愛をうけいれる決心をするのだ。
映画が音声をもちはじめた一九三〇年代初頭に、ヘプバーンのような声の女優がデビューしたのも偶然ではあるまい。喜劇映画がチャップリンやキートンの無声スラップスティックであることをやめたとき、声の喜劇があらたなサブジャンルとして誕生し、キャサリン・ヘプバーンの世界がひらかれる。彼女のエロキューションは、いわば絹のすれあう音から鞭のしなる音までを連続的にあびせるようなものだ。さえずるような台詞まわしから断固たる悲鳴まで、波のように間断なくおしよせる彼女の声は、トーキー映画の観客を魅了する。
かくしてキャサリン・ヘプバーンが、その熱情を文字どおり声楽をとおして表現するとすれば、彼女の魅力は、その直接的身体性にあることになる。彼女は思考し、行動する豹である。彼女はスフィンクスのように考えこんだかとおもうと、つぎの瞬間には『赤ちゃん教育』の「赤ちゃん豹」のように、男たちに襲いかかる。失敗の連続にしょげかえっていたかとおもうと、突然眼光するどく男たちを射すくめる。おそろしい速度でおもいをめぐらしながら、それ以上におそろしい速度でしゃべりつづける。自由闊達、天衣無縫、スポンテイニァスな豹の身のこなし、それが女優キャサリン・ヘップバーンの真骨頂である。
おどろくべきことに、デビューまもない『人生の高度計』(ドロシー・アーズナー監督33年)の女性パイロット時代から、すでにヘプバーンはその身体において思考と行動、愛情と運動の一致をみせていた。つまり彼女は男を愛するがゆえに飛行し、男を愛するがゆえに墜落するのだ。
スクリューボール・コメディの最高傑作『赤ちゃん教育』(38年)はいうにおよばず、ゲイのジョージ・キューカーの手になる一連のフィルム(『男装』36年、『素晴らしき休日』38年、『フィラデルフィア物語』40年、『火の女』42年、『アダム氏とマダム』49年)における彼女の身体感覚のすばらしさは、いくら讃歎の声をあげてもたりないくらいである。
キャサリン・ヘプバーン、ハリウッド・トーキー史上最高の映画女優。一九五二年までの彼女の全作品をナイトレイト(硝酸銀/可燃性)フィルムでみられるなら、わたしは生涯を棒にふってもかまわない。
女優とは切断の産物である。だれもがしっているように、フィルムのうえで女優のペルソナは切り刻まれている。彼女の美しい肢体はみえない鋏をいれられ、クロースアップによって赤い唇は顔から、そしてその顔は身体から切りはなされている。挿入されるインサートカットが彼女の身体を蹂躙し、テレサ・ラッセルのふくよかな頬も数秒をこえて観客の注視にゆだねられることはない。だから映画女優とは、フランケンシュタインの怪物のようなものだ。銀幕という名の光かがやく手術台のうえで、モンタージュとよばれる特殊な整形施術をほどこされ、彼女は、うすぐらい映画館のなかで観客の頭の洞窟に棲みつく。
いま見たばかりのテレサ・ラッセルの全体像をおもいだそうとしても、観客の目にやきついているのは、ただ唇にまといつく髪の毛やゆれる乳房やうつむいた顎ばかりである。彼女は、その身体の各部位に還元されるか、不完全な光合成にいたるばかりで、いかなる意味でも統一的全体ではありえず、それゆえつねに男たちの視線をのがれつづける。
映画『ジェラシー』(ニコラス・ローグ監督79年)のなかのアート・ガーファンクルがテレサ・ラッセルに恋をするのも、そのようにしてであるし、彼女の奔放な生にふりまわされる事情はまた、この映画の監督ニコラス・ローグにとっても同じことだろう。この監督もまたテレサ・ラッセルに恋をする。じっさい恋愛映画を撮っている男性監督が、その主演女優と恋におちないような現場で、まともな映画が生まれるはずがない。しかしスクリーン上で女優をおとなうこの比喩的な切断は、『ジェラシー』の物語世界では字義通りの切断となる。奔放な生活のはてに睡眠薬自殺をこころみたテレサ・ラッセルは、手術台のうえで喉を切り裂かれ、その傷口に強制呼吸器を挿入され、血をながしながら、男たちの手によって、フランケンシュタインの怪物のように、この世にむりやり蘇生させられるからだ。
テレサ・ラッセルは、笑いさざめき、泣きさけびながら、男たちの思惑とは別の地平で、じぶんじしんの欲望と恐怖に身ひとつでたちむかっている。しかし彼女の身体の再切断と再合成は、さながら生命の神秘をもてあそぶ科学者たちの実験室のように、この映画のなかで何度も執拗にこころみられる。欲望と恐怖が本来、切断と合成の産物でしかない以上、『ジェラシー』の分裂症的な編集は、エイゼンシュテインの『戦艦ポチョムキン』(25年)以来最大の映画史的事件であり、ルソーの『新エロイーズ』以来最高の文学史的成果である。
『ブラック・ウィドー』(86年)の監督ボブ・ラファエルスンは、テレサ・ラッセルの女優特性を多少なりともこころえている。冒頭、テレサ・ラッセルの美しい眼を超クロースアップの鏡像のなかで引き裂いているからだ。つぎつぎと夫を死に追いやる喪服の寡婦(ブラック・ウィドー)とは、たしかにこの女優を誤解しつづける男たちにとって、馴致しやすいイメージだろう。いっぽう『ボンデージ』(91年)の監督ケン・ラッセルは、テレサ・ラッセルの失われた全体像の不可能な修復をこころみるが、それはしょせん安全なコメディの枠内においてである。娼婦テレサ・ラッセルが、じぶんの生活と意見を観客にむかって開陳するとき、彼女がかかえる潜在的な恐怖はおしゃべりの洪水にむなしくおしながされてしまうだけである。
同じ女優を共有しながら、『KAFKA/迷宮の悪夢』(スティーヴン・ソーダーバーグ監督91年)と『マリリンとアインシュタイン』(ニコラス・ローグ監督91年)は、ともに『ジェラシー』の不完全なリメイクにすぎない。迷宮の悪夢のなかで失われるテレサ・ラッセルの全体像は、唯一『ジェラシー』の無限退行のなかだけで触知可能なものとなる。
オリヴィア・デ・ハヴィランドをほんとうにかわいい女優だとおもったのは、『風と共に去りぬ』(ヴィクター・フレミング他監督39年)ではなく、日本未公開の『夜明けよ、待て』(41年)を見てからである。『風と共に去りぬ』のメラニー役でも、まして貴族海賊エロール・フリンの相手役でもなく、あくまでもミッチェル・ライセン監督下の清楚可憐なオリヴィアである。
じっさい彼女がはじめてアカデミー賞主演女優賞候補にあがったのがミッチェル・ライセン作品(『夜明けよ、待て』41年)なら、はじめて受賞の栄によくしたのもまたライセンの映画(『遥かなる我が子』46年)でであった。
ミッチェル・ライセン、このわすれられた映画監督の再発見なくして、オリヴィア・デ・ハヴィランドの再評価もまたありえないのだが、そうはいっても、この男性監督が同時代の他の映画作家、たとえばビリー・ワイルダーなどよりも一頭ぬきんでていたかというと、かならずしもそうともいいきれない。歯切れの悪いことおびただしいのだが、要はあくまでもスタジオの方針なのだ。オリヴィアが契約していたワーナー・ブラザーズ社は、結局、彼女にお姫さま役以外のどんな配役も考えつくことができなかった。しかるに女優に絹の光沢と自律性をあたえることのできるというパラマウント社は、手練手管でオリヴィアを獲得した結果、世紀の傑作『夜明けよ、待て』をスポンテイニャスなフィルムにしあげることに成功する。スタジオの方針の枠内ではあれ、オリヴィアの熱情と孤独感はそこで最大限までひきだされたのだ。
じっさい一九三〇年代後半のオリヴィアは、ワーナー・ブラザーズのいうままに動く美しい一体の機械人形にすぎなかった。しかし、つづく四〇年代前半は一転してスタジオの呪縛から逃れるためのながく苦しい戦いとなる。なにしろ、それまで女優といわず、すべての映画関係者は専属契約によって長期間スタジオに縛りつけられる存在だったのだ。それゆえオリヴィア・デ・ハヴィランドという美しい響きの名をもつこの女優は、ハリウッド・スタジオ・システムへの最初の反逆者として記憶されねばならず、じっさい最高裁で勝訴した彼女はスタジオから実質的な自由をかちとった最初の女優となるのである。 そしてここからが興味深いのだが、スタジオの指示ではなく、じぶんのやりたい役柄を自由に演れるようになったとき、この才能と野心あふれる女優がえらんだものは、三〇年代のかわいいお姫さま役ではないことはいうまでもないが、四〇年代前半までの清楚可憐な役柄でもなかった。
四〇年代後半からのオリヴィアの経歴は、「狂気映画三部作」とでもいうべきものによって彩られることになるのだ。それまでに『レベッカ』(アルフレッド・ヒッチコック監督40年)や『ガス燈』(ジョージ・キューカー監督44年)などの女性ゴシック映画が流行っていたこともあって、オリヴィアがみずからえらんだ役柄は心をとざし、狂気においこまれる女性だった。わたしが「狂気映画三部作」とよんだ『暗い鏡』(ロバート・シオドマク監督46年)、『蛇の穴』(アナトール・リトヴァク監督47年)、そして『女相続人』(ウィリアム・ワイラー監督49年)の三本は、今日のジェンダー論的観点からすれば、いかにも問題含みとはいえ、たしかに同時代のいかなるハリウッド女優にもまねのできない心理的リアリズムを獲得している。
とはいえ従来のオリヴィアの清楚可憐なイメージの払拭が一筋縄でいくはずもなく、そのために映画史はひとつの戦略的なフィルムを産みおとさなければならなかった。それが鏡にうつるがごとき一卵性双生姉妹を登場させる「狂気映画三部作」第一作の『暗い鏡』である。清楚可憐なオリヴィアから狂気の炎をやどすオリヴィアへの歴史的転回は、じっさい一人二役という伝統的な方法でなされたのだ。一本のフィルムのなかで天使と悪魔の両方をひとりで演ずることでイメージ刷新に成功したオリヴィアは、つづく『蛇の穴』で本格的な狂気を映画史に導入することになる。
『蛇の穴』というこの恐ろしげなタイトルにもかかわらず、精神病棟に入れられながら、じぶんがいまどこにいるのかもわからないオリヴィア・デ・ハヴィランドの美しい不安気な顔のクロースアップと心の内をきかせるヴォイスオーヴァの十秒間だけで、わたしはもう彼女の孤独な世界にどっぷりとつかってしまう。
オリヴィアは、その美しさだけを利用しようとした巨大男性組織と徒手空拳で戦いながら、その勝利ののちは、積極的に自己更新をはかった類稀なるハリウッド女優だったのである。
7 ヴェロニカ・レイク ノワールな美女
ヴェロニカ・レイクはノワールな美女としてしられている。
うりざね顔というか、うねるような金髪と線の細さをきわだたせる厚い唇、そして遠い眼をした面差しは、夜空に輝く美しい三日月顔というべきだろうか、銀幕スターにふさわしいそのどこかしら人工的な美しさは、今日も彼女の映画の観客を魅了しつづける。ヴェロニカ・レイクの名は、とりわけ美男子アラン・ラッドと組んだ三本の映画において不朽である。『殺し屋稼業』(フランク・タトル監督42年)、『ガラスの鍵』(スチュアート・ハイスラー監督42年)、そして『ブルー・ダリア』(ジョージ・マーシャル監督46年)の三本は、じっさいフィルム・ノワール史上屈指の傑作である。
フィルム・ノワールとは、一九四〇年代にアメリカで成立した犯罪スリラーだが、物語の骨子は、ナチ政権誕生に失望したユダヤ系ドイツ人らが亡命地ハリウッドにもたらした世界観にもとづいている。フィルム・ノワールはその生成の時点から、世界に失望した主人公の転落と再生の物語となるべく運命づけられていたのだ。
さてヴェロニカ・レイクとアラン・ラッドのコンビ映画が成功した要因には、似通ったふたりのスタイリッシュな無表情がある(じっさい、このふたりは双子の兄妹のように似ている)。そして無表情とは失望の産物である。ひとが人間らしい喜怒哀楽の表情をうしなうのは、感情の絶対値を経験したときである。許されざるべき絶望をあじわった者は、人間としての表情をうしなう。それゆえヴェロニカとアランは、あきらかにアウシュヴィッツの時代の申し子なのである。
しかし、にもかかわらず、この美女美男の無表情には、焦燥感に焼かれたハンフリー・ボガートの無表情とはちがって、ある種の優雅さがある。ヴェロニカ・レイクとアラン・ラッドは、まるでファッション・ショーのモデルたちのように優雅な無表情をたたえているのだ。それが今日、このノワールな四〇年代カップルの復権をはからねばならない理由である。世界にたいする深い失望の念にもかかわらず優雅さをうしなわないこのふたりは、徹底した個人主義者である。世界がじぶんの意にかなおうとかなうまいと、そしてたとえこの世が信頼に値しない世界だとしても、それでも人間は卑屈にならずに、立派に生をまっとうしうるのだということを、ヴェロニカ・レイクとアラン・ラッドのカップルは示唆している。
さきごろ、ヴェロニカ・レイク主演の二本の旧作喜劇(『サリヴァンの旅』プレストン・スタージェス監督41年と『奥様は魔女』ルネ・クレール監督42年)が再公開されたが、その圧倒的な愛らしさにもかかわらず、やはりヴェロニカ・レイクの本領はコメディよりもフィルム・ノワールにある。「ピーカブーバン」とよばれる長いブロンドの髪のむこうに妖しく光る目。ヴェロニカ・レイクは、その人工美、そのはかなさ、その銀幕的現前において典型的なハリウッド女優であった。
一九四〇年代の銀幕をかざるスターとして、彼女は一貫してヴェロニカ・レイクでありつづけた。じっさい彼女がアラン・ラッドと共演した三本のフィルム・ノワールは、それぞれ個性的な監督によって演出されたにもかかわらず、たがいにみわけけがつかないほどどれもよく似ている。ヴェロニカ・レイクは、キャサリン・ヘプバーンのような天才的女優でもなければ、オリヴィア・デ・ハヴィランドのようにスタジオにたいして自己のイメージの刷新を要求するラディカルな女優でもなかった。ヴェロニカ・レイクはただその視覚的な美しさにおいて、つねにじぶん自身でありつづけたのだ。
その俳優生命は短かったが、つかのまの栄華に大富豪ハワード・ヒューズと流した浮き名もまた女優ヴェロニカ・レイクにふさわしいものであった。その美貌は、飛行家の実存的な恐怖をえがく『地獄の天使』(30年)で有名なこの映画作家兼冒険飛行家の心を虜にしたように、おおくの観客の魂をつかんで放さなかったのだ。
女優について語ることは映画について語ることである。彼女の情熱は映画の情熱であり、彼女の歓びは映画の歓びである。けれども女優と映画は、その外見ほどにはかならずしも表裏一体ではない。
女優はダンサーとはちがう。昔ケルトの詩人が歌ったように、ダンスとダンサーは分かちがたく結びついている。ダンサーの踊るダンスから彼女の身体だけをとりだすことはできない。ダンサーがいなくなればダンスもなくなるし、ダンスが生成しないところにはダンサーもまた生まれない。
しかるに女優と映画の関係は、ちょうどふるくなったフィルムの皮膜のように不安定である。女優は水すましのように、透明な膜面上にしか棲めない生き物のはずなのに、それでもときとして彼女は映画から剥離してしまうことがある。ハリウッド古典映画では絶対にそんなことは起こらないのだが、一九六〇年代以降のヨーロッパ映画ではそれもめずらしいことではないだろう。
フィルムから剥離してしまう女優、ジュリエット・ビノシュもまたそうした不安定な女のひとりである。わたしはジュリエット・ビノシュに抗いがたく惹かれるが、それは彼女が、その恋人であり監督でもあるレオス・カラックスの映画に出演しているときにかぎられる。ほかの監督作品ではだめなのだ。たとえば『ダメージ』(ルイ・マル監督92年)や『ランデヴー』(アンドレ・テシネ監督85年)のような映画では、ビノシュはただ自堕落な男の愛人という偽りの求心性以外、監督からなにも求められていない。その求心性への安住ぶりが、彼女の映画的存在に致命的なダメージをあたえる。
ビノシュとカラックスの幸福な関係は、女優ジーナ・ローランズと監督ジョン・カサヴェテスについてもいえる。かれらのコンビネーションは絶対的であり、女優と監督の私生活での緊密なつながりが映画のうえにも奇跡的に反映しているのだ。じっさいレオス・カラックスの演出をえたビノシュは映画史の金字塔である。彼女は『ポンヌフの恋人』(91年)で、さながらドキュメンタリー映画の無名の被写体のように映画の主題そのものと化す。ジュリエット・ビノシュはそこで映画の全体からひとり剥脱し、世界からひとり孤絶する。まるでセーヌ両岸の喧騒から切りはなされ、セーヌに浮かぶ孤島と化してしまったポンヌフのように、ビノシュは帰属すべき世界をうしない、ひとり咆哮する。
ハリウッド映画スターの身なら、そんなことはけっして起こらないのだが、カラックス映画のビノシュには、世界との隔絶という不幸がふりかかる。彼女の身体からは、スターの絶対的与件である煌めきがうばわれるのだ。アイライトを浴びて光りかがやくはずの瞳には眼帯をかけられ、きらびやかなドレスのかわりに薄よごれたホームレスの衣装をきせられ、優雅な身のこなしも明透なエロキューションもビノシュにはゆるされない。煌めきを奪われたスターは、映画的星雲の中心をしめるだけの求心力をうしない、フィルムの表面からゆっくりと剥落する。そしてこの剥落の長いプロセスの内にレオス・カラックスの超絶技巧がある。
カラックス映画においては、もはや映画の中心はいかなる意味でも女優の仕草にはない。映画は統一性を欠いた現実世界そのものの写し絵となり、かつて虚構世界の内的統合の要だったスターは姿を消す。にもかかわらずカラックス映画が、剥がれかかったそのビノシュの存在のうえに成立していることは興味深い。それを痛切に物語る『ポンヌフの恋人』のエンディングは、それだけで映画史的大事件なのだが、それを語ることはまた別の機会にゆずらねばならない。
ロザンナ・アークェットといえば、蛙にかえられた王子と結婚しかねないほどの蛙顔だが、彼女が恋をすると、その大きな口から自然と笑みがこぼれ、大きな鼻からは溜息がもれる。しあわせそうに小さく笑うとき、鼻孔から空気がもれる音がして、それが海豚の鳴き声のように、彼女のかわいいシーニュとなる。そうロザンナ・アークェットは鼻孔で演技ができる数すくない女優なのである。
みしらぬ男のまえでヘンリー・ミラーを暗唱してみせるときの彼女はいかにも知的なニンフォメイニアといった感じで(『アフター・アワーズ』マーティン・スコシージ監督86年)、わたしはその魅力に手もなくやられてしまう。その恥ずかしげな笑顔はあらいがたく、プリンストン大かニューヨーク大の田舎出の大学院生をおもわせる。じっさい、わたしたちがロザンナ・アークェットに親近感をもつとすれば、それは彼女がフェミニスト陣営から排除されるアメリカ女を代表しているからだろう。知的ではありながら、理論武装しない女。状況がはかばかしくなくとも、自己弁護する必要を感じない女。そのあやうい無垢。ロザンナ・アークェットが代表するのは、今日のアメリカのそういう空域である。
ロザンナ・アークェットが「かわいい女」であるとすれば、それは彼女が他者への配慮に溢れているからである。彼女は他者の一言一句に敏感に反応し、海豚のように他者を傷つけることがない。それは主体性の欠如のようにみえるかもしれないが、信頼するにたる人間関係をきずくうえで、他者へのおもいやりは自己にたいする誠実となる。じぶんの帰属する閉ざされた共同体のために他者を攻撃することなど、およそ必要のない女なのである。
とはいえ、ロザンナ・アークェットが田舎出の大学院生をおもわせるのは、これから先どんなふうにじぶんの欲望をかたちづくっていくのか、やはりじぶんでも判然としないからであろう。彼女は理想の男とであったら、彼への恋心でいっぱいになり、それ以外のなにもみえない。これが彼女がフェミニストたちから排撃される理由である。
しかし『グレート・ブルー(グラン・ブルー)』(リュック・ベッソン監督88年)をもういちどみていただきたい。さざ波たつ海の色の美しさに息をのむこの海洋映画は夏になればかならずみたくなるフィルムだが、そこでのロザンナ・アークェットの鼻孔は映画史の奇跡というしかない。彼女が小さく笑うとき、鼻と口から同時に息がぬける。その鼻孔の震音が彼女の幸福感をあまさず観客につたえる。アルベール・カミュのように、彼女は人生における幸せの意義をしっている。そして映画史は、一九四〇年代にジョーン・フォンテインの奇跡のクロースアップをもって以来、このロザンナ・アークェットの鼻孔の震音にいたるまで、つねに女優の顔にささえられてきたのだ。
彼女の大きすぎる目と鼻と口は、そのちいさな顔のなかで、感情の絶対値を経験する。その笑い顔と泣き顔は、ジェイムズ・ディーン級の超絶技巧だ(しかもニコラス・レイ演出下でのジェイムズ・ディーン)。『グレート・ブルー』にならぶロザンナ・アークェットの代表作には、『マドンナのスーザンを探して』(スーザン・シーデルマン監督86年)がある。
近作には屍体濫造映画『パルプ・フィクション』(クェンティン・タランティーノ監督93年)へのカメオ出演があるが、この監督には銃声とおしゃべりにたいする耳はあっても、ロザンヌ・アークェットの優雅な鼻孔の震音をききとるだけの耳はなかったようだ。彼女は鼻にピアスをとおされ、残念ながらわたしたちは、あのすばらしい鼻孔の溜息を耳にする機会をあたえられない。
「ティ・アーモ(愛してます)」しかイタリア語を話せないハリウッドの大女優がイタリアの大監督と不倫の恋をする。世界の耳目をおどろかせた世紀の恋愛。そうして産まれたのがイザベラ・ロッセリーニ。母イングリッド・バーグマンの美貌と父ロベルト・ロッセリーニの天才をうけついだイザベラ。なるべくしてなった女優である。
しかし彼女が花ひらいたのはリンチ映画においてである。じっさい監督のデイヴィッド・リンチはイザベラの出自をなぞるかのような家族映画を撮る。リンチ、このファミリー・ロマンスの大家は飽かず家族と夫婦の謎を追求する。
最初期の『グランドマザー』(70年)をみれば、この才能ある映画作家が幼少期に癒しがたい心の傷をおったことはだれの目にもあきらかである。家族と夫婦、この世界一親密なもののあいだにみえない秘密があるという逆説。それがフロイトとリンチを、そしてイザベラを魅了する。夫婦の謎と秘密はまたイザベラの父ロベルトが母イングリッドとともに撮った一連の映画の主題でもなかったか。 映画『ブルー・ベルベット』(86年)は女優イザベラ・ロッセリーニの代表作である。と同時にいまのところ作家リンチの最高傑作でもある。そこに『イレイザーヘッド』(77年)からのポストモダーンな発展形と『ツイン・ピークス』(90年)の優雅な先どりをだれもが容易にみてとれる。『ブルー・ベルベット』は五〇年代B級映画の再解釈の所産というよりも、より正確にはアイダ・ルピノ映画の正統な嫡子というべきだが、それは女優イザベラが生まれそだった年でもあった。
じっさいこの悪夢ようなフィルムは「ブルー・ベルベット」を素肌にまとうイザベラによって織りあげられる。彼女は全身全霊を賭けて、誘拐された夫と息子をとりもどそうとするのだが、そのあげくに惚けた人形と化す。それは胸をつかれる出来事である。彼女の顔はワイドスクリーンの横長の画面に超クロースアップでおさまり、キャメラによっていわば顎と鼻梁と片目を切りとられ、みずからが無意識に望むところの物質人形と化す。空に浮かぶ巨大な唇(マン・レイ)のようにその身体から切りはなされイザベラの唇は、錯乱寸前の彼女の精神状態をまざまざと象徴する。
じっさい死体すらもが屹立し、あまつさえ不意に痙攣しては生きている者をおどろかせるこの映画において、力なく横たわり、よつんばいになり、そして全裸で青年に抱きつかざるをえない人妻イザベラのよるべなさは尋常ではない。
彼女が演ずるのは、困惑し、しかも困惑に溺れる女である。くされかかった葡萄のように現状におしつぶされる女。それはまるで順応主義的な日本人男性のように事態をただただ悪化させるばかりで、ほどなくすべてが手おくれになる。にもかかわらず緩慢な日常のなかで夢みられたこの一幕の悪夢は、それが順応主義のアイロニー劇であるかぎりにおいて、事態は嘘のように収拾し、またもとのかわらぬ平和な日常に復することができる。
困惑しながらも困惑に惑溺する女。そのサドマゾヒズムの眩暈が観客をうちのめす。つてどんな女優がそんなハリウッド的な身振りでそんな非ハリウッド的主題を演じられただろうか。リリアン・ギッシュは困惑に惑溺するような女ではなかったし、ジョーン・クロフォードは男に回収されても復讐をわすれはしまい。ベティ・デイヴィスなら男を毒殺するにきまっている。
しかしこのポストモダーンな現状のなかで、ひとりイザベラ・ロッセリーニだけがリンチの手をかりて、かつてどんなハリウッド映画もえがきえなかった女の肖像を提出する。そのバロックな映像記述はみる者を圧倒し、正が邪であり聖汚一体と化す悪夢のような日常を可能にする。