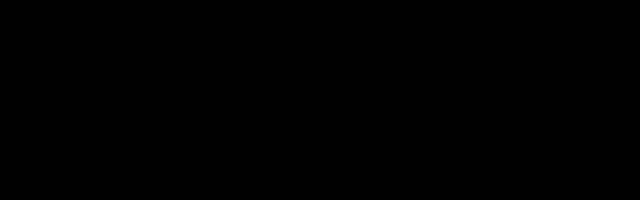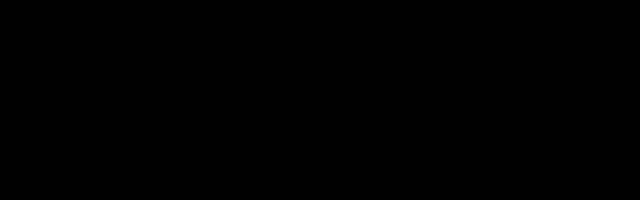
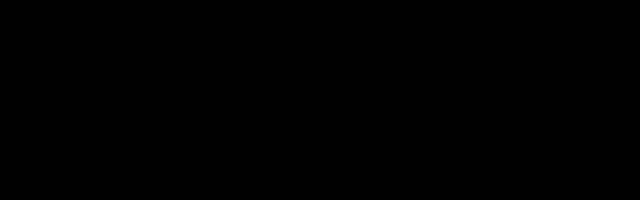
北野 では僕自身のポジションから考え直させていただきますと、そもそも精神分析が嫌なのは、僕がドゥルーズというよりもドゥルーズ=ガタリが好きなタイプの人間であるからです――ある種の分析哲学の方向というものも大好きなんですが。個人的な趣向はともあれ、精神分析で映画を語るというか、精神分析がグランド・セオリーなのではないかという気がなんとなくしていて、それに目を開かせてくれたのがキットラーだったと思うんですよ。映画が出てくるが故に精神分析が出てくるとまでは言いませんけれども、映画と精神分析の出自というのがかなり時代的に接近していて、エピステーメ・レベルでは相互関係がなかったわけではない。ヒステリーの身体とスクリーンに機械的に再現されてしまった身体、あるいは蓄音機で機械的に再現されてしまった声などに、遭遇したときの途方もない驚きですよね、それを回収するときに身体の向こう側にある何かというものを想定せざるを得なかったというふうな形で、キットラーが精神分析というものを設定する。これは石光泰夫さんと雑談させていただいたときもそうでしたけれども、精神分析による映画ではなくて精神分析とともにある映画という形で括っていかなくては駄目なんじゃないかという気はしているわけです。
それでいくと、精神分析が言っていた無意識概念にしろ精神分析の構え全体が、歴史的なパースペクティブのなかで相対化されていかざるをえない。また、メディア史的な観点を重ね合わせると、映画は20世紀のメディアであったとは思うんですけれども、たとえば19世紀的なメディアであった(印刷された)書字言語あるいは20世紀末から現れてきたヴィデオあるいはコンピュータみたいなものを含めた上で映画を考えていくときに、精神分析をグランド・セオリーとしてやっていくのはいかがなものかなとは思わざるをえない。精神分析論じたいももちろんいろんな修正はあったとは思うんですが、基本的に無意識概念が空間化された比喩形象のもとで実体化されていて、その中であまりにもあやふやな因果性の説明のなかで物事が論じられていくというスタンスは総じて変らない。だからこそですが、これだけ色々な領野で反発が出てきていますし、新しい心のモデルも出てきているので、精神分析的枠組みそのものが歴史的なものであったと考えて、その上で映画とともにというふうに問題設定をおこなった方がより適切であって、精神分析による映画論というのはちょっとどうなんだろうかなというふうには思っていますね。その相対化のために認知派なり他のもの、あるいは19世紀的な心の存在論みたいなものを参照していくのは大切なんじゃないかとは思っています。
加藤 全く同感なんだけれど、では、たとえばテクスト分析というのは何だったのですか。つまり先ほど斉藤さんが言われたような、どうしても間尺に合わないというか、言語化・合理化できない理屈に合わない残余が絶えずあるという強迫観念、と呼んじゃうとまた精神分析学に戻ってしまうのかもしれないけど、人間がテクストと向き合ったときになんかそういうものが残っている、そうしたものこそ探求するに値するものであるということを、バルトのテクスト分析は示しています。
斉藤 それが昔は美だったわけですよね、それがビューティであるという。ある意味では美学的なもので説明してきたような気がするんですけれども。
北野 たとえばクレイリーの仕事や、(その当初の論文そのものが読まれた)89年か90年に『ヴィジョン・アンド・ヴィジュアリティ』というコンファレンス(これはこのシンポジウムの後『視覚論』という題で平凡社より翻訳された――北野)があったわけですが、あそこでやられていたいくつかの試みというのは、とにかく精神分析をある種歴史的に相対化しつつ、しかしいわゆるヴィジョン・見えるものとヴィジュアリティ・視覚的なものとの対立、さらにはそれらと言語的なものとの関係みたいなものをもう一度大きく捉え直していこうという発想の中で出てきた話だとは思うんですけれども。おそらくは見えているけれども語りえないというものに関して、必ずしも精神分析的な無意識概念あるいは他の道具立てを使って接近し続ける必要性は無いのではないだろうかなというふうに考えたりするんですが。
加藤 それはその通りだと思うけど。
長谷 ちょっと微妙なところなのですけれども、実際に精神分析学的に、というか抑圧と無意識との葛藤とかそういう中で見ている観客がいると僕は思うんです。つまり単なる理論ではなくて、本当にある時代の観客は精神分析学的主体だという事実があるという気がするわけです。もし未来に向けて精神分析的な無意識というのはもう駄目だという考え方に一定の面白さがあるとすると、観客なり映画なりが、そういう精神分析とともにあった
映画から変化して何か全く別のものになってしまう。たとえばヴィデオというのは精神分析学とは違う論理で作られ、見られているとかね、そういうことを言っていただければ、分かるんです。つまり観客の見方自体が精神分析学的とは違う見方になりつつあるなにかそういう新しい動きがあるといったほうが、僕には・・・。
斉藤 精神分析が出てきたときに、先ほどおっしゃったように映画とパラレルであったわけですね。つまり19世紀的なものがその関係のなかに普遍化された形ででてきたというのは確かにあると思うんですけれども、あの時点で近代人、19世紀の、それが日本に当てはまるかどうかは別問題なんですけれども、少なくともヴィクトリア朝の、それこそヒステリーが生まれる時代のひとつの歴史的言説だと取られたことも確かだと思うんですね。結局精神分析理論自体が独り歩きしてしまって、方法論になってしまったときに、またラカンが入ってきたときに変わってくると思うんですが、たとえば少なくともフェミニズムなんかにおいてはフロイトの精神分析理論というのは19世紀から、つまり近代の父権社会の言語であると、そういうモデルみたいな形でとらわれていたことは確かなような気がするんです。
長谷さんがおっしゃったことと関連しているんですけれども、アナログからデジタルに変わったときに、アナログの持っていた、バザンの言葉を使ってしまうのはどうかと思いますけれども、いわゆる本当の写真的な痕跡ですよね、映像的な痕跡。アナログでは実際そこにあったものを写すことによってしか再現できないものですから必ず不在があるという理論になるわけですよね、それが正しいかどうかは別として。そこがデジタルになってリファレントとの関係が全くないままに、ゼロから全て映像を数字・機械的なもので再現できるとなったときに、あるいはわたしたちの高度消費社会の80年代において、いわゆる抑圧がないという別の抑圧みたいなものが出てきたときに、その精神分析という理論は1世紀前の人間モデルになったのですね。そういう形だったら、そこにおいて全く新しい理論が必要だというのがあるのかなと。それだったらわたしも分かるような気がするんです。ただグランド・セオリーという、それがある時点で実際にそういう形で使われてしまったことは確かなのですけれども、そのグランド・セオリーをただ破壊するためというのだと、ちょっと違和感があるなという感じがしてしまうんですね。わたしにとっての精神分析の興味というのも、先ほど北野さんがおっしゃったように、パラレルであったと思うのです。それは精神分析による映画ではなくて、精神分析とともにある映画という。その意識というのは、ボードリーの『装置論』とかあの辺ではまた別だと思うんですが、少なくともある種のサブジェクトを考えるときに、それはブルジョアの、19世紀からのいゆるモダニティの中にある主体であると。
北野 何が19世紀的にブルジョアの主体なんですか。
斉藤 だから、映画を見た、映画を見る主体。
北野 僕は、19世紀的なブルジョアの主体と映画の主体とは全然違うと思いますけど。映画の主体というのは大衆じゃないですか。
加藤 いや、映画が観客を主体化するプロセスは、観客に超越的一元論的視点をあたえるという点でブルジョアの一元的上昇志向と似ているところがあるのです。そこに大衆のスノビズムがあるわけだし、映画のモビリティの問題機制もあるのです。
中村 その辺をもう少し限定して考える余地があると思うんですね。精神分析そのものと映画との関係、先ほど言われた精神分析とともにある映画という、キットラーなどに言及されておっしゃっているのはよく分かるんですけれども、映画理論における精神分析の使われ方、グランド・セオリーという形でボードウェルが批判するような使い方に関して言えば、先ほどから少し思っていたんですけれども、おそらく精神分析的な理論と認知派の闘争の中で何が賭け金になっているかというとやはり古典的ハリウッド映画と呼ばれるような映画でありそれに対応する観客のモデルだと思うんですよね。ですから、長谷さんが最初におっしゃった古典的ハリウッド映画を見ているときの、身体的な動きとして外に現れないような動きとして何か反応してしまうものがあると言われたことと関連するんですけれども、その時の動きとして外に現れない動きを指し示す、それについて考えるための分析装置として精神分析というものが非常に有効であるというふうに多くの人が思ったというのはあると思うんです。ですから古典的ハリウッド映画とその観客といったものを精神分析派はそれを批判しようとしたわけですよね。たとえば、それはブルジョア的な主体であり、あるいは父権的な主体を構成するものであるという形で批判しようとした。そのための枠組みとして精神分析が有効であると考えた。まさに古典的ハリウッド映画そのものが観客というものを精神分析的な形で構成しようとしたのであり、歴史的なレファレントとして考えるときに、そういう形で分析することがかなり有効であろうと考えた。で、一方で先ほどの認知派が60年代の近代化論に基づいていて云々という話とおそらく緩やかな形で関わってくると思うんですけれども、ボードウェルの理論というのはやはり古典的ハリウッド映画の観客、古典的ハリウッド映画が構成するような、あるいはそれと対応するような観客を基本的に肯定しようとしているとわたしは思うんですよね。で、娯楽として映画を消費する、その物語世界を様々なキューに基づいて読み解いていくという認知的な活動の主体とは何かといえば、それはもう一方の別の形で構成された古典的ハリウッド映画の観客であって、それは肯定されるべきものとして立てられていると思う。ですからその辺りで、精神分析そのものの歴史となるとものすごく大きな問題になってしまうんで発言を控えていたのですけれども、そういう形で限定すると少し見えて来るんじゃないかなと考えています。
北野 では僕の方からなんですけれども。だから認知派は観客を考える場合、基本的に好奇心に突き動かされながら、映画が視覚的に物語を語っていく手つきの巧みさにおいて映画を見ていると考える。古典的ハリウッド映画もそのようなかたちで享受されていくわけですよね、非常にアクティヴな形で。精神分析が、先ほど長谷さんが冒頭でおっしゃられた形の、イモビリティの中で、しかし何ほどかの快楽というものがそこにあるんだというふうなことを言うときに、それは精神分析的に説明されるべきものなのですか。それともそうではなくて?
長谷 わたし自身は精神分析的に説明されるべきものだということを言ったのではありません。ただ歴史的に見た場合に、それを説明するときに他の手だてよりも精神分析が有効であろうと多くの研究者が考えた事実は確かにあるというふうに理解しているんですけれども。
北野 クリスチャン・メッツが精神分析を積極的に取り入れるとき、あるいは構造主義を取り入れるときですけれども、全ての映画は物語映画だという断定を強く打ち出すんですね。
斉藤 フィクション。物語というよりもフィクション映画。
北野 ええ、物語映画であり、フィクション、フィーチャ・フィルムだということを言うわけで、その時に今おっしゃられたような何か分からないモビリティというのはどいうふうに?。
長谷 メッツにはあまり感じないですよ、僕は。
中村 メッツのことはあまり想定してないですよね。
北野 じゃあ精神分析というのでは何を想定しているんですか。
中村 ですから、先ほど言った何かよく分からないモビリティというものは、映画観客という主体を構成するときに作動しているというか、その辺りを説明しようとしたんじゃないかなというふうに。
北野 具体的にはたとえばどういう人達がいるんですか。
中村 たとえばですね、これは斉藤さんを前にしてこの例を挙げるのは恐ろしいんですけれども(笑)、ローラ・マルヴィが女性の表象をどう論じているかというときに、女性の表象というのは男性観客の視線にとっての、いわば躓きの石になっていて、去勢不安の契機になっていると言ってますよね。しかしその部分を読んでいると、単にそういう理論に回収されるような形で取り上げているだけではなくて、やはり女性表象はスペクタクルとしての資格を持つものだという話をしていると思うんです。そうすると、これは少し強引かもしれないんですが、先ほど少しガニングのアトラクションズの話をしましたけれども、古典的映画の中に表れているようなアトラクション的なものとして女性の身体表象というものがあって、それがなぜ古典的ハリウッド映画の男性観客にとってつまづきの石になるかというと、古典的ハリウッド映画の物語というものがまさにそのエディプス的な物語である限りにおいて、そういった躓きの石になる。ですからそこに、物語に回収されない、いわば過剰なものとしてそういうアトラクション的なものというか、スペクタクルという言葉を使うとまた別のインプリケーション(シチュアシオニスム的な)が入ってしまうので、少し危険なんですけれども、今はとりあえずアトラクション的なものという言い方でとどめておきますけれども、そういうものとして躓きの石になる、あるいは去勢不安の契機になるようなある種の裂け目になるという形で似てると思うんですよね。ですから、それが先ほど長谷さんが言われた「イモビリティ的なモビリティ」ですか、それとどこまで一致するかは一概には言えないんですけれども、概ねそういった過剰なものとして論じられているというふうに思うんです。
北野 確かにおっしゃるように、ローラ・マルヴィにはある種の視覚的なものの快楽、まあメッツにも僕はなきにしもあらずと思っていますけれども、語られているものと語りえられてはいないけれどもおそらく我々には見えていてわれわれを非常に惹き付けているものですよね、それを映画研究者としてはどうにかこうにか位置づけていきたいところがあるわけですけれども、それを精神分析的な枠組みで語ったというのはですね、かろうじてわずかな部分のメッツそしてローラ・マルヴィしかない。で、多くの場合、この視覚的なものもどちらかというと、もちろん精神分析的に言うと抑圧されるが故に愛おしいというようなことにもなってしまうんでしょうけれども、他方、蓮實的に言うともう「この黒髪が絶対的に肯定されるべきなんだ」とかいうふうな話になったりして、それは精神分析的な枠組みとは全然違う形で書かれたりするわけだとも僕は思います。やっぱり『スクリーン』を中心とする精神分析的な映画理論の中では、とりあえず語りえないけれどもおそらくそこにあって我々の目の中に入って非常に快楽を引き起こしているものをどうにか我々が語ろうとするときに、『カイエ・デュ・シネマ』から『スクリーン』の70年代の枠組みでは、今のようなわずかな例外を除いて大枠のところでは非常に乏しいものであったといわざるをえない、少なくとも英米の脈絡での成果としては。そこで蓮實さんが「黒髪だ」というふうな形で断定したときには、圧倒的な肯定だとは思います。どこかで、80年代にあれを言うのはあまりにもイデオロギー的に問題があるんじゃないのというのはあるんですが、まあ思惑が御自身にはあったのはあったのかもしれないとは思いますけれども。それは、やはり異なる美学が屹立している。かなりおおざっぱな物言いを許していただけるのなら、僕はエピステーメー的にいうと70年代に何かあったんじゃないかなとは思っているんですが、片方で、英米では、それ以降映画論はどんどん修正を加えていきながら精神分析を取り入れていく、他方で、日本では、圧倒的に何かよく分からない蓮實的断定をするとか、さらに、英米では少し遅れて、認知派が仕事をはじめるといった方向へ行かざるを得ないような動きが、出てきた、そういうことなんじゃないかと思っています。
加藤 そう断定、断定と言うけれど、蓮實の本質的部分というのはテマティスムですよね。まさに彼は彼なりに精神分析学を否定して、深層じゃなくて表層なんだ、スクリーンなんだ、幕があるだけなんだと。で、その幕を滑っていくについては、やっぱり滑り方のコツみたいなものがあって、それが彼の場合、こぶを次々に滑りこなすプロ・スキーヤーみたいに見事だったわけで、白いこぶがここにもあそこにもいっぱいあるじゃないか、みんなそこを滑ると気持ちいいのに見落としているし、滑り落としているじゃないかというのが流行った時期で、それが最良のかたちで表れたのがバルトのテクスト分析であったりリシャールのテマティスムであったり、みんなそれなりに精神分析学的深層を否定しようとした試みであったわけです。
中村 話題としては続くんですが、ちょっと別の視点を出してみます。精神分析と映画の関係を考えるときに重要なポイントとしては、イマジネールの問題というのが欠かせないものですよね。もちろんイマジネールといった場合クリスチャン・メッツの理論というのがまず思い浮かぶんですけれども、メッツの理論に関しては北野さんが書かれたものの最後のところで補論という形で書かれていたんですけれども、実はそこを一番書きたかったんじゃないかなということも含めてわたしは大変面白く読ませていただいたんです。メッツ自身を論じるには、特に彼のいわゆる映画的制度の問題を論じなければならないんですけれども、それはひとまずわきに置きます。まずイマジネールを一般的に考えてみたときに、スクリーン上に映し出されたイメージに我々が対するときに、イメージそのものではない別の何かをイメージが表象している、表象代行、リプレゼントしているという形で見ることになるわけです。そうすると、スクリーン上のイメージについて何かを語るという場合に、実はそのイメージについて語るのではなくて、それが表象あるいは代行している別の何かについて語るという構えになってしまう。で、その何かというそのものについて語るときに、それがたとえば階級であったり性であったり、人種であったり民族であったりするといった形で、しばしばきわめて平板なものになってしまったりもするんですが、ともかくそのためには映し出されているイメージとそれが表象代行しているそのものとの関係について理論的に考えるときに、イマジネールという概念がおそらく必要になってくる。「不在」ないし「欠如」というものを理論的に処理する必要が出てくるからです。で、精神分析というのはそこら辺りを論じるものとして重宝がられたという歴史的な状況というのがひとつにはあると思います。おそらくそれとドゥルーズ的なものとの根本的な対立というのもまさにそこに関わってきて、スクリーン上にあるイメージというのは、スクリーン上にある広い意味での記号として別の何かを指示するものではなくて、端的にそこにあるんだという別の在り方をしているのであって、そのものがあるのと究極的には同じことなんだというベルクソン=ドゥルーズ的な見方になりますよね。あるいはそこまで言わなくても、蓮實的な先ほど加藤さんがおっしゃったテマティスムの場合も、別の何かを意味しているのではなくてまさにそこに反復されているものを語ればいいんだという構えになっていると思うんですね。ですから、その辺のイマジネールというものを精神分析学的な構えで語ろうと言っているのではなくて、精神分析的な語り方というものがなぜ出てくるかといった場合に、イマジネールの存在論というか、あるいはむしろ認識論というのか、その辺について我々がどう考えるかが非常に重要だと思うんです。わたしは、はっきり言えば、ドゥルーズ的立場に可能性を見出すわけですけれども、むしろそうした観点から、精神分析にしても、それを我々が採用するかどうかという以前に、それはひとつの語り方であると、そしてその語り方というのがなぜ要請されるかということを考える必要があるのではないかというふうに考えています。
斉藤 フェミニズムとかって、なぜ精神分析が出てきたかというと、それはひとつは抑圧の理論だったということが大きかったと思うんですね。そことフーコーの二つが、フーコーは前からあったとはいえ、方法論的に実際取り入れられるようになったのは少し後のことになるんですけれども、やっぱりその時は女性というのが声なき存在と語られていたわけですけれども、なんらかの形で女性というのが、先ほど中村さんがおっしゃったんですけれども、古典的ハリウッド映画の制度的な抑圧構造に組まれているということをある程度なぜそういう形が起こるかということを説明するときに、ひとつ有効な手だてであると。
実際にはもう本当に90年代の頭からアメリカにおいては精神分析理論というのは、ほとんど死滅してしまっていると思うんですね。今また別の形で少しずつ、やっぱりもう一回見直してみようというのが出てきていますけれども、それに取って代わるものというのは、初期映画分析であり、歴史分析であり、言説分析であり、カルチュラル・スタディーズ、そういうものだったような気はするんです。ボードウェルの古典ハリウッド映画の分析というのは非常に面白いと思うんですが、なんで面白いかというと、ある種実際に『スクリーン』派がやったような形で、イデオロギー的に殺したと。そういう意味では、それを掘り下げて肯定的にしているんですけれども、なんか最終的には彼は、小津であり、作家主義のそういうポエティックスに行くのではないかと。古典的ハリウッド映画は彼の頭の中には、これはシステムであると。大衆が喜んだひとつの非常に大衆的なシステムであり、美学というかポエティックスというかは別ですけれども、彼にとっては古典的ハリウッド映画とアート映画の対立が存在しているような気がして。そうすると彼は、アート・フィルムというんでしょうか、それはたとえばブレッソンでありドライヤーであり、そこの流れというものがあるような気がして、今のアメリカの映画学の中において、カルチュラル・スタディーズ的なもの、あと歴史研究的なものに比べるとあまり広がりが、ある当時の精神分析に取って代わるような一種の流れにならなかったのは、そこの部分なのかなという、それはわたしの非常に個人的な感じなんですけれども。
北野 中村さんがわたしにお出しになったイマジネールの話は、それは、僕がドゥルージアンにお聞きしたいところでもあるんでが、極めて強い関心がひとつあります。つまり認知科学的な発想、僕は精神分析的な発想もある程度そうだとは思うんですけれども、まあある種の言語中心主義的に記述するときに比較的に起きてくることなのかもしれないことに関係があります。とにかく映画体験における時間性というものがほとんど関係なくなって来るんですよ、認知科学的にやると。それがイマジネールの問題とどこでどう交差するのか分からないですけれども、それがひとつで何かお考えがあれば是非お伺いしたいということです。あとイマジネールに関しては、中村さんの論文にも出ていますし、多くの方が言っていますけれども、中村さんは非常に整理されつつ上手い具合に言っていらっしゃると思うんですが、写真においては「これはかつてあった」になるわけですよね、たぶんそれ以前は「これはここにある」しかなかったある種の言い回しがですね、写真の出現によってですね、「これはかつてあった」というふうな時間と空間に対する特異なセンテンス・パターンが可能になったところがあるわけです。これが映画になったときに、先ほどのイメージがなんらかの何かを実は代理代行しているというところで、「これはここにある」というふうになってしまうんだということをちらっと書かれていたと思うんですけれども、その辺で何かあればそれもお伺いしたいです。時間とイマジネール、あるいはイマジネールなものが2個接近するときの言説構造との関係とかで何かお考えになっていることが。
中村 今言われた写真と映画に関しては、これはあまりにも単純なので、こういうふうに口に出してしまうとばかばかしくさえ感じるような基本的な認識をわたしは持っていまして、スティル写真の場合は「それはかつてあった」という形で我々は概ね見ると思うんですね、まあ細かいことを言えば別のことも言わないといけなかったりもするんですが、それはちょっとさておいて。ところが映画になった場合に、映画は動いているわけですよね、ムーヴィング・ピクチュアになったときには、その動いているのは何かというとプロジェクターの作動であり、それを我々が脳の性能によって仮現運動という形で、本来はそこに静止画像の隙間があるわけですけれども、規則的に撮影された瞬間写真のフィルムの走行を、実際にはフィルムが垂直に流れているというか断続的に移動しているわけですけれども、ある固定されたフレームの中での様々な形象の動きとして見るわけですよね。そういう形で生み出されつつある現場に立ち会っているという点で、それは静止画像であるいわゆる写真を見たときの時間性とは根本的に違うものであるという、それが基本的な認識なんですよね。
斉藤 たとえば『ラ・ジュテ』なんかを見ると、あれはスティルでできているけれども、キャメラが動くじゃないですか。だから映像が動かなくてもキャメラが動くことによって、どうしても時間的なものが出てきてしまう。あれが非常に面白いんですよね。
中村 あとストップモーションにしてもそうですが、映画の中で、『ラ・ジュテ』など顕著ですが、写真が映し出されているのは、そこに写真が貼られているわけではないんですよね。フィルムの走行が実際にはあるんだけれども、それを我々は静止画像としてみているということだから、スクリーン上では止まっていても、これはある意味で動いているという。
斉藤 編集もあるじゃないですか。
中村 そうですね、編集ももちろんありますし。
北野 「これはかつてあった」というものが「これはここにある」になっていくときに、つまり初期メッツが複数のフォトグラフィが並ぶときにディエジェシスが立ち上がって来るんだという言い方をするところがありますけれども、それはキットラー的にベンヤミンを読むと――なんていうめちゃくちゃのことを言いますが――むき出しというか途方もない身体なりイメージが表れたときにそれに言説的に対応せざるをえないような状況に観客が追い込まれたとしてですね、それに対してたとえばキャプションを付けるとか色々な方法があるわけですね。キャメラが制度的にそこに現前していて、これが何かを映し出しているんだというようなことを最初に言われたんですけれども、それとともに斉藤さんがおっしゃられたように、パンであったりあるいは編集であったり、あるいは何らかのエキストラのものが付いて、それを物語化というのかある種の意味連関の中に落ち着かせてしまうのか色々あると思うんですけれども、その中でイマジネールというのはどういった。
加藤 写真の場合が「これはここにあった」だとして、映画の場合は「これはここにある」じゃないとわたしは思うんですよ。「これはここにありつつある」としか言いようのないもの、つまりちょっと待ってよと言っているうちに映画はどんどん先に行ってしまう、次のショットに移ってしまう。だからこそ映画というのは、ナイーヴな言い方に戻るけれど、現実そっくりであってしまう。現実のとらえどころのなさ、現実は「ここにある」のだと提起できない、その掴み取れないもの、そこが映画と現実が非常に似てしまっている理由なわけで、だからこそさっき言ったノスタルジーのノスタルジーみたいなことがあってしまうわけです。
北野 時間性ですよね。ある種の進行形が入ってきてしまう。
中村 そうですね、まさに加藤さんがおっしゃったように、今まさに生起している限りにおいてその都度逃れ去って行くものとしてしかないというのは、もちろんおっしゃる通りです。それはよく分かります。だからむしろ、これはもうちょっと後の話題になるのかもしれないですけれども、ヴィデオ等の装置によって我々はそれを止めたり巻き戻したりということができるようになったというのは、根本的にスクリーン上で映画を見るときの体験と異なる、こういう言い方は正確ではないかもしれないですけれども、映画をある種テクストに還元した形で扱えるようになってしまうという変化は起こったんだろうなと思いますね。
長谷 だから、イマジネールというのはすでにノスタルジーに一歩入ってるんじゃないんですか。どうなんですか。
中村 先ほどわたしがイマジネールについて出した問題は別の文脈だったんですけれども。あくまでも。
長谷 進行形というふうにもし考えるとするとね、映画の時間性を。あるすぐに逃れ去っていくものという。
中村 それはスクリーン上のイメージが何かの代わりとして表象しているという関係ではなくて、イメージそのものが逃れ去っていくがゆえに、イマジネールな対象になるということですか。
長谷 そんな難しく言おうとしたわけではなくて、まず北野さんがイマジネールなことと時間性の関係を聞きましたよね。それの答えが何かなと思って。
中村 「答え」と言われると、ちょっと難しいですね。…ただ、こういうことは言えます。逃れ去るということを強調する見方というのは、サルトルがフォークナー論で使った隠喩を借りれば、トラックの荷台に乗って後方を見ているような時間意識ですね。しかし、ムーヴィング・イメージというのは、後方へ去っていくというよりも、目の前での形象の変化だと思います。逃れ去るというのは、フィルムの走行については言えるかもしれませんが、映画において我々が見ているのは、言うまでもなく、フィルムのじかの走行ではなく、瞬間的に停止した画像の蓄積、ギブソンの表現を借りれば、「累進的(progressive)画像」なんです。だから、それはあくまでも現在の出来事なわけです。
北野 単純過去が、分からないよね。逃れ去っていく進行形がイマジネールだとか。
加藤 人はなぜいわゆる現実世界から離れて映画館に行くのかというと、そこには物語化され、パッケージ化された「現実」があるからですね(現実というのはさっき言った「これはここにありつつある」逃れ去っていくものであるという括弧付きの「現実」なんですが)、パッケージ化されているという魅力があるわけですよね、映画の。つまり自分の人生には始まりと終わりはないんだけれども、映画には始まりと終わりがあってしまうという魅力です。ノスタルジーというものにはやっぱり始まりと終わりがあるわけで、そのおかげで自分が生きてきた過去というものに始まりと終わりができあがって、物語と歴史はそこで重なるわけですよね。
中村 むしろそこをお聞きしたいんですけれども、そのこととイマジネールとの関係というのは。
斉藤 ちょっと話がずれてしまうかもしれないんですけれども。実はわたしが自分の博士論文を提出したときに、ピーター・ウォーレンがほとんど何も言わなかったんですけれども、ひとつだけ聞きたいことがあるんだと言って。メランコリーとノスタルジーはどう違うんだと言われて、わたしの論文はメランコリーに関してなんですけれども、色々話していて、ノスタルジアというのは基本的に喪失そのものが想像されたものではないかと、つまり実際にあって、たとえば自分の母親を失ったときにはノスタルジアは起きえない、それはメランコリーであると。つまりそれは喪失という体験が実際のオブジェクト(リアル・オブジェクト)に関わるものであると。で、たとえば人々はアトランティスに関してノスタルジアを持つことができる。たとえば観光地に行って、そのお土産を持って帰ることによってノスタルジアを持つことはできるけれども、つまり観光地というのは自分にとっては行って帰ってくる、もしかしたら戻ってきたときに不在にはなっても、それは喪失にならないのではないかと。その辺がもしかしたらキーとしてあるんじゃないかなと。わたし自身もよく分からないんですけれども、ただひとつ思うのは、いわゆる古典的ハリウッド映画なんかでもそうですけれども、あの古典的ハリウッド映画が娯楽として、つまり娯楽映画として快楽をもたらすのはどんなメランコリー体験でも一種のノスタルジー体験に変えられるからじゃないかなと。それがなんらかの形で、ある映画ですとかある作家でもいいですけれども、ある種の映画がどうしても実際の喪失体験に、見ている人でも作っている本人でもいいですけれども、関わってしまったときになんらかの形で別のものが出て来るんじゃないのかな。エンターテインメントがノスタルジーをどう使うのかというふうに考えると、ちょっとイマジネールの話とずれちゃうのかもしれないですけれども、ただイマジネールというのは少なくとも想像界という、ただ想像上のものではなくて想像界という考え方からすると、やはりそれは本当の喪失体験、たとえば母親を実際に失っていなくても、分析的に母親を本当に失ってしまったという恐怖、本当の喪失に触れる体験があってこそイマジネールになるんだと思うんですね。つまり、鏡像段階で自分のあったと思った自分に関わる、なんらかの形で本当の対象だと、自分にとって愛のある対象、それはどんな形でもアイデンティフィケーション、同一化というのは必ず最初にエモーショナル・タイであると、感情的な繋がりがあって同一化というものが起こるのであって、そうするとそこがなんか違うのかなと。そうすると、時間の問題と自分とその対象の問題で、たとえば日本人にとって古典的ハリウッド映画を見るというのは、やはり全然文化的な状況が違うし、100%ノスタルジアですよね。ただその中において、ある種の物語とかある種のイメージというのがアイデンティフィケーションされたときに突然それが何らかの形でメランコリーみたいなものに変わって、プンクトゥムじゃないですけれども、ある全くテクストから発生した意味生成がなされるのかなというふうに考えたことがあるんですけれども。ただ写真だったらそこに実際ものとして、スーザン・スチュアート的な意味でのスーヴェニアじゃないですけれども、ものとしてタンジブルというんでしょうか、手に取れるものですよね。するとそれが無くなった喪失を埋めるものになるけれども、そういう意味では映画というのは手に取れるタンジブルなものではないから、そこにおいてもっとメランコリー体験に近いような感じはしてしまうんですね。ちょっと話がずれてしまって申し訳ないですけれども。
中村 いえ、全然ずれてないと思うんですけれども。写真の場合には、痕跡なんですよね。タンジブルというのはまさにそうで、その光の痕跡がまさにそこにあるという形であるからこそ指示対象については「それは−かつて−あった」という言い方も成り立つわけです。しかし映画の場合には、加藤さんもおっしゃって先ほどわたし自身も言いましたように、コマがどんどんどんどん目の前に現われては消え、また現われる。映画を見るということが可能なのは、その痕跡がどんどん交替していくからですよね。それによって映画的なイメージが初めて可能になる。ただそれをノスタルジーと結びつけることが必ずしも必要なのかどうかということがよく分からないので、その辺りもう少しお聞きしたいなという気はするんですが。
加藤 つまりなぜノスタルジーと結びつけなきゃいけないかというと、そこに始まりと終わりがあるからですよ、映画には。現実にはないにも関わらず。だからかつてアトランティス大陸はあったとか、昔、家内と新婚旅行でナイアガラの滝を見に行ったとかいうことを我々は口にすることができる。現実には得られないもの、現実の喪失感を映画は補完してくれるわけです。他方で現実の喪失感を再現しながら、一方で現実の喪失感を補完してくれる。それが普通の映画の基本構造です。
斉藤 現実の喪失というのは、やっぱり悲哀にしても喪にしても基本的には終わりはないわけじゃないですか。それはたとえば愛する人が死んでしまったら、そこの死んだときである意味では時間が止まってしまうというのがあって、時間が止まってもそれは必ずしも終わりではないわけですよね。そうするとただ映画の疑似喪失体験みたいにしたときに、たとえば映画がハッピーエンド、ジ・エンドになるというのはその喪失感にある程度、まあ偽でもエンドマークを打ってくれる、その意味で戻ってしまうというのはひとつあるのではないかなと。
長谷 斉藤さんが最初に知覚体験と物語装置ということをおっしゃった、その二重性みたいなことが今この水準で問題になっているような気がする。つまり、映画が物語装置としてなぜ発展していったのかという問いへの答えが、まさに終わりがあってノスタルジーになってという今説明されていることですよね。でも、もしかしたら中村さんは、そこで知覚体験というものをもう少しそちらに引き付けて考えられないだろうかという問題意識があるんじゃないのかと。
中村 そうですね…、物語として考えた場合にはまさにそうだと思いますけれども、ただそのときに物語を考えるということが、先ほど言ったイメージを表象として見るということになるわけですよね。物語をそこに理解する、物語として見るという場合には、目の前にあるものを別の何かの表象として見るということになってきますから、今のお話はそういう意味ではノスタルジーあるいは喪失というのがキーワードになってくるのは非常によく分かるんですけれども…。
斉藤 面白いのは、たとえば今全然別の授業で『カイロの紫のバラ』を見てるんですね。あれの中で、突然映画の登場人物が抜け出しちゃって、話が違うようになったと。で、観客の一人が文句を言うんです、「同じ物語じゃないじゃないの」と。同じ物語を見に来たのにという観客心理があって、それはひとつ面白いと思うのは、ある意味で物語というのはもしかしたら非常に似たものじゃないですか、そうすると物語はそこで終わるけれども、実は人はやはり同じものを見に帰るというところがあるような気がするんですね。
長谷 古典的ハリウッド映画、とくにジャンル映画に関してはそうだと思います。
斉藤 それが全てではないと思うんですけれども、ひとつの映画の制度ということを考えると、そこの部分というのは。
長谷 面白い問題だと思いますよ。
斉藤 だからたとえばジャンル映画がなくなったときにテレビが出てきて、テレビで水戸黄門を見るとき、毎回話の表層的な部分は違うわけだけれども、人々は45分になったらチャンバラが始まって、48分になったら印籠が出るというのを待っている。それはある意味では現実のようでありながら、現実ではそれはないわけじゃないですか。実際、映画の中で、たとえば大島渚の『帰って来たヨッパライ』の中で、同じ話がもう一度映画の途中で起こってしまうと、これは何か映写機の間違いじゃないかと言って映写室に駆け込んだ人がいるという話じゃないですけれども、その辺の、違うようでありながらも同じものを出すことのできる一種の映画、古典的なものというのは、さっき北野さんがちらっと、たとえばブルジョア的な主体性、違いますよ、大衆ですよと言ったときに、ただ大衆というのは一体何なのかというのはベンヤミンとかクラカウアーとか立ち戻って考える必要があると思うんですけれども、大衆心理というのがブルジョア的なそれと完全に違うかどうかというのはまた別の議論になると思うんですが、一種の娯楽、映画が大衆の娯楽として成立していたとすると、その終わりがあるということと、ヴァージョンを変えながらも同じ物語を語ることができたというか、その辺のところはあるのかなと。まあだから、そこでノスタルジアというのは本来だったらノスタルジアで終わらないものを人間というのは、なんかヒューマニズム的な考え方になっちゃうんですけれども、抑圧であろうと喪失であろうと、そこをある種の消費という名のもとにおいて代替するというか補正する部分というのが、制度としてそれをやることができたんじゃないかなと。
加藤 うん、もちろんそうです。たぶん「同じ物語」と言うのはトートロジーだとわたしは思っています。物語である以上は反復可能でなければならないのだから。
北野 僕もそこのところの話は嫌いではなくて、斉藤さんがおっしゃられたノスタルジアとメランコリーというのはすごく面白いなと思ったんですけれども、加藤さんと話をつなげて言うと、たとえば物語の語りに対して我々はそれにつき合わなければならないわけですよね、映画の場合は。それは基本的に設定されてしまっているわけで、それは本を読むときとかヴィデオを見るときとは全然違っている。しかも開始時間、終了時間だけではなくて、その間物語が語られていくディエジェシスの中で何かが進行していることにも、基本的に、最初のモビリティとイモビリティの話あるいはパッシヴィティの話とどこかで結びつくのかもしれませんが、つき合わなければならない。どうしようもない時間の流れに我々はどうしてもつき合わなければならないけれど、と同時にそのどうしようもなさの中で何か、同じものか何なのかは知らないですけれども、物語が語られてしまっている、というふうな二重性みたいなものがあって。たとえば心理に関してはよく分かりませんけれども、19世紀的なブルジョアが小説を読んでというときには、それなりに時間に都合が付けられた。だけど、大衆社会になったときに、大衆が映画館に足を運ぶというのは、それこそ制度的にかなり枠付けられているところがあるわけで、その中でしかも座って、語られていく物語を見て、でもその物語にコミットしてしまうというようなところというのは面白いなと思いますね。で、これは実は今日斉藤さんにお聞きできるかなとは思っていたんですが、あとひとつは小説と映画のことでいうと、登場人物を書くときに善悪をはっきりさせたりすること、あるいはある種のナレーターがモラル・ジャッジメントをすることが、小説の場合は結構可能で区分け整理していくことができるわけですよね。で、物語を展開させていく。でも映画というのは、少なくとも今の時点で、もしかしたらそもそも当初からいかに悪者が出ていても、ばあっとスクリーンに出て何かを喋ったり何か行動していると、どこまでこいつは悪い奴なんだろう、というか、それが感情なのか情動なのかという話は尽きませんけれども、僕はスター以降の問題というのはすごく大きいと思っているんですが、人物に対して役柄以前のところで何かを感じてしまうのめり込みかたというのもあるわけですよね。これは制度という話とちょっとずれていて、媒体の話になってしまいますけれども、いかがなでしょうか、その辺で、なにか映画には独特の快楽があったりするのかなと。次ページ→