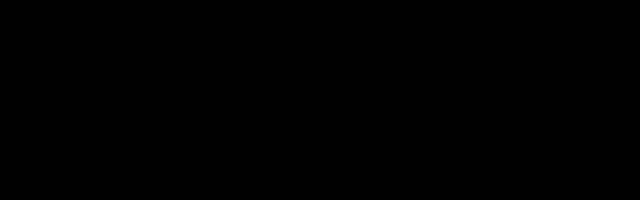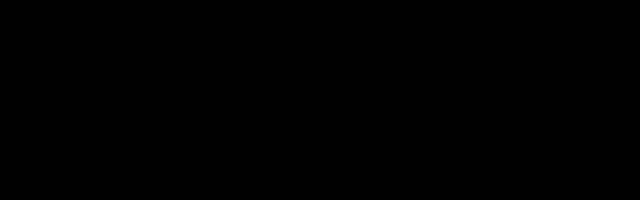
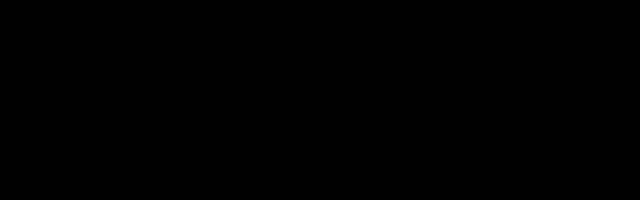
斉藤 論文のために色々読み直していたときに、ミュンスターバーグが面白いことに情動・感情に関する言説というのは古典映画の中には非常に伝統的に、まあ美学が関わっているという点においてその関係だと思うんですけれども、残っているんですね。やはり言語論になって、『スクリーン』派、精神分析はどんどん感情に関する言語を排そうとする、つまりそれは主観的な言語であるという理由において。先ほどのお話じゃないですけれども、精神分析が出てきたときには、基本的には科学的な客観的な言語であるという、メッツが精神分析と言語学と構造主義とかですけれども、特にラカンの精神分析というのは、そういう意味ではサブジェクティヴィティというものに客観的な言語を与えられるという、それはわたしは一種の幻想だと思っているんですけれども、その中でいかに科学的な映画理論というのが打ち立てられるかという使命は非常に大きかったと思うんです、いわゆるコンテンポラリー・フィルム・セオリーと言われる中で。ミュンスターバーグの一番最初の、もっと古いものもあると思うんですけれども、体系的に書かれた映画に関する理論書というものを読み直して見ると、面白いのはクロースアップの問題ですね、顔の問題というのが出てきてしまって、ミュンスターバーグがエモーションというもの、彼は当時の、いわゆるジェイムス・ランゲ理論というのがあるんですけれども、ジェイムス・ランゲ理論に結局影響されている形で、エモーションというのは完全に肉体的な反応であるという考え方をしているんですね。つまり感情というのがいわゆる、まあわたしたちが今思うようなフィーリング、主観的なものではなくて、それは身体言語であるというような考え方をしてると。まだ1915年においては、もちろんスターというのはできていましたし、1910年代からメアリー・ピックフォードとかチャップリンとかが出だしましたけれども、古典的な意味でのスターシステムが確立されつつある時期だったわけです。そのような歴史的状況においてミュンスターバーグが言うのは、たとえば悪役だったら悪役の顔を選ぶのが非常に重要であると。そういう顔を選んでその表情、それでエモーション、感情的に観客は同一化をしながらも、最終的に色々な同一化をしても最終的に主人公に同一化するというのは、主人公のクロースアップによって、たとえばあとは顔の違い、クロースアップの扱い方の違い、そういうもので変わってくるんじゃないかと書いているんですね。それがやっぱりスターシステムというものができてきて――それはエイゼンシュテインもそうですけれども――いわゆるタイページと言われる顔で選んだですよね。それが古典的ハリウッド映画になって、ある意味では、つまり悪役でもスターが演じるわけです。ジェイムズ・ギャグニーがスターを演じたときに、それは悪いキャラクターでもその階層付けが為されるような気がするんです、本当の悪い奴。本当に悪いヒーローに、それをある意味では、システムの中で上手く利用される形につながっていくようになったというのはあるんじゃないかと。ですからクロースアップというのも、感情の問題というのを話すと、それは古典映画理論においては、基本的にはドゥルーズがもちろん『アフェクション-イメージ』の中で主張していますけれども、やっぱりクロースアップであると。で、そこがわたしはある意味ではひとつの限界にもなってしまったのではないかという気がするんですけれども。つまりそういうレヴェルとクロースアップをある意味では直結してしまったというところが。だけれども少なくとも歴史的な意味で判断すると、いわゆるシステム化されていないスターシステムが無いところで、ほとんど知らない人達がタイプ的に出てくる、初期映画の中においてはあとはコードですよね。つまり黒いのを着ている人というのは、ジャンル映画の中で非常に重要でしたけれども、その辺がやっぱり気になっているような気はするんです。
加藤 北野さんは異なる二つの質問を同時に提起しました。その内のひとつにとりあえず答えておきたいのですが(エモーションとクロースアップの問題についても話したいんだけれども、それはひとまず措いて)、北野さんの一つ目の問題については、こういうことが言えます。つまり1930年代半ばに映画というのが世界的に娯楽のピークに達した当時、たとえば東京から船で香港に行くのにさえ12日間位かかっていた、そういう時代に映画館に足を運ぶのに12分で行ける人もいたし、やっぱり12時間くらいかかる人もいたかもしれないけれども、少なくとも映画館に足を運ぶだけで、そして映画館で12分なり2時間12分なりの上映時間に縛られるだけで、香港へでも、どこへでも行けちゃうというところが映画の醍醐味なわけです。やっぱり映画館に行くだけで聖地イェルサレムへの巡礼もかなってしまうという点が映画の魅力なわけです。
斉藤 でも、バーチのLife to Those Shadowsを読むと――わたしは歴史的なリサーチなんかはしていないので、どうしても二次資料からになってしまうんですけれども、今わたしたちが知っているような形で、つまり映画上映中は出ちゃいけないだとか喋っちゃいけないだとか、そういうのって制度的にでき上がったのは、ハリウッドのスタジオ・システムの、いわゆる制度として映画が成り立つにつれてなんですよね。ですから、ニッケルオディオンとか、いわゆるわたしたちが初期映画の観客と考えるような、それが実際どのくらいそうだったかというのはわたしは歴史的に正確には把握してないですが、少なくとも言説的によく言われる労働者であるとか子供であるとか、そういう人達にとっては必ずしもそういう制限はなかったであろうし、これはバーチの言説ですけれども、もし労働者だったとしたら、彼らにとってはもっと制限された労働環境の中にいて、たとえばフリッカーがあって目にも悪いとかいう環境の中においては、やはりそれはアトラクションになり得たというのがもう一つと、加藤さんが前に劇場の冷暖房について論文を書いていますけれども、必ずしもその時間というのを縛られるというようには。興行側はもっと何かを与える、ムーヴィ・パレスじゃないですけれども、実際には社会的にありえないソーシャル・イモビリティみたいなものをも一時の、たとえばそこへ行けることができるだとか考えられないような上流社会の、それは全然フェイクですけれども、そういうものを与えることによって、乗ってないですけれども、ある意味ではファントム・ライドですよね。でも一方で、制度的な決まりが出てくるわけです。快楽の御褒美の為にはこうするべきだという強迫観念が生まれてくる。去年、オノ・ヨーコの上映会をやった時に、見終わった後に女の子が「わたし、この映画嫌で嫌でたまらなかったんですけれども、なんかやっぱり最後まで見なくちゃいけない気がして」という一言を聞いて、でもお金を払って見に来ているから劇場を出るのは観客の勝手なのにと。で、それをしないという制度ができ上がってしまう。あと少なくとも、たとえばUCLAにエチオピアから来た先生がいるんですけれども、エチオピアなんかだったら上映中にみんなぺちゃくちゃぺちゃくちゃ話しまくっていると。
北野 ニューヨークもそうです。
斉藤 そうですよね。だから、そういう意味ではある種の制度的なものというのもあるのではないかなと。
北野 映画に関してある種の言説史を周到にするとしたら、たとえばその法律ですよね。検閲が何を対象としていくかということでやれば、映画館というトポスそのものからだんだんとそこで語られるものへ移動していくとか、映画的な快楽が変遷していくというのは、そっちからも色々と多様に捉えることができるのかなとは思うんですけれども。最初の問題に戻りますけれども、加藤さんの違う土地のものを違う土地に行けない段階、しかしながら世界的にある種の経済の依存関係ができ上がりつつあるときに、それができてしまうということには非常に興味深いイデオロギー機構があって、その中で快楽が産出されていたというふうには思っていますけど。
加藤 だからモバイル・フォン(移動電話)がこの時代に、20世紀の終わりにでてきたというのは何らかの必然性があるんでしょう。かつて電話というものは日本家屋の中でそれなりの定位置があった。玄関先ですね。玄関先は人が訪れる場所だったから、電話もまた外から声だけのお客さんが我が家を訪ねてくる装置として、その置き場所に玄関先が選ばれたというだけでなく、1960年代初頭までの日本では「呼び出し電話」というのがまだ一般的で、電話を持っているお隣さんが持っていないお隣さんに電話を玄関先で取り次いでくれていた。しかし、いまや誰も家にいない時代ですし、またマンションのオートロック機構によって誰も外からお客としてやってこなくなった時代ですから(つまりみんなどこかにつねに移動中なのです)、玄関先に電話を置いていても意味のない時代になった。同じようにして今日、映画館に行くということも不可能になってしまった。モバイル・フォン持ってから誰も自宅にいつかなくなったように、映画館で強いられたイモビリティを通してモビリティを得ることも不可能な時代になっている。
北野 現時点ではどうか分からないですけれども、少なくとも3年くらい前までは、ニューヨークより日本の方がはるかに携帯使ってますからね。それは何なんだろうなと。
斉藤 アメリカは去年くらいからですよね。
加藤 やっぱり狭いところからモバイル・フォンって流行るんだよね。つまり1990年くらいに世界に先駆けて香港で携帯がものすごく流行っていた。
長谷 なんかアジアで流行っているという印象が。
北野 強いですよね。
加藤 その香港の大流行が東京に来たかと思ったら日本全国に広がって。
北野 韓国に行って。
斉藤 さっきのベンヤミンに話を戻すと、先ほどの写真論としてベンヤミンが受け取られたという中村さんの話ですが、やっぱりわたしは映画論として読んだんですけれども、ベンヤミンのあの論文の中ですごく大事なのは、もちろん活字が第一段階で複製ですよね。写真で一種の第二段階に上ったとして、彼の理論の中ではたぶんあのナチの時代にああいう形で書かれたのは、ある意味では希望というものもすごくあったと思うんですけれども、アウラがない映画というものがあの時点でもうすでにつくられていたと思うんですね。ですからそういう意味では、本来彼にとってのユートピアとしてのメディアという映画を打ち立てたかったと思うんですけれども、ただそこでベンヤミンが言っているのは、今度複製になったことによって、人間が動くのではなくて情報が人間の方に来ると。そこによって初めて大衆、デモクラティックな形でのメディアができるという。それを考えると、もしかしたらモバイル・フォンは逆方向に行っているのかもしれないですね。
長谷 逆方向というのは?
斉藤 つまり、たとえばテレビの紀行もの、もう映画でそういうのって無くなっちゃったけれども、今でもテレビを見ると5分間くらいの番組でも紀行ものみたいに世界のどこかに行ってそれを見る、で茶の間でそれを見るという意味では、マクルーハンが言った「メディアはメッセージ」じゃないですけれども、メディアが来るわけですよね。でもそうすると今はどんどん、たとえばDVDなんかも同じような路線として考えられますけれども、逆にテクノロジー的なものに今度は情報が来ているという感覚よりも、情報が来ている範囲に人間の行動範囲、イモビリティが制限されているという考え方もできるのかなと、ふと今思ったんですけれども。
長谷 そうそう、だから加藤さんの最初の話で、3Dシアターとかそういう新しい流れをモビリティとおっしゃったんだけれども、逆にイモビリティが強くなっているような気もするんですよ。人間の移動範囲の拡大とは、足を使わなくともたとえば飛行機に乗って座ったまま赤ん坊のように全てを与えられた状態で移動できることなわけですが、3Dシアターもむしろそれに近いと思うのです。人間にあらゆる刺激を与えてくれて、こっちからは能
動的に何もしなくてもいいというイモビリティ的な面も僕は感じるんですよね。電話もこっちから玄関先にまで行かなくても、携帯電話ではすでに身体に密着したところに情報がやって来てくれる。だからどんどん人間は個室の中に入っていってしまうというような凡庸な話になってしまいますけれども。
加藤 いや、携帯のポイントはやはりかつて電話線につながっていた部屋から出て、歩きながら、移動しながら情報のやりとりができるというモビリティの回復でしょう。ちょっと過渡的なことをたまたまわたしは記述しただけかもしれませんけれども、昨今の無知なメディア論者が進化論的に言うことには、最初、映画には色も音もなかったということです。無論そんなことはなくて、100年前の映画にも音はついていたし色もついていた。で今度マルチメディアは触覚を獲得しようとしている。まさにわたしがアイマックス3Dシアターで獲得したのはある種の触覚で、ああ怖い、こっちに来ないで欲しいと手を伸ばして恐竜を避けようとする、いい大人がそういう赤ん坊状態に戻ってしまったという。だから明らかに次世代のアイマックス3Dシアターは本当に触知可能な映像ということもやってしまうのであろうし、そうするとイモビリティによるモビリティとわたしが言っていたのは、単に20世紀的なメディアのひとつとして映画というのは、ある種のディシプリン、つまり前しか向いてはいけないとか、お喋りをしてはいけないとか、そういう時代を漸進的に反映していただろうということを言いたかったんで(一方に映画館でお喋りする観客がいて、他方にそれを嘆く同時代の評論家なり官僚なりがいたのです)、それがほら首を回してもいいような「自由な」21世紀が来ましたねということを言いたかっただけなんですよね。無論それも幻想ですが。
斉藤 わたしなんか古いからそういうのってやっぱり、来ないでとか思ってしまうんで、だからそれは問題なのかもしれませんけど、なんかその距離が心地よいというか。
長谷 事実としては映画館でも人々はお喋りしていたのであって、きっと精神分析学的な主体というのは本当に理念型的な観客でしかないと思うんですよね、加藤さんがおっしゃったように。でも、それが近代の理念みたいなものとして、そこには抑圧というものがどこかにあると思うんです。映画自体もある種の検閲みたいなものが、自主検閲システムにせよ何にせよ、抑圧としてどこかにあって、その上で主体というものが常にあるような気がするんですよね。たぶん現代の観衆が、自由に首を回せるとしたら、その抑圧がなくなっているように思うんです。僕も近代人だから、それに対して反発したくなるんですが、現代というものの分かりづらさとか語りづらさというのは、最初に抑圧がないような状態に人間が置かれていることにあるような感じがして、それが僕は現代のおぼつかなさと自分のポジションの取りづらさと結びついていると思うんです。さっきちょっと精神分析の語り方がもしかしたらもはや現代をあまり上手く語りきれないかもしれないと言ったのも、それと関連しているんです。
北野 携帯のお話が、長谷さんのおっしゃった点、非常に示唆的だと思うんですけれども、抑圧が同時に快楽を伴っているというのがあって、その在り方がよりどんどん用意周到に。だから携帯を持ったら家に電話があるよりもいろいろ動きながらできるんだけれども、もちろんそれは電波のあるところまでしか行けないわけだし、あるいはいろいろ機能的な回路付けが行われているわけで。交通にしたってそうですよね。時間をかけてものすごくお金があったら自由に行けているところを、電車の線路やら飛行機の航路が確保されてしまうと、基本的にはそれに制約を受けつつ移動しなければならない。同時にそれは異様に便利であって快楽でもあるというのがあって。すごく惹かれる快楽と同時に、ある種の回路付けの中に用意周到にどんどん組み込まれていくというような不安は若干ナイーヴかな?
斉藤 携帯を持っていると、今度は電話を待つ主体に変わってしまう、電話をかけるのではなくて。わたしいつも思うのは、へその緒みたいだなと、年寄りみたいな言い方だけど。電車に乗っている若者なんかでも、常に携帯を見てるし、携帯がへその緒で、社会につながっているみたいな。そうすると便利さと重要さの代わりに、今度は携帯によって規定されてしまうというのが出てくる。
加藤 ジョイスの『ユリシーズ』という小説で、へその緒を電話線としてエデンと交信するというイメージがちらっと出てくる。
斉藤 映画を考えたときに、この前ちらっと話を聞いたんですが、映画自体も今度ダウンロードできるようになるんですって。たとえば1時間半の映画だと20時間くらいかけてダウンロードできて、コンピュータで今度はもし映画を見られるようになったら、完全にそこに座ってしまう。まあテレビが入ってきた時の言説と似たようなものですけれども、そういう部分があって。少なくとも映画館にお金を払って見に行くというのは、ある契約の上でありますしディシプリンでもあるんですけれども、ある程度見に行こうという自発的な選択がなければ、見に行かないわけじゃないですか。そこの部分において少しずつ、だからそれがベンヤミン的に民主的というふうに考えるのか、グローバル・ヴィレッジというふうに考えるのか、その辺はちょっと分からないんですけれども。
長谷 ベンヤミンが言ったことが実現したら、案外民主的ではないんじゃないかという気はするんですよ。
中村 話を大分戻したいんですけれども、さっきの映画館の沈黙に関わる規範とか時間に関わる規範とか、日本でも最近になってすごく厳格になってきたと思うんですよね。ふた昔くらい前であれば、わたし自身も経験があるんですけれども、「私は(この映画を)ここから見た」というフレーズが成り立っていたわけですよね。途中でふらっと入ってきて、その場面に戻ってきたら出るとか、あるいはラストシーンをまず見てしまってから後で全体を見るとか、あるいは冒頭の場面だけをもう一回見るとかね、そういうことを結構やってたわけですけれども、最近はその辺の縛りがきつくなってきたんですよね。そういうみかたが長い間行われていたということと先ほどの加藤さんの物語は始めと終わりがあるという、その辺の関連についてどのようにお考えになっているのかという、これは質問なんですけれども。
加藤 さっきの斉藤さんの映画館に行くのは自発的な選択肢であるということにも関わるんですけど、つまり現実世界の中で暮らしているあなたがどれだけ映画に時間を割けるか、映画を見るということに割けるか、つまりあなたは都市生活者だったら1950年代には歩いて10分のところに映画館があったりして、田舎者だったら5時間くらいかかっても仕方がなかったとか、そういう問題はあると思うんですよね。だから映画の上映時間、始まりの時間と終わる時間というのは、新聞を見れば載っていたわけだけれども、その新聞を参照して映画館に行くまでの時間、着くまでの時間というのは人それぞれ違って、それに応じて、今中村さんが言われたような、途中から入場して途中で退場する観客というのはありえたと思うんですね。で、これはまた推測になってしまうし、答えにもならないのかもしれないけれども、交通が便利になった、JRが世界一タイトなタイムスケジュールを実行しているとかとといわれる今日に、入場時間厳守とか映画館の中で喋っちゃいけないというウォークマン享受世代の個人主義的ハイフィデリティの問題がでてくる時代になったのも、やっぱりこれも機械とシステムに応じた映画館の制度の変化ですよね。
斉藤 なんか一種のフェティッシュ化なんでしょうかね、神聖なものというか。
北野 清潔感というか。
中村 物語を受容するとき、たとえば小説の場合だと途中から読み始めても、もう一度最初から読むということはしませんよね、しようと思えばできるんだけれども。ただ映画の場合にはある時期までは比較的そういうことが、別にそれが逸脱した行為としてではなくて、行われていた。つまり、結末がどうなるか先にもう分かっていて、フラッシュバックなんかとも関連するのかもしれないですが、そういう消費の仕方と、先ほどの時間性ということで、始まりがあって中があって終わりがあるという物語を受容するという体験とがどういうふうに関係するのかというのが。
長谷 その場合は制度自体がかっちりしているわけですね。制度として規律が、何時から何時までというのがあるとするじゃないですか。そうすると逆にそこに行く人間には自由度があると思うんです。つまり、いきなり人間が抑圧されて規律化されているのではなくて、たぶん映画館という空間に規律がかかっていて、観客という主体との間にずれがあるんじゃないんですか。
北野 物語的に安定しているがゆえに自分に対応できる限りで分割して見ることができるというふうな担保を一応取れているので、そういうことも可能だったのではないかということも言えなくもないと思うんですね。
長谷 同じ物語の反復であるから、つまり次がどうなるかはらはらして楽しむというよりは、ある定型のパターンみたいなものを反復して見るという習慣の中だから、途中から見ることが可能ということですよね。
中村 ある限定された時間の持続の中で体験しないでも、自分で見て再構成するものなんですよね、ということがむしろそこから逆に分かるんじゃないかなと思ったんですよ、その物語というのを。先ほどの知覚体験と装置の関係、その関係こそまさにクルーシャルな問題であると思い続けているものですから。
北野 僕もあまり詳しくないんですけれども、「いや、北野さん、18世紀だったかな、本を見ているときに、読まないんですよ。ページを開けてそのページをぱっと見ることで快楽を呼び起こす。本は読むものじゃないんですよね」というふうなことを偽悪的に言っていた僕の友人がいるんですけれども、必ずしも小説だって最初から最後まで読み通さなくてはいけないというふうな規範が確立したのは、歴史的には、19世紀ですよね。
斉藤 ヒッチコックが『サイコ』の時に、商業的に途中から入れないというのをやりましたよね。あれなんかはやっぱり。ということは、その前までには途中から出たり入ったりというのがあって、もしかしたらあの映画の影響というのは大きかったのかなという気がしないでもないですね。それでもちろん全部変わったとは思わないんですけれども、やっぱりなんらかの形で。それとあとはアートシネマみたいなのが出てきて、たとえば二本立て上映というスタジオ・システムの時に全盛だったものというのは、基本的には二本立てなんで、映画の途中ではなくてもプログラム、今だったら一本という考え方じゃなくて二本のプログラムで、途中で入るとか出るとか、その辺がもうちょっと自由だったのかなという感じはしますけれどもね。
北野 物語に最初と最後ができるというのは近代なんですか。
加藤 いや、それはもうアリストテレスの頃じゃないですか。
北野 神話というのは、でも、そういう始まりや終わりが結構あるような無いような話ですよね。断片的な享受可能というやつじゃないんですか。
加藤 でも神話って起源をとうとうと教えてくれるようなところもあるし。『イリアッド』なんか読むと、もう起源への妄執ですよ。
北野 大体神話のどれをもってコーパスだと見なすかというのはあると思うんですけれども、とにかく全部が全部を把握しなくてもある種の共同体のヒストワールの起源の物語に、自分をそこにつなげることができたというのはあると思うんです。でも、説話が、いわゆるこう開いてこう終わるというのはどうなんでしょうね。たとえばオーラルと出版との関係が関与しているとか。語り部が最初から最後まで夜通し語っていたとは思えるような思えないようなものと、印刷されパッケージされた上で読まれていくものとは。
斉藤 でも小説そのものというのは、もっと後じゃないですか。たとえばだいたい18世紀の頃ですよね。で、最初の時というのは、もちろん分からないんですけれども、歌で詩を読むような形にしたとして、あとは演劇じゃないですか。そうすると、演劇自体は始めと終わりがあったので、途中から観るとか観ないとかいうのはよく分からないんですけれども、どうだったんでしょうね。
北野 まあその間に写本があると思うんですけれども。それに、祭祀的な演劇というのは日常とどこまで分離する形で行われていたのか、日常がどこまで祭事の区分だったのかということに関してはどうなのかというのはあるとは思います。まあそういう話は、あまりここで突っ込むとますます映画から逸れていく。で、汽車の話を聞きたいんですけれども、また。
斉藤 でも汽車の知覚というのは映画に似てますよね、本当に。
長谷 それは、まさにそうだと思います。
加藤 他に映画館のディシプリンについてエピソードがありますか。
斉藤 大島渚について書く機会があって色々読んでいたんですけれども、『日本の夜と霧』の上映とかで、あれもすぐに上映打ち切りになっちゃったんですが、70年代くらいに学生運動の関係でもう一回やったりするときに、場内で「異議あり!」とか言うのがすごかったみたいですね。それで、最後演説するところがあるんですけれども、大島が書いているんですが、「健さん!あいつ、ぶったぎってくれよ!」という一言があったらしくて、要するに高倉健にこんな気に入らない奴はもう斬っちゃってくれみたいな。だからやっぱりいろんな形であったのかなと、コミュニティ映画みたいなものが。わたしが直接経験したのでは、アメリカでチャールズ・バネットという黒人の映画監督がいるのですが、彼が長編の第一作(To Sleep With Anger)をつくって、それが奇跡的に全国公開されて、センチュリー・シティというショッピング・モールののなかのAMCといういわゆるマルチ・シネプレックスが14館ある中で一番小さい小屋で見たんです。その時にごくごく普通の映画館で見ていたわけですが、当然黒人の観客がたくさんいて、その人達がすごく話しかけるんですよ、スクリーンに向かって。対照的に、LAカウンティ・ミュージアムというところがあって、そこでよく言われるレパートリー上映とか特別上映みたいなものがあると、白人のカップルがいて、その二人は名物カップルなんですけれども、劇場内で誰かが話してたりするとすっと立ってですね、怒りに行くんですよ。その辺はどう解釈するかは別なんですけれども、すごく面白いなと。だからコミュニティによって全然。たとえば黒人の人達が、まだレース・フィルムという形で限定された、自分達のコミュニティだけで見るという、その時には本当にコミュニケーションとして成り立っていたんじゃないかなと。
加藤 それはそうでしょうね。最近映画館で観客が他の観客に沈黙を強いるもう一つの原因というのはヴィデオの普及があったのかしら。つまり映画を見るというのはパーソナルな、1対1対応のものであるという、とんでもない錯覚が若い世代に蔓延したことが。モーツァルトが生きていた頃は、モーツァルトの音楽を静かに聴いていた者など誰もいなかった。鑑賞のシステムが今とまったく違っていた。
中村 そういう話は事実として色々あるんですけれども、たとえばわたしは小さい頃母親に東映の時代劇によく連れて行かれまして、主人公が危機に陥って、それを助けに馬で駆けつける人物が現れたりすると、うちの母親なんかは手をたたいて「早く!早く!」と叫んでましたしね(笑)。それからあと、小川プロの上映の時にはセクトがいっぱい集まってきて、画面に自分のセクトが現れると歓声を挙げ、あるいは敵側のセクトが現れると罵倒したとかいう話もありますね。
北野 フェスティバルとしての映画とデモンストレーションとしての映画。
中村 ですから、映画館の中で声を発するということにも多様な在り方というものがあったと思うんですけれども、それが逆に個人的受容という形でむしろ一元化されるのかなという気はするんですけれども。
北野 僕がニューヨークのに行ったときには、とにかくよく喋るんでびっくりしましたけどね。そこまで喋るのかというくらいで。たとえばジム・ジャームッシュの映画を80年代に日本で見るとき、こちっとして固まって身構えて見るわけですけれども、アメリカに行ったら、わあっ笑い転げて見ているんで、そうかこれはコメディだったんだと。
長谷 そうやって観客の反応を現象的に追いかけていくと、どんどん理論枠が揺らいでしまうんですよね。ある種強引な、トーキー映画では観客は沈黙しているという理論は、実際の現象として調べていくと何も言えなくなってくるんですよね。そこがいつも悩むところなんですが。
北野 ダグラス・ゴメリーが結構注目をまた浴びていて、僕がいた当時ではやっぱり、認知派でもなくカルチュラル・スタディーズでもなく、僕らのような古色蒼然たる美学派でもなく、とにかくものすごく細かく、大量の資料を集めてきて。
長谷 僕もゴメリーなどを参考にして、映画館とか映画観客のことについて色々調べたん
ですけれども、それについてほとんど書けなかったんですよね。
北野 いろいろあるよ、になってしまう。
長谷 それじゃ論文にならなくて。
加藤 でも、この20年程のアメリカの映画史の論文ってそうじゃないの。先行研究ではこういう定説だけど、わたしが発見した資料だと定説にあてはまらないというタイプの言説構成で。そういうことをラッセル・メリットもチャールズ・マッサーもやっているわけで、それは彼らの後につづく新しい世代でも同じことで、先行研究を批判したマッサーが今度はやられる立場に回った。セオリーとしてのまとまりなんてことは、あまり気にしないリサーチ重視のプラグマティカルな(これは国民性でしょうが)論文や著作が多い。次々に新しい「事実」が発掘されつづけているこの分野では、まず映画史の新しい展開の可能性を重視する。
北野 「多様性がある」とかいうことで締めくくられる文章を見ると、ヘテロジーニアスであるとか、そりゃそうでしょう、と言うしかない。
長谷 僕もそれじゃつまんないと思って。
北野 理論的なものでも、デイヴィッド・ボードウェルなんかも、『メイキング・ミーニング』でも『オン・ザ・ヒストリー』でもそうですけど、結構自分自身の主張というのはほとんで言ってなくて、他の人のを整理することばっかりやってて、というのはちょっと。どこまで生産的なことがやっていけるのかなとは若干思っているんですけどね。で、その成果を見ると、結構、ウィスコンシン一派のデイヴィッド・ボードウェル、キリハラとか僕から見るとよく似たタイプの拡大再生産かなと思わなくもないところがあったりして。それでいて分析上活用されるラヴェリングだけが大きくなっていくんですよね、モニュメンタルとか。
中村 むしろその辺は北野さんにお聞きしたいんですけれども、アメリカの大学におけるフィルム・スタディーズあるいはフィルム・スタディーズの制度性といったものとそういった現象との関係というのは、やはり遠目に見ると明らかにあるんじゃないかと思うんですけどね。もう画一されてしまった制度の中で研究と教育が、いわば生産のオートメーション化みたいな形にされてしまって、どんどんペーパーがたくさん出て来るみたいな。
斉藤 ありますよね。
北野 ありますね。愕然としてしまうのは、イギリスでカルチュラル・スタディーズが立ち上がっているとき、『スクリーン』では理論的以前に知的な政治的な流れとして、別のバーミンガム・スクールの流れとか色々ありますけど、ある種の何か社会的あインパクトがあったと思うんですよ。だけどアメリカにやってきて、もともとある種の流れはあったんですけど、とにかくユニヴァーシティ・プレスの産業化と学会のコーポレイト組合化というか、そういうのがあって、その中でぐるぐる。ニューヨーク大学にカルチュラル・スタディーズをやってる研究者が何人かいますけど、そのうちの一人の仕事をぱらぱらと見ても、最初を見ただけで愕然とするんですが、「クラシカル・ポリティカル・サイエンスにおいては云々」と書いてあって、註があるからクラシカル・ポリティカル・サイエンスって何なんだろうなと思ったら、「自分の友達のカルチュラル・スタディーズの研究者が定義したところでは」と書いてあるだけで一体何なのか全然分からないという。ぐるぐるぐるぐる内輪の中で再生産しているという印象が拭い切れない。ユニヴァーシティ・プレスも絡んでいる。あれだけ全米の大学がたくさんになって、それれが買うから一冊出すと何千部と売れて採算がとれてしまうんですね、図書館回しというのだけで。その中で、自分達のブロックの中で点数を、というのがあって。ちょっとイギリス系のスチュアート・ホール以下皆が、アメリカのカルチュラル・スタディーズの有り様を見て愕然としたというのが伝え聞いたことがあるんだけれども、それはアメリカの文化の問題というよりも、やっぱり資本主義がここまで広がっていて、アカデミズムも消費化されてきたというところで。
長谷 でも逆に羨ましい気もするんですよ。日本にそのような資本主義化がない、学術的な言説に関して。
北野 ないですねえ!
加藤 それは単に日本のマーケットが今まで規制絡みで閉鎖的だったからじゃないですか。つい数年前まで国立大学では外国人教授を自由に雇えなかったとか。これから日本でアカデミック・マーケットを拡大するためには外部からお客を呼ぶ、つまり留学生をどれだけ日本の大学が獲得できるかということじゃないですか。外国から留学生がもっといっぱい来れば、日本の大学出版局も大きくなれるんじゃない。
斉藤 わたしは経験しなかったんですけれども、日本からアメリカに留学すると、よく出てくる問題というのは、あなた日本人だから日本映画やったらどう?っていうものですよね。つまり、一種のマーケタビリティというのと日本語が読めるというものですよね。そうするとある意味では矛盾が出てきてしまう。本来日本映画のリサーチだったら、日本にいてリサーチをした方が効率も良いし、リサーチのマテリアルもあるんだけれども、その中で特殊な、アメリカの中におけるジャパニーズ・スタディーズみたいなものがどういう形で確立されていくかということと、あとは一種のアイデンティティ・ポリティックスじゃないですけども、日本人だったら日本のこと、聞いた話によると平野さんなんかでも元々はユーゴスラヴィアでしたっけ、東欧映画に関心があったけれども、結果的には『天皇と接吻』という素晴らしい研究をなさったと思うんですが、そういう形でのプレッシャーというのは。たとえば、日本人だったら日本というのは、近年の80年代とか90年代以降どんどん強くなっているような気もするんですね。だからそれはカルチュラル・スタディーズであるとか映画理論の土台が崩れてしまってからは、やっぱりそれだけでは、というところはすごくあると思う。それが、最終的に全ておしなべて見ると悪いかどうかというのは別なんですけれども、そういうはっきりとした流れと流行というのはありますよね。
加藤 でも、その現象の半分は学問の普遍主義みたいなものに胡座をかいていて、つまり学的方法がアメリカで教育されれば、そのリサーチの対象は日本であろうがエチオピアであろうが同じような結論が得られるという傾向がある。
北野 僕は基本的にマルチ・カルチュラリズムやら多元主義やらというのは多くの場合もう既に保守反動だと思っています。よほどのものは別として、スローガンだけ掲げているようなものは、制度・システムの中で区分けをした上で人間の交通整理のために使われるスローガンになってしまっているというのはあると思いますね。
加藤 話は尽きないのですが、そろそろ会場を閉めなければいけない時間がきたようです。次回、作品論を中心に第二回シンポジウムを開催するということで、とりあえずお開きにさせていただきたいと思います。今日は本当に皆さんどうもありがとうございました。POSTSCRIPTS→
採録 藤岡篤弘(京都大学大学院在籍)