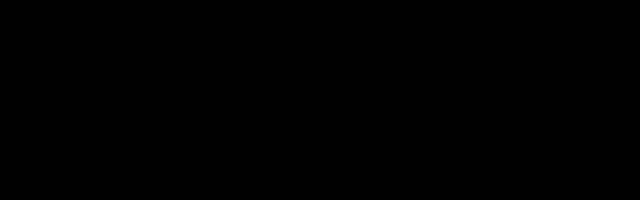3
われわれは、フランチェスカとキンケイドが心と身体を接近させてゆくプロセスが、一本の対角線をもつ矩形上の、至極単純な幾何学的運動にまで還元されているさまを見た。そこで二人は迂回や逡巡をくり返しつつ、最後には同じ地点で出会ってみせる。二人は、この単純な図形上で可能な運動を虱つぶしに試してゆきながら、出会いのドラマを反復しつづけているようにも見える。
今は、イーストウッドの顔について語るときだ。再び「運命の出会い」へと戻ろう。ポーチのすぐ先に停車した青緑色の小型トラックから一人の男が降り立つ。初老の写真家に扮したクリント・イーストウッドの姿は、当初ポーチの上から彼を見下ろすフランチェスカの見た目として、フル・ショットからニー・ショットあたりで示されるが、フランチェスカがローズマン・ブリッジへの道順をうまく説明できずに苛立つうち、ポーチを降りた庭先で、同じ高さで向かいあうことになる。突然の訪問者への警戒心からか、母語ではない英語をうまくあやつれないことのもどかしさからか、ここでもひっきりなしに手を動きまわらせるフランチェスカの不器用な様子に思わず笑みがこぼれるとき、ようやくイーストウッドの姿はバスト・ショットで提示され、ついにわれわれの眼につぶさに観察しうるものとして、イーストウッドの顔が現れるのである。その直前に両手をジーンズのポケットに突っ込んでしまったせいもあり、ここであのすばらしい笑顔を見せるクリント・イーストウッドは、まさに〈顔〉そのものだといえよう。体型の崩れの目立つ半袖のワンピースを着たメリル・ストリープに対し、夏だというのに、周囲の景色に溶け込んでしまいそうな地味なベージュの長袖シャツで上半身をぴったり覆ったイーストウッドは(その内側には、喉元を覆い隠すように肌着の襟がのぞいている)、ただ顔だけを外界にさらすため、ほかの身体的部位を布で覆い隠してしまおうと必死に努めているようではないか。
イーストウッドの顔が常に――だがとりわけ老いを重ねるほどにいっそう――すばらしいことは誰しも認めるところだろうが、しかしこの映画でのイーストウッドの顔は、少なくとも『許されざる者』(1992年)において一つの頂点に達したようなそれとは、すばらしさの質をいくぶん異にしているように思われる。『許されざる者』のイーストウッドは、それを前にしては誰もがただおののき、沈黙するしかない――ユダヤ一神教的な?――〈顔〉として、長年の浸蝕にさらされた険しい岩肌のような顔面を垂直に屹立させていた。これを見よ、そして二度とそれについて語るな――というわけだ。それが『マディソン郡の橋』においては、むしろ周囲のさまざまな自然の事物――木々の緑や梢を吹きぬける風、空に浮かぶ雲や地面に転がる小石とほとんど同等なものとして、物だけがもつどこか不穏なやすらいのうちに、その持続をただじっと耐えているように見えるのである。むろん、単に役柄の違いだといってしまってもよい。動くものなら皆殺しにしてきたという「許されざる者」と、絶えず自然のなかで仕事をしてきた人好きのする写真家とでは、その表情がまったく異なるのは当然だといえよう。だがしかし、それでも『マディソン郡の橋』でのイーストウッドの〈顔〉が、撮影当時六十五歳となっていた俳優=監督クリント・イーストウッドにしてはじめて可能であったような、ある存在様態のかけがえのないドキュメントたりえていることに変わりはない(われわれはこのような存在のありようを、のちに少なくとも一度――より過激な暴力を秘めたかたちでではあるが――別の映画のなかで眼にしているはずだ。身の丈ほどの長いコートで全身をすっぽり覆っていた、『カリスマ』[黒沢清監督、1999年]の末尾近くにおける役所広司である)。
あたりに立ちこめているのは、紛争のつづくタジキスタンとアフガニスタンの国境地帯に駐屯するロシア軍兵士の生活を記録したソクーロフの『精神の声』(1995年)での、あの戦場におけるいつ果てるとも知れない待機の時間に漂っていたのと同様の、灼けた夏草のすえた臭いである。樹木の幹や根、地表を覆うさまざまな鉱物と同じ色の衣服に身を包んだイーストウッドは、薄くなった白い頭髪を野の草のように風にそよがせながら、おだやかな微笑を浮かべて静かにたたずんでいる。ここでなんとも奇妙なことには、切り返しで幾度か映し出されるせわしなく手を揉むフランチェスカの髪の毛は、あたりに風などまったく吹いていないかのように、微動だにしないのである。差し向かいで対話しているはずの二人は、まるで異なる時空間に遠く隔てられて位置しているかのようなのだ。もちろん真相は、早撮りを得意とするイーストウッドが、中ヌキで要領よくスケジュールを消化していったがゆえの「つなぎ間違い」なのであろう。にもかかわらず、この「間違い」は決定的である。『マディソン郡の橋』においてこの「間違い」は、まさに二つの存在のあり方そのものの差異として、われわれの前に示されているからだ。一方には〈家〉の作り付けの部品として、しかるべきシステムの内部であらかじめ地位を定められた〈手〉がある。他方にあるのは、無数の力線に貫かれながらその持続をただじっと耐えている、ほとんど物質に回帰したような〈顔〉である。女を魅惑したのは、不意に到来したアヴァンチュールの機会などではない。男のそうした存在のあり方こそが、女に自らの手が〈家〉の隷属的な部品でしかない事実を発見させ、手になにができるかを彼女自身に真剣に思考させるに至ったのだ。
実際女は、ちょっとした諍いから男と気まずく別れた後、ポーチに置かれた椅子に腰かけ――男も好きであるらしい――イェーツの詩集を読むのだが、やがて立ち上がった彼女は、収まらない身体の火照りを冷ますかのようにガウンの前をはだけ、夜の外気にその裸身をさらすのである。それが、さっきまで一緒だった男の存在のありようを模倣する試みでなくしてなんであろう? だがその試みを嘲笑するかのように、夜空を飛び交う虫たちは、フランチェスカの無防備な裸身目がけて一斉に襲撃を開始することになる。この試みは、実現不可能な企てにすぎないというのだろうか? ……結局彼女は、執拗な虫たちの群れをはらいのけるというきわめて人間的な目的に、再びその手を従属させねばならないのである。