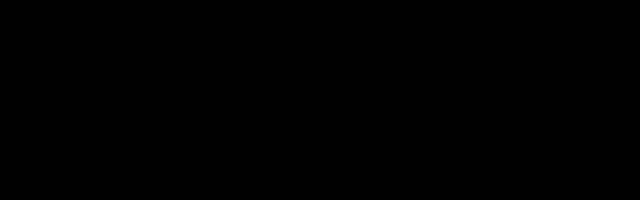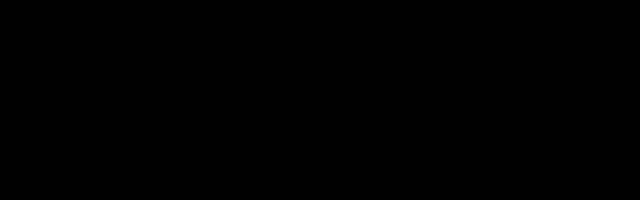
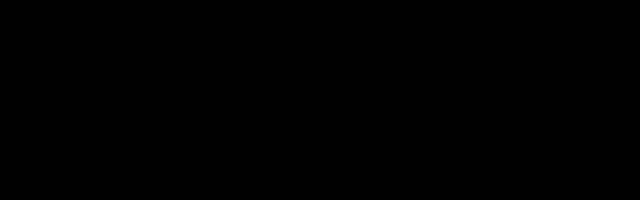
加藤 とりあえず話が一周したんで、あとはフリー・ディスカッション風にどんどん口を挟む形で話を続けていきたいと思います。ワン・サイクルしてうまく話がつながっているので、さすがだなと思って伺っていたんですけれども。
加藤 まずは映画を体験する、それが個人的体験なのか、歴史的主体としての問題はどうするのかというのもあります。その辺のことはまた後に譲るとして、映画を見て、そして映画を語るというところで、中村さん、長谷さんあたりとつなげると、まず一つ最初にわたしが言いたかったところにつながるんですが、どうも映画館の中で話してはいけない、特にトーキー映画以降は長谷さんの論文で社会学的にやられていたものもあったと思いますが、やっぱりパッシヴィティを強制されているところがあって、首を動かしてはいけない、首を動かしたらあなたは映画の幻想世界から外れる。喋ってはいけない、喋っても同じことだという。映画をアクティヴに楽しむためにはパッシヴィティを強いられるというところが制度的にあると。
映画というのは本来そこにはない(もしかするともう永遠に)失われてしまったものを現在進行形で楽しむ体験であって、したがって映画館を出た後でそれについて語るということは再現されたものについてもう一回再現し直す、物語化し直すという二重の再現作業であり、ノスタルジーをさらにもう一回ノスタルジー化する作業ということです。他方では、とりわけビデオが登場して映画的なるものがリピート可能になってきて(もちろん映画館が一日に同じ映画を何回も上映するというのはかなり初期の興行形態においてもおこなわれていたのですが)、映画は本来失われてしまってそこにはないものにこそ関与するものであるにもかかわらず、反復性というのが断固として確保されています(まあ、そこが映画の複製芸術たるところかもしれませんけれども)。一方、先ほどの中村さんのお話にあった角砂糖か固型飲料かをガラスコップの中で溶かすというプンクトゥム(個人的刺し傷)の問題。そこにあるのは古典的リアリストのハリウッド映画がいつも切り捨てる傾向にあった運動と時間の生の、物語という時間には取り込まれない、わたしにとっての「生」の現在を見せてくれる時間です。逆に言えば、映画が普通ノスタルジーたりうるのは映画の物語世界、スクリーンの向こう側の世界を我々は楽しんでいるからで、基本的に観客は映画館の中での出来事をすべて主観ショット化してしまう傾向があります。初期映画のファントム・ライドが見せてくれたトラヴェリング・ショット、つまりここではないどこかへ、時間的空間的に距離をおいた他所へわたしを旅発たせてくれる構造、失われた時空間への旅行という構造が映画にはいつの場合もあります。つまり失われたものが映画にとって重要なのは、まさに角砂糖をコップに溶かしていた自分というものがどこかにいて、あるいはもしかするとこれからそれがやってくるのかもしれませんが、その砂糖を溶かすというかけがえのない「生」の現在へと至るための幻視装置、それが映画の映画的なるものではないかと思っています。
もうちょっと簡単に言いますとね、斉藤さんが、わたしもかつて訪れた大学で集中講義をやって来たという話を伺って、どうも斉藤さんとわたしは授業のやり方が根本的に違うなということに気づいて、わたしが集中講義に行って何をするかというと、映画って面白いでしょという話しかしないんです。つまり自分が面白かった場面をそのまま観客に、この場合は学生たちに、再現して見せる(面白い理由をテクスト分析と歴史的諸考察において説明する)という、自分にとってなぜ面白かったのかというところから抜け出せないのです。斉藤さんみたいに、ちゃんとした客観的な映画史の授業ができない。
斉藤 そうなんですけどね、わたしも。理由付けるんですけれどもね。
北野 じゃあ、偽悪的な振る舞いをさせていただくとですね、先ほどの中村さんのプンクトゥムというかですね。僕はやっぱりそこのところにちょっと寝不足で今日はあまり頭が動かないんですけれども、僕の体験からいうと、そもそも80年代に何が嫌だったかというとある種の美学的な、これは、「…的な」ということで必ずしも蓮実さんご本人がというわけでは必ずしもないんですが、蓮實的あるいはドゥルージアンと呼ばれる形でなされた、いわゆる映画は光を見なくちゃいけないとか、雨のきらめきがどうこうというふうにですね、たくさんの美学的な修辞があったわけですよ。そんな修辞のなかで、「この映画監督の映画を見ていると椅子を蹴って出ていきたくなった」とかですね、あるいは「我々はただひたすら沈黙してしまうしかない」というふうな言回しがさらに伴なわれて、光の美学が形而上学化されたわけですよね。僕は個人的には映画って(唯物論的には)影なんじゃないのと思っていたんですがね。それはともかく、僕は映画で快楽を得ることは非常に少なくて、映画そのものの体験というよりも、80年代に映画を巡って体験してしまったことは、映画をめぐって、そしておそらくは映画を越えてある種の美学的な志向が、ある種のジャーナリスティックな知的言説の中心にあったところがあるわけですね、『リュミエール』から『マリ・クレール』に至るまで、そのような風潮であると思っています。まあ、それに浸って、わたしは映画をこのまなざしで見詰ていたのだとナイーブに信じる人も多いのだろうけど。そのような風潮には僕はほとほと嫌な感じがしていてですね、とにかくそういう形とは違う方向で文化なり映画なり何なりを語る術はないものかなと思っていたわけです。で、80年代末にアメリカに行くわけですが、アメリカにいると、いわゆるバザンの後、メッツ以降のですね、とりあえず美学的な評価は止めましょう、映画というものを語る手だてをいろいろ整えながら分析していきましょうという方向へ動いていった60年代『カイエ・デュ・シネマ』から70年代『スクリーン』の方向というのは、なるほどなあと思うところがあったわけですよね。そのようなラインは非常に重要なことなのではないかなと僕はどこかでまだ思っていてですね、一方で加藤さんも含めてですけれども斉藤さん達の努力のおかげで、ようやくいろいろな形で紹介されてきているというのがあると思うんですけれども、他方でまだまだドゥルージアンが強いというのがありまして。加藤さんも中村さんも書かれてらっしゃるものを見ると、『スクリーン』的なものをかいくぐりつつ、って向きがあるわけですよね。加藤さんの場合はある種の運動とか生の現在とかいう方へという通路があるように思うんですけれども。そのようなことを踏まえて、ですが、それこそ映画を語る言説の磁場を考えたときに今現在どのようにドゥルージアン的な語り方ができるのか、と問うてみたい気がします。中村さんのものも、先ほどの話でいうと視覚と言語の緊張関係という視点が他方でありつつ、片方では野生の映像というようなものがあったりなさって。そこら辺のところを中村さんの場合は今回ですけれども、加藤さんの場合は前からお聞きしたいなと思っていたんですけれども、どういうふうに考えていらっしゃいますか。
中村 そうですね…。たとえば先ほどの木村荘十二のフィルムですが、角砂糖が溶けていくという、あの例を出したというのは、自分で言うのも気恥ずかしいわけですが、あれはドゥルーズ的言説のある種の反復なわけですよね。まさにドゥルーズが『シネマ』の中でベルクソンを引いた、砂糖が水の中に溶けていくという例の、単なる引用ではないにしても、しかし少なくともアリュージョンであるのは確かです。それはもちろん意識して話したのですが、しかしドゥルーズ的な言説を継承するとか、あるいは今蓮實的な批評に対する風当たりが非常に強くなってきているから、あえてそちらの立場に立って戦うとかそういう意図でもなくて、むしろそういった言説も射程に入れるにはどうしたらいいかというのが関心としてあります。おそらくその辺りの作業をするときには、一つには歴史的に批評的な言説というものを後付けていく、読み直していくという作業が当然必要なことだと思いますし、もう一つにはなぜああいう形で話を始めたかというと、映画を語る言説というものの在り方ですよね。先ほど斉藤さんが存在論から言説論へ移行してというふうに非常に明快に整理して下さったんですけれども、それは映画についての言説の在り方の変化ということだと思うんですが、その映画についての言説についての存在論というものがね。北野さんがなさっている作業もおそらくそういうところにつながっていくはずのものだというふうに了解しているんですけれども。そういったことを考えていくとかなり危ないというか、無限後退ということになりかねないんですが、ただそういったところを今考えていかないと映画を巡る状況について何も得られない、言説を反復するだけのことに終わってしまうんじゃないかという危機感も一方であるわけですね。
ですからたとえば北野さんが例に挙げられた、日本での80年代のジャーナリスティックな知的言説の中心に映画があったんじゃないかという状況判断については賛成なんですけれども。それまで映画を語るということが一方ではある種まじめな、映画の中に人生を読むというような形あるいは映画の中に社会問題を読んでいるというような形で初めて映画が言説の対象になっていた。それ以外では映画は回避されてきたということが背景にあって、にもかかわらず、ある傑出した批評家の力によって突然一種のトレンドみたいになってしまったという、それこそ言説の社会的な存在論におけることですよね。それはある種気持ち悪いことであるし、それに対する批判というのが今起こってきているというのは健全なことでもあると思うんだけれども、そういったこともわたしは視野に入れたいと思うんですよね。ですから今フィルム・ノワールについてしようとしていることも、フィルム・ノワールについて語るときにまず口ごもるわけです。「フィルム・ノワールについて研究してます」と言うときに「フィルム・ノワールという…」の後が続かないわけですよね。皆さんご承知のように「フィルム・ノワールというジャンル」と言い切ってしまえない事情がある。その「フィルム・ノワールという…」のところに一体どのような言葉が入るのか、フィルム・ノワールを一般的な概念の中のどこに位置づけるのかという時に口ごもらざるを得ない状況、これは一体どうしてそういうことになってしまったのかということを、今調べつつあるし考えてもいるところなんです。ですからそれは非常に局地的な狭い範囲での作業なんですけれども、先ほど言ったような大きなプロジェクト、わたしだけのものではないんですが、今映画を語ることを巡って露呈しつつあるような、そういう問題性に触れる作業ではあるかなと思ってやっています。先ほど北野さんがまず「偽悪的に」というふうにおっしゃられて、本当はそこでいわばその喧嘩を買うみたいな形で役割を演じる方が生産的だったかもしれないですけれども、むしろそれは非常によく分かる話だとは思ってしまいます。むしろ対立するというよりも、おそらく考えておられることというのがかなり共通するものがあるのではないかと、とりあえずは言っておきます。むしろその辺りは長谷さんの方が別の観点から見ていらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども。
長谷 まず逆に僕が喧嘩を買っておくとすると、わたしには蓮實しかいないと言ってもいいわけです。いまだに蓮實しかいない。骨の髄まで全て蓮實的な問題体系の中でしか映画を考えたことがないし、映画を見たこともないです。そのことに抗おうという気もないくらいに、仕方がないというか、わたしはそういうふうに生きてしまったので、否定しようもなくそれはあるんですね。だからわたしの場合ドゥルージアンというよりは蓮實なんで
す。ドゥルーズの『シネマ』という本は、蓮實というものとは僕にとっては違う意味を持っていると思います。だからむしろ僕にとっては、日本の文脈の中で、今日本で映画について何かしら書くというときに80年代の蓮實の言説、まさに僕はそれにぶち当たってそこから出発したので、それ抜きには考えられないです。
ただ蓮實に対して美学的と言い切れるかどうかというところが僕の中ではあるんですね。もちろんひとつにはジョン・フォードのエプロンであるとか雨でもいいんですけれども、そうした細部への指摘があって、インパクトも受けたしびっくりした。ただそれ自体がまず蓮實さんのひとつの戦略ということですよね。それはその時の蓮實さんがいる映画言説の地場があって、その中でどうやって読者を驚かしてやるか、そしてどうやって地場を
動かしてやるかという戦略だったということがあると思います。むろん『リュミエール』あたりから薄気味悪い蓮實現象みたいなものがわあっと一般的に広がっていって気持ちが悪いと、それはわたしも全く同じなんですけれども、ただ『リュミエール』辺りから蓮實自身は変わってきたのではないか。つまり『ハリウッド映画史講義』にまとめられるようなあの仕事を読んだときに、蓮實は美学ではなくてある種の歴史性みたいなものを映画言説のなかに導入したような気がするんです。それまで蓮實が単に「素晴らしい」とか「美しい」とか言っていたのは、まるで山本益博のグルメ批評みたいだとか言って揶揄されていたわけで、僕もそうだと思っていたんです。でもそうではなくて、ちゃんとハリウッドのスタジオ・システムの問題とか、我々が今喋った問題体系みたいなものを提起する形で、蓮實さんは自分のそれまでの美学的な発言を歴史的な枠組みによって読み変えるという作業をされたような気がするんです。で、僕も結局それについていくような形で初期映画論をやったりしているので、やっぱり蓮實についていっているだけだと思ったりするわけです。
斉藤 そんなにハスミアンとは思いませんでした、長谷さんが。
長谷 いえ僕はそうなんですよ、たぶん。
加藤 ほんとにね、あの時代を日本で過ごしてしまった映画少年少女は確かに多大な影響受けていますよ。斉藤さんと北野さんは日本にいなかったからね、あの当時。
斉藤 あたしはOLしてたんですよ。OLは蓮實さんの世界には。
北野 僕も(日本に)いましたけど、ヤンキーもどきやってましたから。知的雑誌は読まない。
長谷 だからその蓮實の美学的批評をそのまま反復する梅本さんとかって確かに恥ずかしいと思うんですよね。だけど中村さんの場合、それをメタ的言説によって説明しようとしているわけじゃないですか、フィルム体験とか知覚体験は何かというように。蓮實さんみたいに「やっぱり雨がすごいぜ」とただ言い続けているだけだったら何も発展して行かないと思うんですけれども、そうじゃなくて蓮實さんが出した問題を、「野性の映像」とい
ったような別の枠組みで少しずつとらえ直していくことによって、僕は映画の持っている知覚体験の問題みたいなものを学問的に考えられると思うんです。だから逆に僕は映画批評というものをやろうという気が一回も起きたことがないんです。蓮實さんのやり方を真似て、そういうふうなことをやろうと思ったことは一度もないわけですね、不思議と。というかやろうとすると蓮實さんに似てしまうだろうという恐怖があって全然手が出せない。にもかからず僕は、明らかに知覚体験とか存在論とかフィルム体験とかというのも、ある種の政治的な文脈の中に位置づけないといけない問題だというふうに思っているんです。僕がそれくらい蓮實に惹かれてしまったとすると、どうしても知覚体験とか存在論とかプンクトゥムというものについて書くときに、単に客観的には書けない。というか、自分がどのように書くかというときに、やっぱり現状の言説の磁場でもあるいは映画自体でもいいんですけれども、それへの政治的姿勢を根拠にせざるを得ないと思うんです、否応なしに。もちろんそれと違う視点を出していただくとそこで喧嘩もできると思うし、そういう別の地場が形成されればそれはそれで面白いとは思うんですが。
加藤 春先にデイヴィッド・ボードウェルと会ったときも、自分はこれからアムステルダムで開かれる認知学系の映画学会に出かけるんだと言っていたのですが、その新しい次の磁場ということで、国際学会まで開かれているコグニティヴ派・認知派といったときに、先ほど北野さんの発言でパッシヴなという形容詞がついていたと思いますけれど、わたしも何編か認知派の映画学の論文を読もうと試みたところ、どうもどこが落とし所というかビューティ・ポイントなのがよく分からなくて、その辺を説明していただけないかなと思います。
斉藤 認知派というのはやっぱり心理学的な認知から来ているんですか。
北野 いや。コグニティヴ・サイエンスからでしょう。
斉藤 コグニティヴ・サイエンスって何なんですか。
北野 その辺の内容を正確に説明せと言われると僕もよく分からないんですけれども、名前が来ているのはもちろんコグニティヴ・サイエンスですね。
斉藤 もともと認知というのは心理学の概念ではないかと思うんですけれども、違うのかな。
北野 認知科学の一分野に認知心理学というものがあるという具合ではないでしょうか。
斉藤 認知科学ってあるんですか。
北野 認知科学をやると本当に頭がウニ状態になってくるんで、よく分からないんですけれども、従来の感覚・知覚・統覚みたいな区別というのを認知という名のもとに一括しつつ、その作用みたいなものを、もちろん科学ですから観察実験を繰り返しながら、しかもなるべくグランドセオリーに吸収されない形で綿密に解き明かしていくというふうな感じでいいんじゃないかと思うんですけれども。そこでは得られた成果の、昔の意味でのナイーヴなアキュミュレーションというんですか、累積というか、そういうことは実はあまり硬直したかたちでは信望されていなくて、相互に折り合わないものがあるならば、もともとのポイント・オブ・プレファランスというかですね、フレームワークというか、そういうある種の理論的概念を交通整理しながら推し進めていけばいいというようなプログラムだと思うんですけれども。
それはともかくとして、その話と今の中村さん、長谷さんの話をつなげるということになるとですね、蓮實さんご自身がいろいろ変化なさっているというのはもちろんそうだし、彼の映画への愛というかですね、それはある意味で僕も政治的に見ても一番正しいんじゃないかと時々思うというか。それに、映画を見なくても蓮實さんの文章を読んで感動してしまうということは確かに僕もあるんですけれども。さらにはまた、実際昨年、講談社現代新書で山内昌之さんとの対談が出ましたよね。そこでおっしゃってますよね、映画を趣味でだけ語っていては駄目なんだということにようやくわたしも気づき始めましたとか。そういう一節があるんですけれども。ともあれ、先ほどのお話とどうつながるかというと、70年代の『スクリーン』的な発想でやっていったときに、言語をモデルに、少なくとも言語を軸・中心に語られてきているところがあって、それに対して映画のヴィジュアルなものあるいはバザンが一応リアリズムと名付けたようなところのものを、改めてどこかで射程に入れつつ映画を語っていかなくてはいけないというふうなところは、僕もそう思っているというのが一点ですね。
それからもう一つは山本益博のグルメ批評の話じゃないんですけれども、蓮實さんは一応括弧に入れておいて「蓮實的な」文章で言うとですね、その映画への愛を美学的に昇華していくときに、それが80年代日本に訪れた消費社会なり何なりに対する目くらましじゃないですけれども、芸術映画ではないにしろ、ある種の特定の映画が美学的に評価されていって、映画の装置としての社会的機能とか社会の中での位相みたいなものにあまり目が向けられなかったというのはあったと思うんですよ。そこで加藤さんが今僕に問題を提示されたのは、美学的方向ではない形で何かあったのだろうか、あるいはこれからありうるのだろうかというと、それはもしかしたら、たくさん可能性があるのかもしれませんが、『スクリーン』だって、70年代には構築論者のジェフリー・ノウェル=スミスなんかが先導していて映画史などないんだというようなことを言ったことはありましたけれど、70年代後半から80年代は映画史的な作業もするわけで、さらには、たまたま昨日からうちの図書室で90年代の『スクリーン』の近年の歴史論をまとめた論集を見ていたんですけれども、これは90年代に入って『スクリーン』が認知派にある程度シフトしたのではないかという感じされ示しています。僕はベン・ブルースターなんかは転向したのではないかと思っていますけれども。構築論者にしろ認知派にしろ、まずはそういう映画史論的な方向性がありますよね。また、先ほどの話で、「映画固有の何かの体験」に対してどのようなスタンスをとるかという問いを洗練させていくという方向だってある。認知派というのは一区切りにはできないですけれども一番端的に表れているのがノエル・キャロルで、ミーディア(媒体)のことは考えない「ポスト・ミディアム・セオリー」と言うんですよね。この場合ミーディアというのはいわゆる社会学的なミーディアではなくて絵画のミーディアにしろ彫刻のミーディアにしろそういうものを含めてですけれども、彼はそれこそメディアを巡る言説、理論的な構えみたいなものの変遷をなるべく用意周到に辿り、現在の位置を測定していくという研究方向は可能だと考えていると思うんですよね。僕は前に加藤さんにお聞きしたことがありますけれども、視覚的なものが物語化・ナラエティヴァイゼーションされるといったときの、そのようなおおざっぱな括りを大前提にして、それをまるごと批判するというのではなくて、言語で語られていた物語と視覚的に語られていた物語というのは、どこがどう違っていたのか、その関係性はどのように変遷したのかというのはもっと綿密にできる話だと思うんですね。実際、最近最も刺激的な著作のうちの一つだと思っているキットラーの一連のものがありますけれども、視覚的な物語においてドッペルゲンガーがなくなっていくとかいう話をしているところもあって。あるいはジェイムソン的になりますけれども19世紀、書簡体小説が近代小説になっていくときに、すでにポイント・オブ・ビューというものがいろいろ手なづけられながら小説の説話法のある構成のなかに入っていくという時があるけれども、それと映画のポイント・オブ・ビューはどこがどう違うのかという話は、十分に可能なのではないかという気がするんですね。たとえば語られないものを見えているものだと極端に戦略的に概念のチャート化するとしてもですね、それをしかし実体的に美学化してしまうことではない方向で、あくまで語られないものは語られないものとしてあると、その上でそれをめぐって紡がれた言葉の推移を分析していくということですね。別の言い方すれば、そのような作業のなかで言説の組み方をどんどん変えていく、交通整理していくという形でやっていくことも可能なのではないか。そうすると、もちろん認知派がそうでしたけれども、スタイルの問題一つを語るときに映画の産業構造の変遷あるいは映画の技術の変遷みたいなものとを連関させながら、非常に綿密なスタイルの歴史というものを描いていくことができるということはあると思いますけれどもね。僕は必ずしも認知派ではないんですけれども。
加藤 いわゆる認知学派的な映画学の論文を読もうとしたときに、何も新しい知見が見えてこないから途中でいつも投げ出してしまうんですけどね、わたしは。言語学的記号論が一時流行った時に、すごくつまらない映画論が輩出したあの30年前の悪夢をふっと最近のコグニティヴ・サイエンス・フィルム・セオリーに見たりして、どんな新しい成果が出てくるのかなというのが楽しみのようで、よく分からないので、ナイーヴな質問をしてみたんですけれどもね。
北野 おっしゃることはある意味でその通りだと思うんですよね。たとえば蓮實さんのあの無根拠な断定とかというのは、危ういところであると同時に非常に魅力的であるというか韻文というか文学的な感じがあって、それに比べると認知派というのはものすごく散文的であると思うんですよ。ただ、それでも、たとえば、「クラシカル・ハリウッド・シネマ」というのが、構築論者のナイーブな物言いのなかで、描かれている物語世界に対して透明性を保持しつつ観客を没入させていくというふうにおおざっぱに言われるときにですね、認知派は、非常に微に入り細に渡る調査と観察をしてですね、もちろんディープ・フォーカスの問題であったり、デイヴィッド・ボードウェルが言うところのモンタージュであったり、あるいはまた時間の圧縮とか引き延ばしとか空間の移動とかいう技法であったり、さらには自己言及的な仕掛けまでも含めて、クラシカル・ハリウッド・シネマの中では「透明な」物語を逸脱してしまうことは十分に認められていたどころか、積極的に活用されていたというようなことをどんどん解き明かしていったわけですから、それは成果がなかったわけではないと思いますが。
斉藤 ボードウェルがコグニティヴと言い出したのは、そういうものの後ではなかったですか。
北野 いや、ボードウェルは70年代から『スクリーン』と喧嘩していて、基本的には対立点は、構築論者はおおざっぱにしか映画の画面を見ないからという点だと思います。『ナレーション・イン・ザ・フィクション・フィルム』においても基本的に彼がクラシカル・ハリウッド・シネマの大きな特徴として見るのは、明晰さであって透明性ではない。実際今回訳された『新映画理論集成』の最後の文のところにもですね、原文であればイタリックでですね、「しかしながら重要なことは、こうした大部分の普通の映画においてさえ、観客は知識・記憶・推論のプロセスに従って形式と意味を構築するということだ。古典的映画の観衆がどんなに型にはまり、透明(イタリック)になってもそれは一つの認知活動であり続けるのだ」ということをあの時点で言っているわけなんですよね。だからこれがコリン・マッケイヴの「古典的リアリスト映画」とかジャン=ルイ・コモリの「透明性の映画」と混同されただけで、これは混同した方が悪い。もともとアメリカの映画がどたばたとしていた時期なのでみんなが混乱していたとは思うんですけれども、ポジションは当初から違っていたのではないかと僕は思います。
斉藤 よく分からないのが、わたしはそれぞれポジションが違うと思うんですね。もちろん『スクリーン』派とコグニティヴ派みたいな形でカテゴリーに分けたとして。ボードウェルが認知派だとカテゴリーすることによって得られるものというのは何なんですか。
北野 僕が彼らを認知派と呼ぶのではなくて、彼ら自身がそう自らを名づけているだけです。さらには、彼らに立って言うと、ノエル・キャロルとデイヴィッド・ボードウェルも僕は違うと思うし本人たちもお互いそう言い合っている。トム・ガニングだって付かず離れずですし。しかし『ポスト・セオリー』なんかをまとめていく際、あるいはボードウェルが『メイキング・ミーニング』を書く際、あるいはノエル・キャロルが『ミスティファイング・ムーヴィーズ』を書くときに念頭に置いているのは、自分たちも認めているように、『スクリーン』の業績を認めてないわけでは全然ない。バザンはともかくとして、バザン的な作家主義の評価の仕方から離脱して、映画を語る枠組みというものを整えていって、映画をいろいろな形でかつ社会と結びつきながら形で語られるようにして、それでどんどん成果を上げていったことは確かであろうと。しかしながら80年代の終わりあるいは90年代の初めに至って、当初に比べるとインパクトがなくなっということもあるんですが、認知派と称しはじめた彼らから言わせると、概念的枠組みの弱さによってあるいは理論立ての弱さによって、映画に関しておおざっぱなことが言われたりそれが故にでしょうけど、アルチュセール・ラカン派の映画論というのは、映画経験のなかで重要な差異であろうものを見過ごしてしまう事態になっていっていると。ここで映画理論というか研究というものをもう一度見直して見る必要があるのではないかという広い意味での反省を促したというのが『ポスト・セオリー』なのであるという気はしますけど。それがまずは企みであったと。
中村 今北野さんが言われた点の、特に最後のところに関連して質問なんですけど、いわゆるコグニティヴ派というのは、たとえばラカン=アルチュセール的なものに影響を受けた理論に対して、それはグランド・セオリーだというふうに批判するわけですよね。彼らのグランド・セオリー批判の標的には実はハンセンやガニングがベンヤミンを援用したりする場合も含まれていて、あれはカルチュアルリズムでり、「ヘーゲル主義」的(!?)なグランド・セオリーだというふうに攻撃される。その時に認知派の理論的な枠組みというのが、あくまでもそれ以前の70年代以降の映画研究を支配してきたある種のイデオロギー的な枠組みを掘り崩していくための、つまり認知派の理論を強い意味で主張したいというよりもむしろ戦略的に前の時代にドミナントであったものを掘り崩していく破壊的な用具として使われているのか、あるいは認知科学に依拠するということを別の形で、メディアの本質を語るための理論として本気で用いようとしているのかという点が疑問です。たとえばノエル・キャロルの「メディアの本質を語ることに意味はない」という言が先ほど引かれましたが、映画の本質的心理的な語り方をめざすか反本質的な語り方をとるかという問題にわたしは非常に興味があって、むしろ後者の方で言説だけではなくてキットラーを引かれたように映画以外の文化装置との絡み合いを分析していく中で映画という対象が言説的あるいは非言説的にどう構築されてきたのかというのは非常に興味深い問題だというふうに思っているんです。認知派のスタンスとしてその辺りがどうなっているのか、つまりもう一つの本質主義的な語り方を導入しようとしているのかあるいは、そこら辺りはかなり自覚していて戦略的にやっているのかというところが今ひとつわかりにくいところです。
斉藤 今の中村さんの質問にちょっとプラスした形で、認知派にとって言説というのは一体何なのかなと疑問に思います。認知派の考え方によると歴史性とか政治性というのはどういう形で入ってくるのか、つまり人間の知覚ですとか、わたしが理解する形では科学という名のもとにおいてある種のグランドセオリーに取って代わるユニヴァーサルな人間というひとつの機械を想定して、その中においてユニヴァーサルなものを求めているのではないかという感じが少ししてしまうんですね。もしかしたら違うのかもしれませんが、そこに出てくるある方向性つまり言説分析の中に、もし人間が機械だとしたら、それをサブジェクトととらないとしても、歴史的文化的なある状況の一点におかれた一つの有機体であるような、まあ有機という言い方が正しいかどうか分からないんですけれども、その辺と方向性としてわたしは違うものがあるような気がするんです。中村さんの質問とつながる形になるんですが。
北野 『ポスト・セオリー』の段階では旗揚げであったと思いますね、副タイトルが「リコンストラクティング・フィルム・スタディーズ」でありますから。本当にいろんな人が集まって書かれているところがあって旗揚げだと思いますけれども、コグニティヴ・サイエンスを積極的に、それでも括弧付きですが、「グランド・セオリー」として取り入れてるのがデイヴィッド・ボードウェルとかウィスコンシンの一派で、ノエル・キャロルはあまりそんな気はないと思いますね。だからデイヴィッド・ボードウェルは映画言語の中にある種の普遍的なものがあるんだということを言ってしまっているところがあるわけで、おいおいと言いたくなるんですが。現在どうなってきているかというと、デイヴィッド・ボードウェルはトム・ガニングにしろ何にしろ、仲間内も潰していこうとしているなという気はしなくもないですね、『オン・ザ・ヒストリー・オブ・スタイル』を見ていると。ただややこしいのはですね、認知派は基本的に人間の認知活動というのは、自己批判的に成長していくというか拡張していくというか、複雑になっていくということを当然のごとく認めているわけですよ。だからメンタル・コンスティテューションにおいてですね、決まった形の何かがあって、それに当てはめてとらえていくという方向ではない。認知派としては、対象にしろ心にしろ、何ら理論的な前提は持たないというのが基本的なスタイルだと思いますが。
加藤 やっぱりナイーヴな質問ですけれども、もしそれがコグニティヴ・サイエンスから派生しているのであれば、サイエンスというのは追試可能性というか実験可能性、つまりある一定の条件下では同じ現象が万人に起きねばならないということを前提としているはずですね。精神分析学がサイエンスではないと思うのも、どうも万人に対して同じことが起きているということがなかなか共有しづらいところがあるからです。精神分析学もそろそろ100年くらい経っているので、学的流行としては比較的長命な方です。しかし認知派が今後どれだけ長命たりうるのかというと、どうなんでしょうか。パターン化、理論化しないと科学にはならないし、再現可能性というのは得られないから。
北野 科学基礎論的な言い方をすれば、検証性とか観察可能性とか経験主義性とかいうことに関して、ものすごく丁寧に概念整理しつつ、科学というもののとらえ方そのものを変えていっているところがあるのではないかとは思ってますけれども。ともあれ、少なくても認知派にとっては精神分析が想定しているある種の無意識概念ですね、これは危うい。映画論に関わらず分析哲学の方からも、あるいはその他のいわゆる最近「心の科学」と言われている方向からも、精神分析の無意識概念あるいは精神分析がいろんな諸事象の因果性の危うさみたいなものがいろいろ指摘されていて、それに寄り添う形でなされているわけです。ともかく人間の心とか対象世界に関して、認識論的前提あるいは存在論的前提というものをあまり立てないでやっていきましょうというような感じなんだと僕は思いますけれども。
中村 斉藤さんの質問されたことでもう一点、歴史性の問題ですよね。たとえば前の時代の映画理論がスペクテイターシップというのを、ある理念的な観客のモデルを立てて、それが非常にアヒストリカルなものだと批判される。しかし、認知派の場合も、一切の前提を立てないということはほとんど不可能ではないかと思うわけです。やはりある種のスペクテイターシップというものを置いているとしか思えないんですよね。にもかかわらずそういう人間学的前提について、そういう前提を置かないのだと彼らは強く主張している、そういうものは置かないでやっているんだと。もしそうだとすれば、その辺りが彼らの研究の射程という点で歴史的研究とどうつながっていくのか。先ほどの『ポスト・セオリー』のお話で、まさにあのペーパーバックの表紙なんかも非常に挑発的な、ローレルとハーディが三角帽を被って授業をして非常にばかげた数式を書いていて、あれはグランド・セオリーをおちょくっているんだというのは、それこそヴィジュアルに読みとれるわけですが、あの本の中でわたしの記憶に残っているのは、ヴァンス・ケプリーのソヴィエト映画観客論ですね。20年代のソヴィエトにおける労働者クラブについての歴史的な、非常に良いサーヴェイを書いていて、あれは認知派の道具立てというのをほとんど必要としないような社会史的なデータに基づいた、その限りで明快なものであったと思うんですけれども、その辺りも含めて、認知派における歴史性との関係というのをお聞きしたいと思うんですが。
北野 対象の領野と心の活動に関してなんら理論的な前提を立てないと片一方で言いつつ、具体的に作業を進めていくときには何らかに寄りかかっていて、とりあえず今手に入る、彼らにとってそれなりに有効性がある、具体的には楽観的な精神分析あるいはアルチュセール的な社会イデオロギー論とは違うもので有効性があると思われるものを使っていっているところはあると思います。それに関して問題性がないかというと、僕自身はやっぱり思いっきりあると思っているんですよ。これは何回か発表しようと思って、ある程度は書いているんですけれども、少なくとも日本で発表しても仕方がないものなんですが、デイヴィッド・ボードウェルあるいはウィスコンシンといった連中は、1960年代の近代化理論を90年代になってある種のアメリカの社会科学の連中が洗練させていますけれども、それに則っているところがあって非常に問題があると思いますね、イデオロギー的に。社会学者の方がお二人いらっしゃって恐縮ですが、あの悪名高きロストーの「テイク・オフ」ですか、デイヴィッド・ボードウェルの本の中にあの単語が出てくるんですよ。そういうところに非常に問題があると思っています。
加藤 その辺りをもう少し説明してもらえますか。
斉藤 近代化理論というのは何なんですか。
北野 近代化理論というのは、個別共同体レヴェルでの社会発展論なんですけれども、1950年代後半から冷戦構造の中で出てくるんですけれども、マルクス主義的な植民地解放理論あるいは社会の発展論ではない形で自由主義、資本主義側が社会の発展や成熟みたいなものを理論的に整えていく、それが個別社会の発展段階論になっているわけですよ。がらっと変わるのではなくて、徐々に移行していくという感じだと思います。近代化を示すいろいろなインディケーターがあるんですけれども、そのインディケーターがある程度出揃ったところで、これを近代社会というのではないかなと。理論形成そのものにもステップがいろいろあったようですが、少なくともある時点で日本が決定的なモデルになっていたと思います。そういうものがあったわけです。
加藤 それとデイヴィッド・ボードウェルが小津安二郎を論じることがパラレルというわけ?
北野 めちゃめちゃパラレルですね。それはもともとデイヴィッド・ボードウェルが小津論を書いて『スクリーン』に出したときに、典型的なオリエンタリズムではないかということで叩かれるわけですけれども、デイヴィッド・ボードウェルは1920、30年代において日本は十分に近代化を成し遂げていた、少なくとも日本の映画産業というのは垂直統合を初めとして、あるいはハリウッドの言語の吸収においてもそうであって、その上で小津はモダニスト的な実験をやったのであるからこれはオリエンタリズムでも何でもないという形で反論したというふうに僕は考えています。そのために社会学総動員であのような本を書いて、どうだと。そういう形で歴史に関しては若干危ういところがあるとは思うんですけれども、ただ中村さんの先ほどの質問につなげると、ベンヤミンからクレーリーに、そしてトム・ガニングのラインだとは思いますけれども、ヒストリー・オブ・ヴィジョンの視覚体制あるいは視覚文化編成の歴史として歴史をとらえるといったふうなものに関しては、グランド・セオリーであろうと裁断しているのは確かだと思います。僕自身それもまたいろんな意味で反動的だと思っていて、ただしかしクレーリーだって様々なコンテクストがあるとは思うんですが、たとえば最初に日本に紹介された時は『批評空間』の大澤真幸の解釈がありますが、あれって結構グランド・セオリーですよね。
長谷 それは大澤真幸だからだよ。クレーリーではない。
北野 クレーリーを読むときに、ヘテロジーニティというのを十分に確保しつつ、その効果として出てきたある種の視覚編成なんだというところをクレーリーの本から十分に読みとれていないというか、読みとれていたのかもしれないですけれども、僕がそれを読んだときにはあれっと思ってしまって。
長谷 だんだん議論が細かくなってきたんで分からないんですけれども、認知と言うからにはある種の人間中心派というような気がしますね。観客が映画をどう認知し、それに対してどう反応するかといった、観客を主役にしようという理論の流れが一つあって、その中で出てきた究極的な考え方であるように思うんですが。
北野 それはちょっと違っていて、基本的にグランド・セオリーを確保せずに観察・検証である種のパターンをセンサーしていくところがあるので、個別領域が全く好き勝手に進んでいくことがあるんですよ。その上、映画を分析するときに、異様に精緻であるといってよくなかなか反対派は皆かなわない。また、たぶん僕が気持ち的に属している派とは全然違う脈略ですけれども、最近の『オン・ザ・ヒストリー・オブ・スタイル』は作り手側からの話ですよね。だから観客の話ではないところもカバーできる。もうレセプション・セオリーはいいでしょうというところがあるかなとも思います。レセプション・セオリーでは映画の美学は出てこないだろうというのがあって、それと他のものがどう折り合い付くかということに関しては今後またやればいいわけで、とりあえずスタイルの歴史というものを作り手の視点に立ってからやりましょうと。
長谷 それも認知派の仕事なんですか。
北野 ボードウェルの仕事ですね。
加藤 いまのところ彼の最新の書物たる『オン・ザ・ヒストリー・オブ・スタイル』が認知派の仕事なの?
斉藤 分からないですよね、正体がつかめないというか。
長谷 正体ない感じが。
北野 正体がないわけではないんですよね。
斉藤 ボードウェル達の理論によると、映画があり、観客というのは、学習能力を万全に整えた人間がいて、その人間達は映画を見ることによって学習していくという形だったような気がするんですね。つまり学習というのは認知論的にある種のキーを学んだり、たとえば古典的ハリウッド映画ならば、それが作り出した規則みたいなものを見ることによって学んでいく、受け皿的な、ある意味ではサブジェクトではないですけれども、似たような。サブジェクト自体がラカンの言ったように無意識で何もないところから全て言語によって形成されるという考え方ではなくて、最初から準備万端のヒューマンであるというモデルなだけであって、それがよくわからないんですね。先ほどのお話ですと、あの人(ボードウェル)はネオ・フォルマリストじゃないですけど、そちらの方に近いのかなと。
北野 もちろん基本的にはおっしゃるとおりだとは思います。ただ精神分析が考える心の働きと認知派が考える心の働きとは接近しているところがもちろんあるとは思うんですけれども、無意識を認めるか認めないかというのは大きい話だと思うんですね。
斉藤 哲学的な問題ですよね、完全に。
北野 哲学的というか基礎論的な問題だと思いますけど。その意味で観客の受容の歴史ももちろんあるでしょうと。ただ視点を別にとれば、特殊な観客としての作り手側が作り手側の学習というものをするわけで、それをおおざっぱに一緒にするとまずいのではないでしょうかと。もっと細かく、あるいは別の区分けもできるかもしれないですけれども、少なくともレセプション・セオリーがこれだけ跳梁跋扈したあとですね、映画研究あるいはカルチュラル・スタディーズにおいて美学が消えているというのは確実にある。一番最初の話に戻りますと、ドゥルージアンでない形での美学というものを立ち上げる別の方法は何があるかといったときに、一つの参照点になるかとは思いますが。ただ基本的に斉藤さんがおっしゃられたようにネオ・フォルマリストというか、こてこてのフォルマリストなんで、出発点からそれですから。たぶん彼が読み込んでいるほど、彼が映画を鑑賞できるほど普通の観客はできないでしょうというようなところが、やっぱりあるんだと思いますよ。
斉藤 北野さんが先ほどちょっとおっしゃられたように、ボードウェルに関しては、やっぱり美学なのではないかと思っていたんですけれども、それはそうなんですか。
北野 美学だと思いますよ。美学というか美術史の一分野としての映画というものを絶対に立ち上げなくてはいけないということは思っているところはあると思いますよ。
長谷 先ほど観客の話じゃないかと質問したときに考えていたことがあるんですけれども、アルチュセールとか精神分析派と比較して認知派はどうこうという話になってましたけど、ドゥルーズに対抗してという言い方のほうが僕には分かりやすいんです。つまりドゥルーズの映画理論って簡単に言ってしまうと、人間のいない世界、人間なんか無くても映画はあるんだというふうに主張していたのが僕には最大の衝撃だったわけです。人間が見
なくても映画はあらかじめ存在する、観客の眼は映画の一部にすぎないと。それまで僕は人間がまず存在して、人間が知覚することによって映画が生まれるという考えでいましたから、ドゥルーズを読んだときに、人間以前にすでに映画はあるんだというふうに言われて驚いたんです。ある意味では観客という存在を理論から消してしまったので、精神分析学とかから批判されるということもあるんですけれども、そういう立場にドゥルーズが立
った。それがむしろ面白いんですよ。だから認知派のように、どこかで人間(観客)を置いて考えるという立場との間に対立軸があるのではないかということを僕は言おうとしているんですが。キットラーも、そういう意味では非=人間派だと思うんです。「メディアのことは考えない」と説明されましたよね。でもキットラーはむしろ、メディアがあってそれをどう受容するのかという問題の立て方ではなくて、メディアというものそれ自体の
凄さでいくと思うんですよね。そうするとメディアとかキャメラという機械みたいなことを中心に置いて、機械の方から映画を記述してやるのか、それとも認知する側の、観客の受容の方を中心にとらえるのか、一つそういう対立軸があるのではないかと。それでドゥルージアンがどうこうおっしゃっていたのかなと。
北野 とにかく僕はドゥルーズのことは避けているので、よく分からないんで、他のものはともかくとして映画論は読んでいないんですよ。ただ、中村さんがどこかでお書きになっていたように、視覚的なものと言語的なもののある種の対立関係というか緊張関係の中で、近代の芸術の歴史みたいなものはとらえるべきじゃないのかというフーコーを見出したのはドゥルーズですよね。
中村 その場合の視覚的なものと言語的なものに対して、最初の話から出てきているんですけれども、もうちょっと説明してもらわないと応答できないのですが。
斉藤 ドゥルーズとは関係ないと思うけどな。
北野 ドゥルーズの「フーコー論」で。
長谷 としたら、フーコーでしょ。
北野 フーコーには色々あるわけで、『スクリーン』のフーコーもあれば、いわゆる記号論的というか構造主義的に還元されまくったフーコーというのもいるわけですよね。それではなくて、見えるものと語られるものの還元不可能性、あるいは見えるものと語られるものを何か同一の枠組みの元に了解しうるということを言っていないフーコーもいるわけですよね。
長谷 それはドゥルーズがフーコーに見出したことですよね。
北野 はい。僕は読んでいないからよく知らないんですけれども、ドゥルーズの映画論は、少なくともクリスチャン・メッツに対する反対から始まりますよね。
斉藤 それは「時間−イメージ」の方ではないですか。
北野 僕、クリスチャン・メッツは非常に面白いと思っているんですが、当初、構造主義的な手法を取り入れて映画をどうにかこうにか語ろうとするときに、とても歯切れの悪いところがあって、つまりバザン的なリアリズムというか先ほどの話で言うと、記号論にしたいけど映画のスクリーンに見えているものの言語的枠組みへの還元は不可能だというふうに逡巡しますよね。これは妥協の産物であると言いつつですね、ショットは語でないとか、それは文であるととりあえず言うしかないとか、非常にぐちゃぐちゃとしながらやっているところがあって。しかしながら精神分析が入ったときに、それを想像的と象徴的という二つのプロセスの話なんだというふうな、視覚的なものと視覚が語るものの整理をつけてしまうところがあるわけですよね。それってある意味で見ることの快楽、見ることを貫く欲望とか色々の主題を出した貢献はあるとは思うんですけれど、もしドゥルーズが反発している「人間」というものがあったとして、それが精神分析的な主体であるとするのなら、認知派もそうであって、アンチ精神分析型「人間」であって、つまり、認知派は、先ほどから申し上げているように、心の働きに関してはとりあえず何もメカニズムを想定しないというのがあるので。
長谷 想定しないと言われると困ってしまうんですけどね。
斉藤 でもそれでなんで認知と呼ぶんでしょうね。
長谷 心っていうのが気持ち悪いということ?
北野 ですね。
長谷 もっと科学的な。
北野 いや、そっちでもなくて、その中間の非常に危ういところにいくわけですよ。
長谷 システム論みたいな?
北野 だから、『フィルム・アート』でも言われていますけれども、とにかくクエスチョンが違えば、ある対象を語る言葉はどんどん変わっていくということをボードウェルは平気で認めているわけです。クエスチョンをどう立てるかということに対象をどう語るかは激しく依存しているというようなことまで言っているわけなんですね。ですから、ある意味で、人間学的な人間をドゥルーズは想定していなくて、認知派は想定している、というのではなくてですね、両方とも想定していないんじゃないかという感じがしますけど。それだったら精神分析のほうがそれを想定しているんじゃないかと。
長谷 だんだん話が難しくなってきたな。まだドゥルーズの説明が半分くらいしかできていなかったのかもしれないけど、つまり僕がドゥルーズを読んで面白かったのは、映画が人間に対して無関心であるとすると、そういうものを人間が見るという経験は人間にとって違和性があるので、人間が自己批判的な発展をするために有効ではないかと思ったからです。映画という機械が生み出すイメージが、人間の有機的メカニズムに合わないようなメカニズムを持っているとしたら、それは人間が普段生活しているものと違う方向に自分の認識を開いていく、そのような可能性があることが逆に見えてくるわけです。同じように、少なくとも精神分析では、たとえば心を層にして、無意識ではこうこうだから人間が変わっていくという可能性を人間という装置の中に組み込んでいるという面白さが僕にはあるわけです。そうすると認知派というのは、映画を見て自己批判的な発展をしていくと
か言っているらしいのですが、それでは一体どういうふうに変わるのでしょうか。ドゥルーズや精神分析なら、まだなんとなくイメージで分かるんですけど。
北野 僕は、精神分析が自己発展していくというのが全然分からないんですよ。だって無意識が想定されている以上、無意識の中で起こることというのは埒外なわけですから、無意識の中でぐるぐる回ってしまうのではないですか。
斉藤 無意識というのは、フロイトの考え方によると、なんらかの形で葛藤があって生まれるものですから、埒外で、そこが哲学的な矛盾でもあるんですが、埒外でありながらも必ず出てくるものという想定なんですよ。
長谷 出て来なければ話にならない。
北野 何が出て来なければ?
斉藤 無意識が。そこが精神分析は哲学の矛盾であるという批判は、いくらでもされているんですが、フロイトにとってはそれが矛盾であるかどうかは関係なかったわけですよ。つまり、どうしてこういう現象が起きるのかを考えたときに一つのモデルを立ち上げたわけですね。無意識は、大きな意味での歴史ではないけれども、個人の歴史に関わってくるものだと。そういう想定ですよね、ラカンは別ですけれども。
北野 無意識概念には矛盾があるけど、それはそうとしか言えないんだと言われると、僕自身は何とも言えないんですが、無意識によって我々の知的活動が条件付けられているとした場合に、我々が意識的な行動をとりつつ我々の思考を発展させていくということに関しては、どこまでチャンス・オペレーション以上のものを期待できるのでしょう。無意識を想定していて、無意識に我々の知的活動が条件付けられているとしたら、我々が意識的に我々の知性なり思考というものを展開、改良していくことをどういうふうに考えることができるのですか。
長谷 そもそも意識活動も無意識との関係においてしか成り立たないから、無意識も意識が抑圧する。
北野 僕は僕の無意識に関しては知り得ないわけですよね。それが大前提ですよね。
長谷 後から知るわけですよ。
北野 それだったら、認知派と。後から知る。後から知り得るんですか。
斉藤 こうなるとあまりにも離れてしまうので、たとえば映画を考えるとするじゃないですか。そうすると、映画の中でひとつ出てくる問題というのは100%観客は映画を知りうるかという問題とつながってくると思うんですね。つまり100%作った人が映画を知っているか。もともと精神分析的な理論がイデオロギーとの関係で出てきた折というのは、それまでは作り手がいて、作り手の意図性ですよね、インテンショナリティで全て語られてきたわけです。ブレッソンがある映画を作る、ブレッソンがあるショットを撮ると、それはブレッソンが全て分かった上で、それで作家主義という形になってきたわけですよね。つまり、全てコントロールされている形であると。ドゥルーズはある意味では、精神分析を超越して、テクストをテクストではないという全く別の考え方で提示していると思うんですけれども。そうしたときに映画が、逆にたとえば産業的なスタジオ・システムの中において、B級のものをつくろうとしたら80分のものしかつくれないから、その制約があると。それによって全てが説明できるかどうか。それで説明できないと感じる人々が、それは見る側との関係において出てくるものだと思うんですけれども、じゃあ、なぜこのショットがというところにおいたときに、ひとつはスタイルの変遷というものを、ボードウェルが「作り手に戻った」と言うのは、ある意味で非常に帰結的なところではないかという気がするんですね。そうしたときに、何か語られないものとか、その部分を語ろうとして、ある意味では精神分析的な無意識というものをテクストに入れ込んだ事情というのは、それが正しいかどうかは別ですけれども、あるのではないかと考えるわけです。
やっぱり映画というのは、ある種習慣というのでしょうか、つまり、作り手があって作った作品があると、それを受容する観客があると。そこの中では直線的につながっているわけではないわけですよね。だからそこを話すときに、たとえば理論的に無意識というのが正しいかどうかは別問題として、とりあえずあの時点では認知派とかそういうものではなくて、心のそういう不可視なもの、見えないもの、理解できない、メイクセンスしないものをどういうふうに考えるかという形で、ひとつ理論的に持ってきたもののような気がするんですね。
映画でいうと、たとえば、なぜグリフィスが500本近く一巻、二巻ものをバイオグラフで作ったときに、どういう形でそれまではなかったスタイルを作り上げていくか。スタイルの問題でいうならば、それまではキャメラが動くということは全然念頭になかったわけですから。イギリスのバンフォース社の有名なものを読みますと、子供がスカートを釘につけていて、子供のショットを見せるのにキャメラが移動したのではなくて、子供が今度は逆側になって、動いている人達が反対の壁の向こうにと行くという。それからどういう形でグリフィスが、最初は後ろ側にドアがあったものを横と横にドアを合わせるようにしてショットとショットを続けるようになってきたのかということを考えたときに、それは100%産業的な問題だったのか、その辺がどうしても。映画というのは観客がいるかどうかは別として、そこにあるわけじゃないですか。それは装置として、ずっとある種の歴史を持って100年なりやってきたわけで、そこにおいてそれをどう解明するかというのを、それは映画が目的になるかどうかは別として、映画というものを巡るあるひとつの何と言ったらいいんでしょう。そこの部分から出てきたんじゃないかなという気がするんです。ちょっと話がずれてしまったかもしれませんが。
加藤 ボードウェルはその「小津安二郎」論に「詩学」というタイトルをつけているわけでしょ。だからボードウェルにとってはレセプション・セオリーであれ何であれ、まず作家がこれを作った、それで作品があります、そして観客がそれを見ますという少なくとも三つの層のあいだで、やっぱり作品がいかに構成されているかという作品の創造方法の層、すなわち詩学(ポエティックス)を中心にすえている。先ほど美学という話が出ていて、わたしには美学という意味がよく分からないんですけれども、ボードウェルがやっているのは詩学であり、その詩学的説明ために同時代の歴史なるものや産業史が担ぎ出されてくるのだと思っているけれども。
北野 「美学」という言い方に関しては、不用意だったかなと思います。認知派のモデルに関して不十分で申し訳ないんですけれども、たとえば――これは必ずしもコグニティブ・サイエンスかどうかは怪しいですが、少なくとも「心の科学」の最良の一部分ではあると思います――一番具体的なイメージとして分かりやすいのはマーヴィン・ミンスキーの「心のモデル」であって、複数のプロセスが同時に走っていると。こことここがくっついて我々はある意識的な活動をしているとか、ここのラインで今意識的な活動をしているという形で心のモデルを考えましょうというのはあるわけですよ。この複数の心の働きのプロセスが走っているときに、それは前意識と呼べるものはあるかもしれない、しかしながらそのようなプロセスの位相をまるごと実体論化してしまって無意識と呼んでしまって、それに我々が全くあずかり知らぬ因果性、欲望とその抑圧の相互作用空間があるんだというふうに考えるのはいかがなものかというところが認知派にもあるし僕にもないわけではない。それを考えていただければ、認知派の具体的なイメージが少しは出てくるかと思うんですけれども。
加藤 その辺りはわたしはどうかなと思っています。無意識を実体化する精神分析学を批判することは大事ですが、その一方で現場なるものが機能している歴史がある。つまり精神分析療法・セラピーという現場があって、それはやっぱりある個人の過去に起こってしまった取り返しのつかないことでも、心の傷は未来にかけて治癒可能だという前提に基づいている現場ではないんですか。無意識がどこかしら個人のある場所にできてしまった、しかし未来においては、その場所に向かって洞窟探検することができて、できてしまった無意識を、つまり過去を、未来と現在においてなんとか修復することができるのではないかという前提ではないのですか。そうした現場が神なき時代の神学としてであれ、談話療法として一定の成果を挙げている実績はあるんではないのですか。
北野 それはよく分からないですけれども。
長谷 よく分からないというか、常識的にはそう考える。
北野 それはある種の精神分析学の常識ですよ。ラディカルな精神分析だと、たとえば治癒という状態はありえませんよね。
長谷 だから問題は、無意識というのがただあずかり知らぬところにあるというのではなくて、ある種の意識とか矛盾とか葛藤とかを孕んで、意識に関わることだというふうに考えるのが普通ではないかと。
北野 意識とか無意識とか、細かい話になるといろいろ。
長谷 だから、そこにむしろ政治性とか歴史性が生まれる要素があるのに対して、認知派が複数のものがあるよと言ったときに、葛藤とかそういうものがないから、かえって社会性や政治性が出てこないのではないかという感じがするんですよ。
斉藤 なんか閉鎖されたシステムですよね。次ページ→