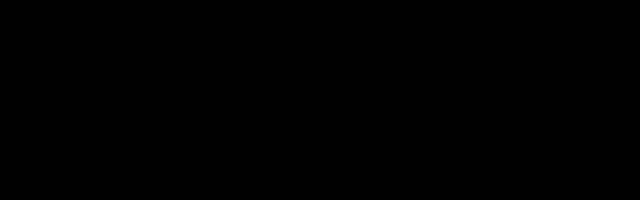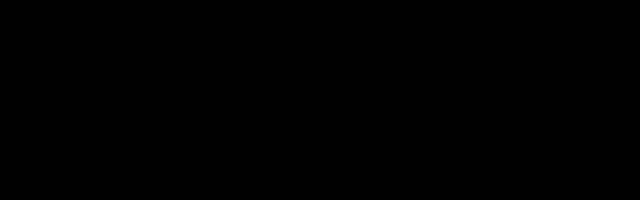
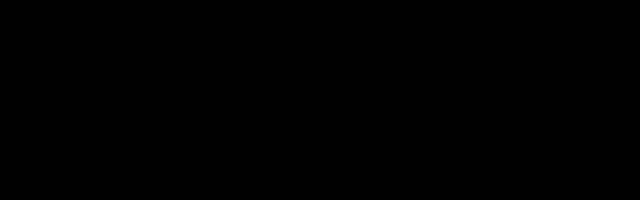
パネリスト:加藤幹郎(京都大学)、北野圭介(新潟大学)、斉藤綾子(明治学院大学)、中村秀之(桃山学院大学)、長谷正人(早稲田大学)
加藤 最近考えているのはモーション・ピクチュア(映画)を見る観客のことです。観客はモビリティ(運動性)を味わうためにイモビリティ(非運動性)を強いられているという、そういう問題系が一つあると思っています。わたしはなぜかしら旅先でアイマックスを見ることが多いのですが(シカゴとかホノルルとか大阪の天保山とか、東京やロンドンではまだ見たことがないんですけれど)。そうすると、自分がそのアイマックス・シアターで何をしているかというと、首を上下左右にティルトしたりパンしたりしながら映画を見ているわけです。つまりスクリーンの巨大さを自分の身体で確認している。普通の35ミリの劇場ではそんなことはなくて、従来の劇場のスクリーン・サイズに比べると、アイマックス・シアターのスクリーンは表面積で約15倍だというふうに言われています。それともう一つ、アイマックスを3D(立体錯視)で見ると、子供達が泣き叫んでいる。アイマックス3Dシアターでは5・6歳くらいの子供が泣き叫んでいる。3Dだと手を伸ばすところまで恐竜の口が伸びてくるように見えるんで、我々観客は手を挙げて、もう身体が反射的に恐竜の口が迫るのを避けています。そういう具合にして、わたしはこのアイマックス・シアターという新媒体で、観客が長らく失っていたモビリティを回復しているということに気づきました。それは実際、初期映画の観客がリュミエールの『列車の到着』を見て腰を抜かすなり浮かすなりして以来、一世紀近く失われていた身体運動です。一体いつ頃から、またいかにして35ミリ劇場で観客は自分の首をパンしたりティルトしたりすることをやめ、あるいは叫び声や話し声を上げることすら禁じられはじめたのでしょうか。
それともう一つは、偶然、長谷さんとわたしがほとんど同時期からじゃないかと思うのですが、映画と列車の関係について興味を抱いていて、今年たまたま『ファントム・メナス』という「スターウォーズ」シリーズのエピソード・ワンが公開されましたが、あのつまらない映画の中のどこでみんなが一番目を奪われ、心奪われるかというと、やっぱり砂漠地帯を猛スピードでエア・カーが駆け抜けるのを操縦席から見た目のショットで押さえた場面ですよね。そうすると、例のファントム・ライドと言われるもの(列車等の先頭にキャメラを積んで撮影した風景映画)がサブジャンルとして流行したピークがちょうど100年前の1899年くらいですね。去年出版された、チャールズ・マッサーがエジソンの映画会社のカタログを編纂したものを見ると、やっぱり100年前くらいの初期映画にはファントムライド系のものが多い。それから、ある論文に引かれていた当時の新聞によると、やっぱり圧倒的にそのファントム・ライドに驚いている観客の声が大々的に報じられている。そうすると人は映画にモビリティを錯覚して、それにモビリティをもって身体的に反応している。こういうことを考えると、モーション・ピクチュアの歴史というのは、列車は動くけどキャメラは動かない1895年の『列車の到着』ではなくて、むしろ1896年頃の『聖地エルサレムを列車で発つ』という、列車ごとキャメラも動く(それによって観客に自分が一緒に動いているという運動錯覚をあたえる)「列車の出発」から映画史も出発したのではないかと思うのです。最近、20世紀とはこういう1世紀だったのだというタイプの言説がはびこっていますけれど、それにならえば、20世紀とは、ファントム・ライドをいわばマルチメディア化した1905年の「ヘイルズ・ツアーズ」にはじまって、それから約80年後のディズニーランドの「スター・ツアーズ」をへて、1999年の『スターウォーズ・エピソード・ワン(ファントム・メナス)』にいたるモビリティの歴史であったということになります。言いかえれば、居ながらにしていかに運動性を獲得するかという歴史です。「ヘイルズ・ツアーズ」も「スター・ツアーズ」も座席が振動したりとか、ヴィジョンを主体にして運動性へ接近しようとしています。何が言いたいかというと、人間はその場を動かないで、ただ視線だけを特権化して、動くということをとことん味わう欲望主体として、ファントム・ライドから今日のヴァーチュアル・リアリティ装置まで基礎づけられているということです。
長谷正人 映画の現在ということを、加藤さんは観客のイモビリティからモビリティへの復活へというふうにとらえておられると。
加藤 まだはっきりとした確信にはいたってないのですが、たぶんそうだと思います。20世紀のどこかで映画のモビリティが失われてしまったという気がします。それが21世紀を迎えようとしているいまモビリティが復活しはじめていると。テレビを見るとき、たしかに我々は部屋の中を歩いたり家事をやりながらして動きつつ見ていますが、映画がかつて観客にあたえていた運動性はそれとは異質のものですよね。『ファントム・メナス』という映画の中で一番おもしろいところは、やっぱり主観ショットの、車載キャメラで観客に移動感を味わせる、その辺なんですよね。100年経っても映画の醍醐味というのはそんなに変わってないというのが一つあると思うんですよね。キャメラを動かすことで、動いていない観客にモーションの錯覚を与えるというのもやっぱりまたアイマックスの話に戻ると、別にそういうスター・ツアーズ系ではなくても、ヘリコプターに乗せたキャメラが地表すれすれを滑空していて、ふっとその地表が切れて断崖絶壁になったところだと、足下が崩れるようなそういう錯覚がアイマックスシアターの観客にはまだあります。だからその辺のヴィジョンを通したモーションの錯覚、モビリティの復権というのは、かなり否定しようがないところまできているなという、そういう実感があります。最近考えているのは、大体そんなところですね。次に長谷さん、お願いします。
長谷 わたしは映画に関して社会学的視点から考えてきましたが、その場合まず観客がどのように映画というものを経験しているのかということが、いつもわたしの問題系の核としてありました。ですから、今の加藤さんのお話はそれと非常に近い視点に立っているとは思うんですね。たとえば観客のイモビリティとおっしゃいましたが、その裏には古典的ハリウッド映画のイモビリティへの批判、つまりそうした映画がイリュージョンとしての
イメージに観客を閉じこめて、ある種の能動性や世界に対する批判的意識を失わせてしまうという批判があると思います。そういう観客のイモビリティを生み出すある種の映画に
対して、能動性や身体性、もしくは世界に対する批判的思考をどのように回復するかという問題が確かにあります。それはたぶん古典的ハリウッド以降の映画の問題でもあり、僕自身の映画研究の発想の出発点でもあるわけです。
ただ、そういう問題系にうまく乗らないもう一つの発想というのが最近僕の中に出てきて、そこが一番僕にとっての問題なのです。簡単に言ってしまえば、そのイモビリティの映画が私自身はやっぱり好きだというだけのことなんですけれども、もしファントム・ライド的なモビリティの映画しかないとすれば、わたしはこんなに映画に入れ上げていないと思うわけです。やっぱりハワード・ホークスがいるから映画に入れ上げているのであっ
て、いわゆる、70年代以降の精神分析学理論のようなもので批判されてしまうような、大衆がある種のイリュージョンの中に閉じこめられてしまうと言われてしまうような、そういう普通の映画にどこか惹かれるものがあるんですね。他の芸術とは違って、ある種の大衆性を獲得しながらも、何か魅力のあるものとして迫ってくるような不思議な芸術として映画というものに私は興味がある。つまり観客のイモビリティというように括られて批判
されてしまうものを、むしろ肯定的にとらえ返すような契機はありえないだろうか、という発想があって、それが最初の問題との間でせめぎ合っているというのが、最近僕が悩んでいるところです。ちょっと僕は加藤さんの発言を強引に一般化しすぎているのかもしれません。しかし最近の研究者は、身体性とか観客のモビリティとか能動的反応ということを良いものとして担保に置くようなところがあるので、逆の発想はできないのだろうかと
いうふうに、いつももがいているという感じがあります。それが何なのかということは、ちょっとまだ言えません。
でも、もちろん加藤さんのような発想でも考えてはいるんですね。ファントム・ライドのことも関心を持って調べたし、リュミエールの映画を観客がどういうふうに能動的にとらえたかも。でも加藤さんにとっては『列車の到着』は能動ではないんですね。そこがちょっと不思議だったんですが。
加藤 なんでかと言うとですね、最近、木下直之さんという美術史家が『写真画論』(岩波書店)というのを書いていたことに気づきまして、その中で彼がリュミエールの『列車の到着』(1895年)の頃の作品(何百本もあるわけじゃないですか)を何十本か集中的に見て、ある抽象的な結論に至っていて、そこで彼が言うには、ムーヴィング・ピクチュアは先行するスティル・ピクチュア(写真)の影響をありありと受けている。なんとなれば、まず被写体が世界の風光明媚な風物、珍奇なもの、要するにトラベローグ的発想で選択されているからだと言うんです。スティル・キャメラを担いでいったように、ムーヴィング・ピクチュア・キャメラを担いでいって、世界中に撮影隊が派遣されていると言う。まあリュミエールのキャメラが軽かったせいですけどね。それはいいのですが、もう一つ、木下さんが言うには、なるほどシネマトグラフでは確かに被写体は動いているけれど、キャメラそれ自体は動いてないじゃないかと言うんですね。その点において映画は写真とちっとも変わっていないじゃないかと言うのです。しかしながら木下さんとその読者にはお気の毒ですが、確かに列車に乗ってエルサレムを出発するリュミエールのキャメラは動いているわけです。この手のファントム・ライド系の映画は当時、船や列車にキャメラを乗せて、いっぱい撮られているし、いまでも見ることができるわけです。つまりトラッキング・ショット、トラヴェリング・ショットです。木下さんみたいな絵画から出発した人には、そのトラヴェリング・ショットのすごさと意味が分かっていなかったんじゃないかなということで、先ほどああいう問題提起をしてみたんですけどね。
長谷 今のお話を聞きながら思い出したことがあります。直接はリンクしないんですけれども、結局僕は一見観客のイモビリティとしか見えない映画を見る経験、つまり普通のハワード・ホークスを見る経験のなかに、手を出すとかそういう明らかな能動的反応はないかもしれないですけれども、ある種のモビリティの経験があると考えているのです。たとえばモンタージュって要するに視点がワープすることだといつも言うわけですけれど、たとえば向かい合った男女にキャメラがぱっぱっぱっと切り返しているときに観客は、もちろん心理的にはある二人の恋愛の幻影の世界に入っているのに、身体のどこかで視点がワープして瞬時のうちに切り替わってしまうという経験をしているのではないか。そのことから身体的な刺激みたいなものを受けているのではないか。それはほとんど無意識下においてでしょうけれども。だからイモビリティの映画の中にも、ファントム・ライドとは違う形のモビリティみたいなものがあって、それが映画の魅力としてずっと実は続いていて、ただそれを直接的に表現することなく、非常に潜在的な形でやっていたのが古典的ハリウッド映画ではないかなと思います。そういう発想で行けば、モビリティというものを別の形で発見できるのではないかなというのが、わたしが最近考えていることです。
北野圭介 まずふたつのことを断っておきたいと思います。研究に関しては、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、ここ半年か一年くらいはフレデリック・ジェイムソンのことばかりやっているのですが、それはかなり特別といえば特別なので、置いておきたい。あともう一つは、今のお話にやっぱりつなげる形で何か言えればとは思うんですけれども、加藤さんのお話も長谷さんのお話も非常におもしろくて、それにここにいらっしゃる方々のお仕事もぱらぱらとしか読んでいないんですけどやはりとてもおもしろいんですね。ともかく皆さん、基本的に非常にいい意味で実証的で、過度にポエティックな美学的な話に回収してしまったり大袈裟な枠組みの中でというふうなところがなく、面白い仕方で映画を語る流れを作っていらっしゃる。僕が映画理論に非常に没頭しすぎているがゆえの、コンプレックスでがあって、実は話すことはない、皆さんのお仕事はもうすばらしいと言うしかない、という本音もあるわけです。
それで、あえて、というかたちで自分の日頃考えていることに繋げながらお話をさせていただくと、ということでご勘弁を、ということでよろしくお願いいたします。長谷さんのお話でいうと、古典的ハリウッド映画というものをどういうふうに考えるかといったときに、やっぱり、70年代『スクリーン』の連中がやっていたことを、今ウィスコンシン大学でデイヴィッド・ボードウェルやノエル・キャロルらがやっていることとは分けておいた方が良いと思っています。「古典的ハリウッド映画」というのは少なくともデイヴィッド・ボードウェル、あるいは認知派と称される人間の中では、パッシヴな観客の在り方を誘導するような映画では全然ない。簡単に言えば、観客の認知の活動を活性化するものであるというふうになるわけです。それとよく似たかたちで、しかし決定的に異なる意味で、コリン・マッケイヴは「古典的リアリスト映画」みたいな言い方をするわけですけれども、あるいはフランスではジャン=ルイ・コモリとかが「透明性」ということで、ハリウッドを中心とする映画を特徴づけるわけです。同じようにある特定の映画言語の一揃いという発想であるにもかかわらず、観客がある意味で馴致されてしまうような映画言語を具現したものとして、ハリウッド映画を考えていくわけです。この後者の流れを受けて、観客をイデオロギー的にネガティブなかたちで馴致してしまう、がゆえに乗り越えられていくべきハリウッド映画に対抗する映像実践を探すという方向が当然出てくる。それが初期映画研究のひとつの誕生原因ですよね。ラディカル美学の追求すべき方向を探すという意識のなか、すなわち、いわゆる60年代の実験映画が終息した後にラディカルなものをどこから呼び込めるかということで、初期映画研究に英米(欧米のといっていいかもしれない)の研究者向かうわけですよね。ノエル・バーチにしろトム・ガニングにしろそうなわけで、ノエル・バーチが初期映画に脱構築的なものを見るとか、トム・ガニングが「シネマ・オブ・アトラクション」、あれはもうまさしく60年代のアメリカの実験映画の投影的把握でしかないとは思うんですけれども、そのようなものを考え出し見出そうとするとき、現状のもしくはハリウッドの映画を美学的にそして政治的に克服するような可能性を初期映画の中に読み込もうとする欲望があったわけですよね。それとは別に、これは路線としてはボードウェルに近いんじゃないかと思いますが、チャールズ・マッサーなりクリスティン・トンプソンなりあるいはその他の初期映画研究者が、いわゆるあるパラダイムから別のパラダイムというか、ある映画のモードから別のモードへ、まあ1906・7年にするのか1917年くらいにするのかというのはいろいろ違いはあると思うんですけれども、ラディカルにガラっと変わったということはまあないであろうという前提がある。そうではなくて、多種多様な映画という装置あるいは映画という装置がつくり出す快楽というかですね、あるいは商品的な快楽というものがあって、それが大体1910年代あたりからだんだんとハリウッドを中心に、ある大きなストラクチュアに固まっていくんじゃないかなというふうな視点を採るわけですよね。
北野 現時点ではわたしとしては、細かくみていくということが映画研究ではやっぱり大切なんじゃないかなと思っていますので、「シネマ・オブ・アトラクションズ」とかあるいは脱構築的なものが初期映画にはあったというような期待の地平のなかの研究ではなくて、身体性を非常に強調したものがあったり、とにかくもいろんなものがあったというふうな形で初期映画を読みほどいていくということが非常に大切なんじゃないかと考えているのですが。しかし、だからといって、それが映画の今あるべき、あるいは向かって行くべき美学的可能性なのかどうかということに関しては、ちょっと括弧に入れたいかなとは思うんですけれども。とにかく、そういうふうな感じがしますね。あと、モビリティの話が出てきて、いきなりびっくりしてしまったんですが、全然考えていなかったもので。中村(秀之)さんにつなげる形で、僕の関心を言わせていただくと、今回「映像学」(日本映像学会誌)に書いたものがあるのですが、それは結局、60年代にメッツから『スクリーン』に至る流れでリアリズムのとらえ方が全然変わってきているというのが、まあ皆さんご承知のことだと思うんですけれども、その中で視覚的なものと言語的なものというのが、言語と視覚というのはある緊張関係のもとに対立し合ってきたところがあるはずなのに、やっぱり構造主義的・ポスト構造主義的な記号論的な発想を採るとですね、いわゆる映画がテクスト論になってしまうわけで、視覚経験が余りにもテクスト概念帝国主義で還元されて捉えられてきたのではないか、という問題意識もあって書かせていただいたところがあります。言語中心主義的発想をとったとしても、たとえば声の優位で書字言語がヘゲモニーをとってきたとかいう単純な話ではなくて、声と書字言語がですね、いろいろに対立し合いながら絡み合ってきた流れもあるわけですから。まあそれを括弧に入れるとしても、少なくとも視覚的なものを言語的なアナロジーを引いて一気に論じてしまえると裁断してしまう方向ではない研究の視座を確保すべきだと思うんですが。それをやってしまうと、たとえば初期映画にハリウッド映画の言語的物語性の優位を越えるための、初期映画のなんらかの視覚性の優位とかいうふうな単純な発想になってしまうんで、そうではなくて、たとえば、まだ言語と視覚というのが緊張関係を取り合いつつある構造を変え展開してきたのであって、それが初期映画のハリウッド映画に流れてきているというふうに、とらえた方がいいのではないかと思っているのですけれども。そこをまずおさえておきたいですよね。
その上でですが、その視覚に関して、中村さんがなさったお仕事をちらちらと読んでいたのですが、そこに身体性をもっと呼び込んで映画に関わる視覚的快楽の概念を広げようとなさっているところがあって。僕はこれって無理なんじゃないのと一瞬思ったんですけれども、今の加藤さんのお話とか、まあ改めて考えると、それもあるのかなとなんとなく思い始めたりしてはいます。まとめて言うと、古典的ハリウッド映画をどう考えるのかと対応する形で、初期映画をどう考えるのかというのはずっと今まであったわけで、そこをどういうふうに整理するのかということ。で、その一つの切り口となるのが、ヴィジョンとリングウィスティックなものの緊張関係みたいなものをどういうふうに改めて枠組みし直せるかということだと思うんです。そこのところをかなり周到に考えておかないと、モビリティや身体性の話も、期待の地平のなかでかなり還元主義的な話になってしまうんじゃないかというのが僕の考え方ですね。
加藤 先ほどの長谷さんの「ファントム・ライド系だけじゃなくて、やっぱりハワード・ホークスの映画があるから」という話から、初期映画と古典的ハリウッド映画という形の視覚的なものと言語的なものとのという話が、ここまでうまくつながってきていますけれども、次に中村さんの方から。
中村秀之 我々はいま映画について語り始めているわけですが、映画について語るというある種の制度とは言わなくても、もうちょっと漠然とした磁場みたいなものがあるとして、自分がなぜそういう磁場の中に入ってきてしまったのかということを考えるんです。そのことに関連して二つ、最初のとっかかりとしてお話ししようかなと。
まず、映画について語るということをわたし自身長い間回避してきたのですが、なぜいま映画を論じようとしているかというと、ベンヤミンの「複製技術時代の芸術作品」という論文について、これは映画を対象にして論じているものなんだという極めて単純な主張をしたいがために、論文を二本も書いてしまったということがあるんですね。ご存じのように、ベンヤミンのテクストは長い間「メディア論」の古典として扱われてきました。しかし、そこで扱われている対象がまさに映画であるという点については、必ずしも充分に考察されてこなかった。少なくとも日本では、あの論文を、映画史の知識や映画学の知見を踏まえてまともに受けとめようという流れはほとんどなかったといっても過言ではない。実際に読んでみれば、明らかに映画についていろいろな角度から論じている文章であるということは明白なはずであるにも関わらず、なぜ映画が回避されてきたのかという疑問が生じたんです。言説の対象として映画が回避される、特殊な領域としての映画学とか映画研究とかいった歴史は日本でももちろんあるわけですけれども、そこを一歩出てしまうと映画がなぜか回避されてしまう。その対象として、たとえば社会学にしても文化批評的なものにしても、ごく一部の20年代のソヴィエト・モンタージュ理論を始めとして、芸術映画的なものが世界映画史の中からフランス映画のある時期のもの、詩的レアリスムとかヌーヴェルヴァーグ、あるいはイタリアのネオリアリスムであるといった形で拾われてくるけれども、「映画」という対象自体はなぜか回避されてしまってきたと。で、そのことに対する驚きと不満というのがあって、いや実はベンヤミンは「映画」を論じているじゃないかということを強調したかったわけですね。
ですから出発点として、わたしは映画のフィルムテクスト自体ではなくて、むしろそのディスコースの方、映画を巡る言説というものを対象にしてその仕事を始めました。最近書き上げたばかりの論文もフィルム・ノワールを扱っているんですが、これもフィルム・ノワールの様式論であるとか、フィルム・ノワールのテクストの中に見られる様々な主題系を分析するというよりも、「フィルム・ノワール」という概念あるいは記号というものがどういった言説編成の中で浮上してきたか、構築されてきたかということを問題にしているものなんです(「フィルム・ノワール/ディスクール・ノワール」、吉見俊哉編『メディア・スタディーズ』所収)。まあ、そういった関心を持って仕事をしてきたということがまずあります。ですから、映画を語るということがある文化的な営みとしてどういう意味を持っているのかということですね。そこで少なくとも日本の場合には、映画がその対象としては軽んじられてきたといった文化史的なコンテクストを、一応社会学に身を置いているものとしては考える意味もあるし、やっていこうと今も思いつつあるところです。
中村 しかし他方で、個人的には映画を語るということ、自分自身が映画のフィルムについて何かを語ろうとする場合にはものすごく困難を感じる。その困難というのは何かといえば、最初の加藤さんの問題提起とどこかでつながっていくことを期待しているんですけれども、フィルム体験そのものをどう語るかという、フィルム体験自体をひとたび問題にしてしまったときに絶句せざるをえないようなものが少なくとも自分の中にはあります。先ほど、映画を語ることを長く回避してきたと言うのは、映画を見ることは好きで子供の頃からみているにもかかわらず、それを語るということをどこかで抑圧してきた。その映画を語るというのがどこか怖いというか、それを語ってしまうことでフィルム体験の何かが欠落してしまうというか、それを縮減してしまうような、そういったことをむしろ恐れていたのではないかと考えているんですね。事実わたしはスクリーンに何を見ているかというと、全然物語なんかは理解しないで見ているわけで、これはたとえば蓮實重彦的なものの影響などではなく一貫してそうなんです。だからたとえばトム・ガニングが「シネマ・オブ・アトラクションズ」というようなことを言っていて、これはああいう形で理論的あるいは歴史的に問題提起をしてくれると非常にありがたいんですが、そこで語られていることは自分にとっては当たり前のことだという思いもある。映画はイメージを見せるというところにそのポテンシャル、可能性があるということを冒頭のほうで言ってますよね。『鉄路の白薔薇』に興奮したフェルナ・レジェの文章を引き合いに出してますが、そのなかでレジェの"making
images seen"という表現を引用している。しかし、これは自明ではないかと、事実スクリーン上に映る様々な光であるとか動きといったものに対して目を見張る、絶句しているというそういう体験がわたしにとって映画体験なんです。しかしそれをいったん語るということになると様々な戦略とか装置といったものの助けを必要とする。すると、これはどこかで自分がいったん映画を語る磁場に身を置いてしまったときには、既に存在している映画についての語り方といったものに身を寄せていくしかない。まあこれは映画に限らず経験一般についてもちろん言えることかもしれないんですけれども、映画に関しては特にそれを感じる。あるいはむしろ映画というものは語らずに済ませてしまえるものである、実は。そういった磁場に身を置かないで、語らなければ語らないで、見た途端にそれを忘れてしまうといったことを普通の観客というのはむしろやっているのではないだろうか。そういったことまで含めて、それを思考の対象にするとどうなるんであろうかという、全然答えは出ていないんですが、そういったことを考えようとしているんですね。
もう一つ、あんまり個人的なことを言うのもなんですが、議論のきっかけになればと思ってあえて話してみます。昨日、加藤さんのお世話でフィルムセンターで日本映画を何本か見せていただいたんですが、木村荘十二の『からゆきさん』という映画、1937年の作品ですが、その中で一カ所、どちらかと言えば取るに足らないといわば言えるかもしれない場面なんですけれども、入江たか子の自宅に彼女の子供の学校の先生が訪ねてくる場面なんですね。そこで客をもてなすときに、あれは何なんでしょう、角砂糖をお湯で溶かして出す。で、注いでるうちにだんだん色が濃くなってくるのでただのお湯ではなくて紅茶か何かなのかな、などと不思議に思ってみていたんですが、その時に角砂糖がお湯で溶けていくところがですね、光が当たって微妙な透明感というか半透明感というか、非常に美しく見えるわけです。あれを見たときに、物語の流れとは関係ないんですけれども、ただ砂糖がお湯に溶けていくというところを見せてくれる映画というものは、やはり素晴らしいというような形で見てしまう(笑)。実は、たとえばガニングが「シネマ・オブ・アトラクションズ」の中で、あれは映画史のいわば時期区分のための概念装置として「アトラクション」というものがあるかのように読みがちで、実際にそういうふうに機能してもいるんですけれども、ガニング自身、アトラクション的な要素というものがその後の古典的ハリウッド映画にも消えたわけではなくて引き継がれていて、たとえばミュージカルのようなジャンルには歴然としてあるんだということを言ってるんですね。ですから、そういう形で古典的な映画の中にもいくらでもアトラクション的要素は遍在していると。で、自分は実際にそういうものを見てきたんだということを考えれば、そういった形で理論的あるいは歴史的な概念装置で映画というものを分節化して語るということは必要でもあるのだとは思うんですけれども、そういった枠組みに収まりきらない、もうちょっと生の映画体験みたいなものを改めて語る可能性というものがないのかなというようなことを今考えているところです。まだそれは全然形になっていないし答えも明確なものはないんですが、問題意識をとりあえず、ということでしたので。
斉藤綾子 今の皆さんの話をいろいろ聞いていて、やっぱりこれはわたしが映画を教えるときに自分が映画の定義のようなことから始めようとして、どうしてもいつもぶち当たってしまう問題というのがここに出ているんじゃないかなと思いました。それはまず知覚体験としての映画というのと、それから物語装置としての映画という映画自身が持っている二つの要素の存在、それを矛盾と取るか対立するものと取るか、それを統合したものとして映画が存在しているという意味に置いて一種の特殊な一つの形式であると。もしかしたら映画というのは他のジャンルに比べて一つの形式という言い方ができないんじゃないかなと、映画のフォルムという形でまとめることができないものなのかなという問題意識が一つあります。最初に加藤さんがお話しになったモビリティとかイモビリティの問題というのは、やっぱり映画の知覚体験にある程度直結した問題であると思います。でもそうすると、そこから出てくる問題というのは、今はほとんど語られることがなくなったと思うんですが、映画の存在論的つまりオントロジー的なところに一種関わってくるものなのかなと思うんですね。同じように、映画の中においても映画の存在論的なものと、中村さんと長谷さんがおっしゃったような映画を語る、言説を通じて映画というものに近づいていく、あるいは映画そのものというのは一体何なのかという形で近づいていくという、今映画理論自体を考えると存在論から始まったものが言説論に動いているという二つの流れがここにも出てしまっているのかなという意識です。
こう考えたときに、先ほど北野さんが視覚と言語というふうにお話になったと思うんですが、もう一つの問題の軸というのはやっぱり物語に立ち戻るのではないか。つまり視覚があって言語があって、言語というのはもしかしたら視覚と物語の中間点に位置するものですね。言語というのをまずどういうふうに考えるのかというのが出てきてしまうと思うんですけれども、そこでもう一つ映画の存在論と言説みたいなものを考えたときに中間点的に、それが映画を考えるときに認識論的に考えるのか現象論的に考えるのかというのが、最近その映画理論という地点からはあります。そしてそれの中にどういう形で観客の問題、つまり受け手がいるということをどういうふうに取り入れたらいいのかなということが問題としてあるような気がするんですね。
初期映画というのが物語を語るというふうに出てきたごく最初の時というのは、日本では弁士という存在がいたわけですけれども、たとえばメリエスの『月世界旅行』ではメリエスのコメントが残っているということで、何が元になったのかというのはいろんな別のジャンル、小説があり演劇がありという中において映画が入ってきて言語的な補佐というものが介在してしまったというときに、そこから一つのハリウッド古典映画というのをナレーションとして考えるのか特殊な知覚体験、認識体験として考えるのかというのが、それをきれいに体系づけて考えようとするのが良いのかどうかは別として、混在しているんじゃないかなという気がするんですね。
斉藤 最近話をすると、いつもこの話になっちゃうんですが、映画と情動論ということについて考えたんです。先ほどたとえば長谷さんがおっしゃったように、ハワード・ホークスの映画を楽しむということ、それが身体表現にならなくても何らかの形でモビリティになるということと、あともう一つは中村さんがおっしゃったようなある一つの映像なりイメージなりが一作品全体を、映画を個人的体験として成立させてしまうという不思議な映画体験。それはもしかするとバルトが初期の物語学から最後の「明るい部屋」に移った動きでもそうですが、映画というものを考えたときに誰もがどうしてもその両極を揺れ動いてしまうのではないかと。今中村さんがおっしゃったのはバルトの写真論のプンクトゥムに非常に似た部分というのがあって、その引っ掛かりみたいなもの。それは映画と関わっているのか、ある種経験との問題になってしまうんですが個人と関わっているのか、そして古典映画における物語を消費するという大衆というのが、それをエンターテインメント・娯楽として享受するという、その辺が一体どういうふうになっているのかなと悩むわけです。
もちろん全然解決の着かないことだとは思うんですが、いろいろな流れがあって70年代にイデオロギー論とか政治論といった文脈があって、映画を教えるということになったときに、映画を一つの個人的体験として見て欲しいという部分と、テクスト論と考えるかどうかは別として作品自体が持っているイデオロギーとか政治的とかいった文脈とどう結びつけていくか。それはもしかしたら映画論というものと映画言説というものとの乖離というんでしょうか、つまりどうやったら映画そのものについて語るということと映画について語る言説というのが遭遇するようになるのかなと。わたしとしてはなんらかの形で、受動性とか能動性とかいう枠組みではなくて、感情と身体をつなげるような映画的体験というものがそこに考えられるのではないかなと考えます。
アトラクションという言葉が出ていたんですけれども、論文を書くに当たって、古典映画論のなかで感情あるいは情動というものがどういう形で論じられてきているのかというのをアルンハイムからずっと調べたんですけれども、おもしろいのはエイゼンシュテインの中で、彼のアトラクションで、彼は後期になって自分でパトスの映画というのを言い出したのですが、アトラクションからパトスに移る途中で映画を、英訳なんですけれどもアフェクティブ・フォーム、感情的な形式として考えているんですね。パトス論を展開していたときに、30年代前半の時点でもうすでにエイゼンシュテインが演劇の時にやっていたアトラクションと今彼がつくっているパトスの映画というのは絶対的な乖離があるのではないかという批判をシクロフスキーにされて、彼自身がポストスクリプトという形で基本的には同じことなんだという反駁をしているんですね。ですからその辺で映画理論というものを考えるときに感情、わたしはやっぱり情動と言うのが一番ぴったり来るのですが、その点に関して映画理論というのは言語を持っていないのではないかなという感じが非常にするんですね。それが理論化できるかどうかというのは全く別問題なんですけれども、いろんな言説のはざまで体験という言葉を使ってしまうと、最終的に個人の受容だけに帰属してしまうような気がして、そこのテクストとの関係あるいは歴史的主体としての受容している個人の問題がうまく出てこない。まあ情動論というのを使ったとしてそれが出てくるかどうかというのはまた分からないんですけれども、その辺の感情を、皆さんのお話を聞きながら自分の考えている問題というのを発したんですけれども。自分が何か映画について書くという作業と、それを教えるという作業になったときに、それが必ず正しいと思っているわけではないんですが、映画の持っている様々な側面を紹介しなくてはならないだとか、わたしが教えるのはたとえばフェミニスト的な云々というのを言われてやることが多いんですけれども、自分自身が受容しているときの問題と文脈としてとられたイデオロギー的な政治的な問題があるにも関わらず、先ほどの長谷さんではないですが、享受してしまう自分、そこをどういうふうに考えるのかなと。最初の問題で言うと、存在論的なものなのか言説論的なものなのか認識なのか現象論なのか分からないですけれども、その辺が得体の知れない映画というものを巡っていろいろあって収まりが良くなくて。まあただ収まりが良い状態を見つけてはいけないんだろうという良心的な呵責もあるんですけれども、それは道徳みたいになってしまって良くないなとは思うんですが、その辺のところが非常にわたし個人の問題としてあります。次ページ→