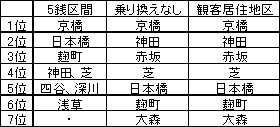| CineMagaziNet! Articles | |
|---|---|
| ��̉��č�����f��ɂ��Ă̊o�� �\�w�f�拳���x���ɂ݂�i�g�R�i�f�ʋ@�j��CIE�f��̎�e�ɂ��� | �݂�Ȃʼnf������ɍs�����I �\�\�A�����J�ɂ�����f��ق̕����j |
���{�f�拻�s�j����
�\�\1930�N��ɂ�����Z�p�v�V����ыߑ㉻�ƃt�B�����E�v���[���e�[�V����
�����čO
�@�͂��߂�
�{�e��1930�N��ɂ�������{�̉f�拻�s�̎��Ԃ��T�ς��鎎�݂ł���B�����̗h�Պ��Ƒ吳�̐��������o�āA���鍂�݂ɒB�������{�f�悪�g�[�L�[�Ƃ����Z�p�v�V�ɒ��ʂ��A�\�����v�𔗂�ꂽ1930�N��́A�^�Ɏ��͂���ē������T�C�����g���ɐςݏd�˂����̂��J�Ԃ����A�����ɏG��ݏo�����u��������v�ł������B���̍��͂܂��A���������������l�X���₢������������搉̂��Ă�������ŁA�R�������܂��܂Ȑ�[���J���A�틵�ɉ����ăi�V���i���Y�����V�g���Ă����Ȃ��A�f��̐����I�ȗ��p���l���F�߂��A�f��j���V���Ȃ�i�K�ɓ����������Ƃ������悤�B���������̂Ȃ��ŁA1930�N��Ƃ������{�f��́u��������v�ɁA���X�̉f���i���s��������Ƃ��Ẳf��ق̗l�Ԃ��A�̌n�I�ɍl�@���鎎�݂͂���܂łȂ���Ă��Ȃ������B�{�e�ł́A1930�N��̉f��ƊE����f��G���𒆐S�ɁA�e�퓝�v���l��f�拻�s�Ɋւ���L�������A���{�̉f�拻�s�̏��L������ŋq�ϓI�ɑ����邱�Ƃ�ڎw���B�����ł͉f��قƂ����~�f�B�A����Ԃ̗l�Ԃɂ��܂��܂Ȋp�x���猟�������킦�邱�ƂŁA���ꂪ�f��̋Z�p�v�V����{�̋ߑ㉻�v���Z�X�ƘA�ւ��Ȃ���@�\���Ă������Ƃ����炩�ɂȂ�ł��낤�B���@�Ƃ��Ă͂܂��A�g�[�L�[�Ƃ����S���E�I�ȉf��̋Z�p�v�V�ɂ���āA�f������҂�y�t�ȂNj����s�`�Ԃ��`�����Ă������݂��p�������A�f�拻�s�`�Ԃ��ω����Ă��������Ƃ��m�F����B�����Ă��̎����A�����ɉ��K�������߂͂��߂��s�s�̉f��ϋq�̗~�]���f��ق̓����\����ω������A�܂����傷��f��l�������e����ׂ���f�挀��̌��݂����������B�����ď��i�Ƃ��Ẳf��̉��l�����܂�A�f��ق͑S���I�ɐ�`������J��L�����B����Ɍ�ʋ@�ւƉf��ق̖��ڂȊւ�荇���́A���s�҂ɂƂ��Ċʼn߂ł��Ȃ����ƂȂ����B���������������m�F���邱�ƂŁA1930�N��A���{�̉f�拻�s�̎��Ԃ�������B
1.
1. 1930�N��̉f�拻�s
1895�N�Ƀp���ŏ��߂ėL����ʌ��J��f���ꂽ�����~�G�[���Z��ɂ��V�l�}�g�O���t�i�X�N���[���Ǝˌ^�̎B�e�@���f�ʋ@�j�́A2�N�����������ē��{�ł���f����͂��߂邪�A�����͉��|�����ɂĊe�퉉�|�̖��ԂȂǂɏ�f�������̂ł������B����������̗v���ɂ���āA�������������̉��|�����͏�݉f��فi�Ȍ�A��݊فj�ɈƑւ����A�f�撆�S�̃v���O������g�ނ悤�ɂȂ�B���{�ŏ��̏�݊ق́A1903�i����36�j�N�A�u�d�C�d�|�̊��ނ�AX�����̎����������āA�d�C�̒m���y���T�X�A�������Ƃ��ē��ꗿ������Ă����v�̓d�C�قł���[1][1]�B
21���I���ނ��������݂ł����̋敪���܂������Ȃ��Ƃ͂����Ȃ����A��O�͏�݊ق̂Ȃ��ł����{�f����فA�O���f����فA�����ĕ��݊قƂ�����r�I���m�ȋ敪���������B�܂��ȉ��̐}1�����Ē��������B
�} 1�@
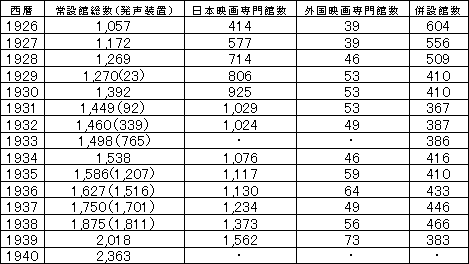
�}1��1930�N��ɂ�����S���̊e���ِ݊��̕ϑJ��H�������̂ł���[2][2]�B���̓��v�ɂ��ƁA�S���̏�ّ݊�����1920�N��㔼����30�N���ʂ��Ĉ�т��đ����𑱂��Ă��邪�A�Ȃ��ł����{�f����ِ��ɑ啝�ȑ����X�����݂���B���̈���ŊO���f����ِ��ɂ͂��܂�ϓ����Ȃ��A���ِ݊��͌����X���ɂ���B�e��f��ِ��̕ϑJ���߂���A���������X���ɂ���āA���������Ă���̂��B1930�N�ɔ������ꂽ�����\�I�ȉf��ƊE���͎��̂悤�ɕ��͂��Ă���B
���䢈��N���A���{�f��̏�݊قɉ�������i�U��͖ڊo�����A�Q���O�����̐l�C��D�ЁA�����ŊO��������݊ق𑫉��ɍ~���A���{������ɏ�f�����݊ق̐��͌��𒀂ӂɏ]���đ������鐖�����������B�������O�������f�悪�Љ���ɋy������̌X���͉v�X�������Ȃ��ė����i�����͈��p�҂ɂ��A�ȉ����j[3][3]�B
�����f�����f����₤�ɂȂ��Ă����A�]���̊ϋq���m���K���ɑ����鉽�\�����̏����O��ӏ܉Ƃ��c���āA�ꕔ�̊O��t�@�����ߗ��ڂɑ䓪���ė������{�f��ɑ���₤�ɂȂ����͓̂��L�ɒl���鎖���ł���[4][4]�B
�ȏ�ɕ]�����悤�ɁA���{�f����ِ��̑����X���́A���{�f��̖��i�Ƃ����v�f�ɉ����A�O�������i�g�[�L�[�j�f�悪�A������͂��߂�1920�N��㔼����n�܂�̂ł���B�܂����{�f��̖��i���u�O��������݊ق𑫉��ɍ~���v���Ƃ���邪�A���ۉe����ւ����̂͊O���f����قł͂Ȃ������B�܂�g�[�L�[���̖��ɍ��E����Ȃ��ꕔ�̍������O���f��t�@���w�i�u�m���K���ɑ����鉽�\�����̏����O��ӏ܉Ɓv�j�����݂����Ƃ���A�O���f����ِ��͂���قǑ傫���ϓ����Ȃ��B���̈���A�����ʂ�q�w����肵�Ȃ����݊قł́A���{�f��ƊO���f��̋��s���тɖ��m�ȗD�����A���̌��ʁA���̎����ɑ����̕��݊ق����{�f����قɈƑւ������̂ł͂Ȃ����B����͂��܂������̈���o�Ă͂��Ȃ����A���{�f��̖��i�ƊO���g�[�L�[�f��̏�f�J�n���d�Ȃ������̎����A�u�f��t�@���v�̚n�D�����m�ɕʂ�͂��߂����Ƃ��l�����킹��ƁA�Ó��ł��낤�B
�f��ق͍�i�Ƃ����\�t�g���ϋq�ɒ���n�[�h�ł���Ȃ���A��ɂ��̃\�t�g�����i�Ǝ�e����ϋq�̓��Ԃɓ��h��������s����ȑ��݂ł��������Ƃ͂܂������Ȃ��B�܂��|���āA���̎����̉f��ϋq���A�g�[�L�[�Ƃ����V�Z�p�����ɔ������s�`�Ԃ̕ω��ɖ|�M��������ł͂Ȃ��A�e���݊ق̋��s���j��ς��Ă��܂��قNj����̂������̂ł���B
2.
2. �g�[�L�[�f��̉e��
�ł́A��������̓g�[�L�[�f�悪�]���̉f�拻�s���x�ɗ^�����e���������������B���{���̊O���f��g�[�L�[���s��1929�N5��9���A�V�h������قƐd�C�قɂ�����A�u���[���B�[�g�[���v�������f��[5][5]�w�i�R�x�i�}���Z���E�V�����@�[�ēA1929�j�ƃn���C�A���E�_���X�̒Z�҉f��w��C�̉S�x�̏�f�ł���B���̌�A�e�Ќn��f��ق������Ɖ��nj^�̔������u���w������Ɏ���A���̔N�́u�������ɓ����Ă���̓g�[�L�[�̒������X�ڐ��܂����A���S�ɊO�拻�s�E�����[�h���A�������u��ݔ������݊ق̐����Q���������A���N���ɂ͑S���œ�\�O�ق̑����ɏ�����v[6][6]�Ƃ����B���̌�A�������u��ݔ������݊ق̐��͌������Ă����A1938�N�ɂ͑S���̏�݊�1,875�ْ�1,811�ق܂ł������f�ʋ@��L����悤�ɂȂ�i�}1�j�B
�Ƃ͂����A�g�[�L�[��f�����ɂ͂��̐�����߂����Ċ����ɋc�_���J��Ԃ���Ă����悤�ł���B�Ȃ��ł��g�[�L�[�ے�_�҂̐��́A���̑������������Ǝv������́i�u�����ɋt�߂肷��v�u�ꎞ�I���s�v�u�ꕔ�̉Ȋw�҂Ƌ��s�҂ɂ���ėv�����ꂽ���́v�j�₻�̐����ɂ���đ��X�ɉ���������p�̖�����ł��邪[7][7]�A������ɂ���f��̃g�[�L�[�����͏]���̋��s�`�Ԃɑ���ȉe�����y�ڂ����ƂɂȂ�B�����ł́A���̎����̉f�拻�s���`�����Ă����d�v�Ȑ��x�Ƃ��āA�f������ҁi�َm�j�Ɓu�X�e�[�W�E�v���[���e�[�V�����v�ɁA���̉e�����m�F���邱�Ƃɂ���B
2.1.
2.1.
������
�����҂̑��݂́A���̐�����߂����đ吳���i1912�|26�N�j���炳�܂��܂Ɍ��y����Ă������A�����ł��A���{�f�挤���҂ɂ������҂̍ĕ]���͐���ł��邪�A�{�����Ő����҂̖������グ��̂́A�Ȃɂ����ނ炪���̎����̉f�拻�s���`������s���ȑ��݂ł���A���x�ł������Ƃ��������ɂ����̂ł���B���̐����҂Ɋւ��Ă͂ӂ��̖�肪�����オ��B
�܂��M�҂������ŗp����u�����ҁv�Ƃ����ď̂������A�d�v�Ȗ���s��ł���B�Ȃ��{�_�ł́u�����ҁv��p����̂��B�����1930�N��̉f��Ɋւ��錾����ň�ʂɗp�����Ă���ď̂�����ł���B���̌ď̂Ɋւ��ẮA���{�f�挤���Ƃ̃A�[�����E�W�F���[���ȉ��̂悤�ɕ��͂���B
���������u�����ҁv�Ƃ́u�X�N���[���̉��ɗ����A�����ŕ���ו��̌���o��l���̉�b�̕⑫�������v�u�َm�i���فj�v�Ƃ��������̌ď̂��A1910�N��㔼����̏��f�挀�^��[8][8]���͂��߉f�挾���E�ɂ�������v�_�҂����ɂ���ĉ��߂�ꂽ�ď̂ł���A�u�����ʐ^�v���Ӑ}�I�Ɂu�f��v�Ə̂����悤�ɂȂ鎞���Ƃقڏd�Ȃ�[9][9]�B�܂�f��̎��������咣������v�_�҂������A�u�ߏ�Ȍ���ŊϏO���͂�͂炳����v�u�َm�v����A���̌��������グ�A�u�f�悪���̌ŗL�̈Ӗ���`�B����ۂ̎菕�����`���Ƃ���v�u�����ҁv�ւƍ~�i������ߒ����W�F���[�͑e�����邪�A�����ɁA�����ɂَ͕m�ɈˑR�����������������Ă����u�Љ�I�ɗ�����Q�O�v�ɑ���A���v�_�҂����̌y�̓I�Ӑ}�����݂����Ǝ咣����[10][10]�B���̌ď̂̕ω��ɂ݂��鎖���A�����̉f�拻�s��ɂ�����e�ϋq�̈ʒu�W�ƁA���́u���فi�f�B�X�^���N�V�I���j�v�����Ȃ��炸���炩�ɂȂ邵�A�܂������ɐ����҂̑��݂̑傫�����Ċm�F�ł���̂ł���B
����ł͂Ȃ��A�����҂͉f�拻�s�ɂ����Ă���قǑ傫�ȑ��݂ɂȂ肦���̂��B���̐��x�����{�œƎ������W�𐋂����o�܂������ЂƂ̖��ɂȂ�B�����҂ɑ������鑶�݂͓��{�����̎��ۂł͂Ȃ��B�Ⴆ�A�����J�ł́A�ulecturer�i����ҁj�v��1910�N��O��܂ő��݂����B�W�F���[�͉f��w�҃g���E�K�j���O�Ɖf��j�ƃ~���A���E�n���Z���̘_�������p���A�u����ҁv��1908�N�O��ɂ͒����K���ϋq�ւ̐S���`�ʂƕ���I�ו��̏����s���A�����A�����J�f��Ɂi�����K���ϋq����荞�ނ��߂́j�d�v�Ȗ������ʂ��������Ƃ𖾂炩�ɂ���B���������ǂ��̒���A�f��Ɖ���҂Ƃ́u��A�����v����ނ�͕s�v�Ƃ���A����Ɏp�������Ă������̂ł���[11][11]�B�Ƃ��낪���{�ł�1930�N��̔��Ɏ���܂ŁA�����҂͑��݂��Â����B�f��]�_�Ǝl���c���F�͓��{�ɂ�����u�َm�v�̑��݁A�������R��I�m�ɂ܂Ƃ߂Ă���[12][12]�B
�����������{�ł́A�u�����ʐ^���l�`��ڗ��̂悤�ɉf���i�`�ԁj�Ɖ����̕�����O��Ƃ�����O�����̉�������Ɏe���ꂽ�Ƃ����o�܂��v����A�f���Ɖ��������Ȃ炸���������̂��̂ł���K�v�͂Ȃ������B�܂��`���I�Ȍ��̌|�����������߂ɁA�u�َm�̂悤�ȕ��G�ɂ��Đ������ꂽ�p�t�H�[�}���X���\�ƂȂ�A�܂�������x�����Ă�܂ʑ�O�̚n�D�������v���ꂽ�Ƃ���l���c�́A����Ɂu���݂̒n�_�v����ȉ��̂悤�ɏq�ׂ�B
�َm�͒P���ɐ�s���đ��݂���t�B�������]���I�ɉ������l���ł͂Ȃ��A�ނ���t�B������f�ނ̂ЂƂƂ��Ĉ����p�t�H�[�}���X�̎�̂ł������B�ނ͊ϋq�̉f��̌������݂ɑ��邱�Ƃ��ł������肩�A����T�C�h�ɑ��Ă����̔������������A���{�f����A�����̎��Ȋ����������Ă悵�Ƃ���n���E�b�h�f��Ƃ͈قȂ��������ւƔ��W������̂Ɍ����������B�����~�G�[���ȗ��A�f�悪���ׂ��炭�\�ۂ̎����Ŏ~�܂��Ă����Ƃ��A�B����{�������\�ۂ��z�������O�̎����ɓ��B�ł��Ă����Ƃ���A����͂ЂƂ��ɕَm�������Ă̂��Ƃł���[13][13]�B
�܂���{�́u�َm�v�Ƃ͒P�Ȃ�f��̐����҂ł͂Ȃ��A���{�̓`�����ۏ���p�t�H�[�}�[�ł���A�f�悪�B�e��ҏW�̋Z�@�œƎ��́u�����v��҂ݏo���Ă��A�܂������̉f��G����ǂݒ^�������v�_�҂����̑��݂�ے肵�悤�Ƃ��A���{�̑命���̉f��ϋq�ɂ͎x������Â��鑶�݂Ȃ̂ł������B�����҂ɑ���W�F���[�Ǝl���c�̌���I���_�́A�����҂̑��݂������̉f��ϋq�ԂɁu���فi�f�B�X�^���N�V�I���j�v�������炵�A�܂����{�f��̎����̂��̂�Ǝ��ɍ��߂��Ƃ����d�v���𖾂炩�ɂ���B�������A����ł��Ȃ������҂��������͂��߂�̂��A1930�N��Ȃ̂ł���B�ȉ��̐}2�����Ē��������B
�} 2�@
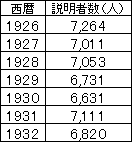
�}2��1926�N����1930�N�㏉���ɂ����āA�S���̐����Ґ��̐��ڂ����������̂ł���B���̌����X��[14][14]�̂Ȃ��A1931�N�Ɉꎞ�I�ȑ����X����������B���̌X��������f��ƊE���͈ȉ��̂悤�ɕ��͂���B
�I�[���E�g�[�L�[���̑䎌���`���v���J���v���̏�ɁA�O������ɂ��炭���y�I�ɌP������������ʑ�O�������f������}���锤���Ȃ��B�����Ă��̋������A�ꎞ�͔����f��ׂ̈߂ɂ��̑��݂���Ԃ܂ꂽ�����҂��A�킸���ɋ~���Ă�錻��͊m���ɔ���Ȏ��ۂł���[15][15]
�������Ƀg�[�L�[���ɂ���ĉf��j�͐V���Ȓi�K���}�����Ƃ����悤���A����܂Ŗ����f��ɐe����ł����f��ϋq�̂��ׂĂ����̋Z�p�v�V����Ƃ͍l�����Ȃ��B�Ƃ��ɓo��l�����O�������O���f�悪�{�i�I�Ƀg�[�L�[��f����n�߂�1930�N���ɂ́A�����҂��ėv�����ꂽ�̂ł���A���v���ʂ͂��̒��˕Ԃ�Ƃ��ė����ł���B
�����Ă܂��A�u�َm���A�L�Q�ȃ��b�Z�[�W���������邱�ƁA�������͌��ݓI�ȃ��b�Z�[�W��t�����邱�ƂŁA�e�L�X�g��ς��v�邱�Ƃɂ���āA�u���I�ȊϏO�����グ��v����҂Ƃ��Ă̖��������Ƃ��َm�������҂Ɋ��҂������Ƃ��W�F���[���q��[16][16]�A�u���{�ł͂��鎞������َm�͖Ƌ����ƂȂ�A�����ɒ��F�̈����v�z���P�����邱�Ƃ�v�������悤�ɂȂ����v�Ǝl���c���q�ׂ�悤��[17][17]�A���{�����B���ς�u�������A���{�l��ʂ̖ڂɌ����Ȃ��Ƃ���ŐN���푈���J�n�����A�܂���1931�N�ɐ����Ґ��̈ꎞ�I���ˏオ�肪�����邱�Ƃ͒P�Ȃ���R�Ƃ��Ċʼn߂ł��Ȃ����Ƃ������ƂɂȂ낤�B�������A���҂̐����A��1932�N���猸���̈�r�����ǂ�����Ґ������������̂ł͂Ȃ��B
���āA���̌�A�����Ґ��͍Ăь����ɓ]���A1930�N�㖖�ɂ͑S����388�l�A�����ł͂킸��5�l�������݂��Ȃ��B�������A���̎��_�ł��A�k�C����75�l�A�F�{��54�l���݂����Ƃ����L�^[18][18]����A�n���ł͂܂��f��ق̃g�[�L�[�ݔ��̕s�����炩�A�����҂��K�v�Ƃ���Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B
2.2.
2.2.
�X�e�[�W�E�v���[���e�[�V����
�g�[�L�[�ڍs���ɋꋫ�ɗ������ꂽ�̂͐����҂����ł͂Ȃ��B�f��قŖ����f��̔��t��S�����Ă����y�t�������܂���ʂɉ��ق��ꂽ�B�܂�u�]���e��ٕ݊��̊nj��y�c�Ɉ˂��Ĕ��t����Ă�f��͎����Ɖ��y�Ƃ����₤�ɂȂ����̂ŁA�K�R�I�ɋ��s�҂͊y�t�����ق����v[19][19]�̂ł���B���̌��ʁA���{�e�n�ŒP���I�ɋN�����Ă����f��ق̊y�t���c�́A�₪�đS���I�ȘJ�����c�ɂ܂Ŕ��W���邱�ƂɂȂ�[20][20]�B
�܂�����ŁA�f���݊قł̕��x�A���|�A�S�Ȃǂ̃��C���E�p�t�H�[�}���X�A������u�X�e�[�W�E�v���[���e�[�V�����i�A�g���N�V�����j�v���u���s����ɍs�l�����召�̋��s�҂ڂɎh���v[21][21]���A1929�N�㔼��������ɂ܂��O���f����قŗ��s����B����͂₪�ē��{�f����قɂ��g�y���A���S�E���x�Ȃǂɂ�颗]����������̏�݊ق𒆐S�ɏ㉉����A�܂��n���ł́A�u�������ȉS���x�q����绂ƂȂ�A�����߂�l�`�U��ŋ��A���˓��̏�݊قɂ����钵���ƂȂ��āA�ϋq������A���Ђ����E�������v[22][22]�ƁA���̉ߔM�Ԃ肪����������B�Ȃ��ɂ́A�u���̊قƋ�����K�v�ɔ����ă����B�����㉉�v���Ă����f��ق�A���������قɕ��x�c�Ȃǂ荞�ށu�����B���u���[�J�[�v�����݂��Ă���[23][23]�B���������|�́A�{���́u���ƌ|�v�ł����邱�Ƃ���A���̕������ꎞ�̗��s�ɏI��点���ɁA���̕���ɗ͂𒍂��Â����B
���ہA�����̈�ࣂ��郌�����[�A���H�[�h�r�����������čD�]�������|�́A���c�Îq�A���`���V��A���c���F�Ƃ������X�^�[�܂ł�����ɏグ���B�܂��u�^�[�L�[�v���Ɛ��m�]��q��������ɂ��ꑮ�y�����i1928�N�n���A�̂��̏��|�����̌��c[SSK]�j���J��Ԃ������k���W���Â����悤�ɁA��Ƀ������[�̓��e�[�����͂���A���̕���ł͑��̒ǐ��������Ȃ������B���|�̓g�[�L�[�ڍs����A����ɗ͂����Ċy�������g�������A������f���f�̖��Ԃɍ�������ł����B���̌��ʁA�u���|���̃X�e�[�W�E�v���[���e�[�V�����͐��Ɋe�n�Ɉ��|�I�l�C���l�����A�V���Ƀ������E�E�t�@���܂ł��z���v����Ɏ������̂ł���[24][24]�B1932�N�̓�����ˌ���i����j�n����͓����|���t�]���A��ˏ����̌��c�₻�̑��Ɛ�����Ȃ铌�c�A����ɌÐ샍�b�p���c�Ȃǂ�S���̓���n�����f��قɏ�����������A�ϋq�������[25][25]�B�f��E�ɂ����鏼�|�Ɠ���͂��̃��C���E�p�t�H�[�}���X����̂Ƃ���{���̋��s�̐��i��A�f�搻��A�z���A���s�Ɏ~�܂炸�A�f��ȊO�̃��C���́u�Ăѕ��v�Ɏ���܂�����ȑ������J��L�����̂ł���B
���������O�q�����悤�ɁA�f�拻�s�����ɂ����ẮA�f��͂���������A�̃X�e�[�W�E�v���[���e�[�V�����̖��Ԃɏ�f����錩�����̂ЂƂɂ����Ȃ������B�₪�ĎY�Ƃ����n���A�Ɨ����s�Ƃ��Ē蒅�����f���f�̖��Ԃɂ���炪�u���s����v�Ƃ����t�]���ۂ́A�f��j�I�ɏd�v�Ȗ��ł���B������ɂ���{�߂Ŋm�F�������������Ƃ́A1930�N��ɓ��{�f�悪�u��������v���}����O�i�K�ɂ́A�g�[�L�[�����Ƃ����f��Y�ƊE�S�̂�h�邪�����v�V�̔g�������A���̉ߓn���ɂ́A�R���Ȃ�����₪�ď����䂭�����҂�y�t���邢�̓������[�c�����݂������ƁA�����ĂȂɂ����ނ炪�����̉f�拻�s���`����Ă����Ƃ������Ƃł���B�����āA�����������{�̉f�拻�s�̐��x���A�g�[�L�[�Ƃ����Z�p�v�V�ɂ���Č`��ς��A�p�������Ă�����1930�N��́A���{�f��j��A�ł��d�v�ȓ]�����̂ЂƂł��邱�Ƃɂ͂܂������Ȃ��B
3.
3. �f��ٌ��z�ƕ����i��[26][26]
�{�߂ł�1930�N��ɋN�������f��ق̂��܂��܂Ȍ`�Ԃ̕ω��ɂ��ĊT�ς���B1930�N�̂����\�I�ȉf��ƊE���́A1920�N�㖖�ɋN�������f��ٌ��z�i�����z���܂ށj�u���b�V���v�̗��R�Ƃ��āA���̎O�_�������Ă���B
��A�k�Ђ̃o���b�N���z��{���z�ɂȂ�����
��A�]���̖ؑ��o���b�N���z�ł͋����Ȃ邽�ߑ��z��������
�O�A�f��ِݗ����o�ϓI�Ɋm���Ȃ��Ƃ̗��r�_��L����C�^���i�W���Ă�������[27][27]
�܂���_�ڂ́u�k�Ёv�Ƃ͖��_�A1923�N�̊֓���k�Ђ̂��Ƃ��w���B�֓���k�Ђɂ���Ċ֓��n��̎�v�B�e�����|�����߂ɁA�d�v�ȉf��l���������s�̎B�e���ɓ���Ă������Ƃ͓��{�f��́u����j�v�ɂ����ďd�v�ȏo�����ł��邪�A�f��́u���s�j�v�ɂ����ĉf��ٌ��z���V���ȋǖʂ��}�������Ƃ��܂��d�v�ł���A����̌������ڂł���B
�@�Â����R�̓�_�ڂ́A�s�s�̖c���ɔ����f��l���̑���Ɍĉ����A�苷�ɂȂ����f��ق����A���A�V�z���͂��߂����Ƃ𖾂炩�ɂ���B����͉f��ق̌��z�\���ɂ��܂��܂ȐV�@���������炵���B�܂�f��ق͂���܂ł̓����\������ς��A�܂�����ł͐V���ȊO�ς��������̂ł���B
3.1�D
3.1�D �f��ق̓����\��
1930�N��ȑO�́A�����̉f��ق̓����\���͂��܂��ɉ̕��ꌀ��Ȃǂ̓`���I���C���E�p�t�H�[�}���X����̂�������������Ă���A�ϋq�͗L���ʼn����������Ԃɗa���A���z�c�ɍ����ĉf����ϗ����Ă����B1930�N�㏉���ɂ܂������̋��s�`�Ԃ��c���Ă����n���s�s�̏Z���́A���̔ώG�����ȉ��̂悤�ɔ���������ĒQ���B
�����Ⴂ���܂����A�p�����b�ł����u��������Ⴂ�v�ƌi�C�̂��T���ɑ����ă��M���ɐؕ���n���ƁA���ɉ����D�A�ς킵�������D�������ď��Ɓu���z�c�������v�ƕʛl��������I�����i�A�Ǝv���Ă��a�X�����ė���������̂Ȃ痿���ܑK�ɉΔ��ܑK���v�\�K����Ƃ���B�����Ē��֓���ƌÐF���R����ԓ��������ւāA�������l�p�ɋ�����ϗ��Ȃ����ėђ���Y�剉�f��Ɖ]�Ӄ^�C�g���ɖ����̔���A�₪�ėђ����X�N���[���Ŗ���Ă钆���u�G�T�����l�͔@���v�u�����₨�َq�͂����U�v�ł��B�f�ʒ��͉����͂��\�ЂȂ��A�����͂̂ށA�₪�ăn�l�鍠�ɂ̓����l�̋�r�Ɨ��Ԑ��̔�ƁA�����̔�Ŏ��͂��͂���A�A�鎞�̓T�A��厖�A�����D�̗L��͎W�R�Ƃ��ċP���B����҂̓}���g���A������̂��Ԃ�A����҂͂��̓��������ׂɑ����ꎞ�Ԃ̋���]�V�Ȃ������̂ł�[28][28]�B
���{�̓s�s���ō��z�c���֎q�ȁi�܂��قƂ�ǂ����֎q�j�ɂȂ�A�����a���肪�p�~����͂��߂��̂͂悤�₭1930�N���O�ɂȂ��Ă���ł���B����͉f��ق����̌|�\���㉉����u�n�R�v�Ɗ��S�Ɍ��ʂ����Ƃ����Ӗ��̂ق��ɁA�l�X�̉f��ϗ��ւ̑ԓx�ɑ傫�ȕω���^�����B����A�ނ���t�ɋߑ㉻����s�s�̐����҂��f��ق̌`�Ԃ�ς����Ƃ����ׂ���������Ȃ��B�����a�����p�~���邱�Ƃŏo������̍��G�͊ɘa����A���z�c���֎q�Ȃɂ��邱�Ƃʼnf��ق̏W�q�͂͂���Ɍ��シ��B�f��قɊ��炩�ɓ��ޏ�ł���悤�ɂȂ����ϋq�́A�f��ϗ�������܂ł����C�y�Ȃ��̂Ƃ��Čo������̂ł���B
3.2.
3.2.
��g�[�̐ݒu
�܂��A1932�N�Ăɂ͓����̒鍑����ƕ�����ق����{�̉f��قŏ��߂ė�g�[��ݒu����B�l���̑�����ʋ@�ւ̐����ȂNjߑ㉻�̃v���Z�X�ɂ����āA���{�́A�Ƃ�킯�s�s�Z���͐����ɐv��������K�������߂��͂��ŁA�f��ق��܂��ނ�̗~�������ׂ��l�ς�肵�͂��߂��̂ł���B�����ł͉f��قɂ������g�[�ݒu�̈ꎖ��Ƃ��ċ��s�̐V���ɉf�拻�s�X�̏����グ�悤�B
���s�ł́A�鍑�فA�L�l�}��y���i�Ƃ���1934�N���z�j�A���s��ˌ���i1935�N�J��j�A���ɉf�挀��i1936�N�V�z�j�A���|���i1937�N�V�z�j�Ȃǔ�r�I�{�݂̐������u�ꗬ�v��݊ق̑�����1930�N�㔼�ɐV���z���J�n����B����͂Ȃ��ł��낤���B�e�ق̐V���z�̂Ȃ��ł��ŏ����ɍH���������������鍑�ق́A1934�N12��31���A���̂悤�Ȏp���������B
�����͂��Ɏl�����]�̒��X�s�[�h�H���ŁA��s�ꗬ�قƔ�ׂĂ��������F�Ȃ��ߑ�I�f�挀��ɉ��z�Ȃ����V���ɒ鍑�ق́A�킪���f��ٌ��z����[�^���ւ��\���ʑ��K���X����̋@�ւ����ɉf��X�̈�p���ނ������k�����l��i�O�ς́A���̊��y���ɂӂ��͂�������a�V�����z��������ċ��s�l�̊���������ċ���B����ɒg�[�A��[�A���C���u�̊�������ċ��鎖�����s�ł��ŏ����قł���k�����l�C�̗���������A�i�E���X�̐ݔ��A�w��ȑO���A���c���X�̐ݒu���A�f���݊قƂ��Ă��V�������݁i�T�b���͈��p�҂ɂ��A�ȉ����j[29][29]
�ȏ�̂悤�ɁA�鍑�ق͂��̉��z�Łu��s�ꗬ�قƔ�ׂĂ��������F�Ȃ��v�A�u��[�^���ւ�v�A�u�a�V�ȁv�A�u�ŏ��́v�A�u�V�����v�ݔ��ڂ����̂ł���B�Ȃ��ł��d�v�Ȃ̂́A���̎��_�Œ鍑�ق����s�ł͂��߂ė�g�[�������������Ƃł���B�鍑�ق�7��5��~���₵�����̑��u�́u�X�`�[���ɂ��g�߂�ꂽ��C��d���t�@���ɂ�����e���̃p�C�v�ɑ��v��g�[�ƁA�u�n����S�\�ڂ��@�艺�����Ǔ��̋�C������A�����j�A�Ƌ��ɑ����ăp�C�v�ɂ���ď���ɑ��v���[�ł���[30][30]�B�鍑�قɂ͗��N�i�J�ٗ����j�̌��U����A���ϋq���E�����A�V���ɉf��X�́u�h���v���l������[31][31]�B�������f��X�́u�h���v���l�����邽�߂ɁA�Ȃ���g�[�̊������K�v�Ƃ��ꂽ�̂��B�f��w�҉������Y�́A1950�N��ɗ�g�[�ݔ��������Č��`�������s�s�̉f��ق̎��Ⴉ��A�f��قɑ���ϋq�̗~�]���ȉ��̂悤�ɏq�ׂ�B
�ЂƂ͉f��قɁA�▋�̖��ɂ��ڂ�邽�߂����ł͂Ȃ��A�~�ɂ͔����̂��߂ɁA�����ĉĂ͔����̂��߂ɂ䂭�悤�ɂȂ�B�f��ق͍r�����m�ȕ���ƃX�y�N�^�N���ɂ���āA�z���͂̐����Ŋϋq�Ɍ��������������炷�Ɠ����ɁA�f��ق̊O�̌��������R������̓������������炵�Ă����B�v����ɋ��s�s���́A�f��قƂ��������Ȍ��I��Ԃ��~�n���s�̓~�Ă̌�������a�炰�邱�Ƃ�����̂ł���[32][32]�B
�܂�f��قɑ���ϋq�̗~�]�́A�f���i�ɂ�錻�����������ł͂Ȃ��A��g�[�ݔ��ɂ����K�ȉf��ϗ��ɂ��������Ƃ����̂ł���B���������������ϋq�̗~�]��1950�N��ɂ͂��߂Đ��܂ꂽ���̂ł͂Ȃ��B1937�N�̂���f��G���ł́A��[�ݔ���L���鋞�s�̕����f�挀���]���āu���̏����̒��A��[�łЂ�肷�邾���ł��\�K�̒l�����͂���v�Əq�ׂ����ŁA��[�ݔ��̂Ȃ��V�܉f��فA�ΒJ���ɂ��Ă͎��̂悤�ɍ��]����B
�����̗����A�V�����؊وΒJ�����舫�邭�����x�z�l�N�T���B�����A�������͎x�z�l���ǂ��A�Z�b���Ƃ���ŁA�d�����Ȃ��B�قɗ�[���u���������炾�B�����A�S�x����̏��ꂵ�������֑K���o���ē���C�͒N�����Ă��Ȃ����炤�i�l�Ȃ�[�j�����Ă������j[33][33]�B
����ɂ���1930�N��㔼�ɂ́A��g�[�i���Ȃ��Ƃ���[�j�̊�������Ă��Ȃ��f��قɊϋq�����t���Ȃ����Ƃ́u�d�����Ȃ��v�����ɂȂ��Ă����悤�ł���B���������A�܂�1930�N�㔼�Έȍ~�ɋ��s�̈ꗬ�ق���g�[�̐ݒu�������n�߂锭�[�ɂȂ����̂́A��͂�鍑�ق̉��z�ł��낤�B���̉��z�ɂ�鋞�s���̗�g�[���������s�̋��s�X�ɗ^�����e���́A���̂Ƃ���ł���B
�g�[���u�����̒鍑�ق͉䂪�V�������Ƃ���A���s�l�ɑ��L����`����̂ŁA���ق��k1935�N1���l��O�T�͍��ؔԑg�Ŕw���̐w�����������A�Q����₦���т������R�̖҈Ђɂ́A�@���Ƃ��Ȃ��p���Ȃ��A�g�[�ݒu�������|���n�ߓ��n�O�ْ��̉��z�Ă����������ɊX�̘b��Ƃ���Ă���[34][34]�B
�����ł́A�鍑�ق����قɐ�삯�Ċ���������g�[�����`���A���ہA�l�X���E���������߂ɁA���s�����Ƃ��鏼�|�n�f��ق��ł�̐F�������Ă��邱�Ƃ�������B�Ƃ͂����A�����̉f��ق��������ܗ�g�[�ݒu�H���Ɏ��|���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�����Ŏ��т�ς���n�̑匀��A���s��ˌ���̊J��i1935�N11��11���j����g�[�ݔ��������Ƃ͕ʂƂ��āA���|�n�̉f��ق���g�[��ݒu����̂́A�鍑�ق̉��z����2�N�ȏ����̂��Ƃł���B����������͉̕�����������p�������ɉf�挀��i1936�N12��31���j�A���s�ꗬ�ق̏��|���i1937�N7��1���j�Ƃ��Ђɂ��V�z�H���ɔ��������̂ŁA�Ђ��������Ȃ���A��g�[�̐ݒu�͂���ɒx�ꂽ���Ƃł��낤�B�����A���̎����ɐV���z�����f��ق̑S�Ăɗ�g�[���������ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B��L�̈ꗗ�Ɍf�ڂ��Ă��Ȃ��u�ꖖ�v�̉f��ق͂������A�鍑�قƓ������ɉ��z���{�����L�l�}��y���ł��A���܂��u�ϋq�Ȃ̉��P�A�g���A�h�����u�̊����v���ւ̎R�ł�����[35][35]�B����͂Ȃɂ����o��̖��ł���A���̐ݒu�͂��Ƃ��A���R�ғ��ɂ�����Ȕ�p�����������B�����̋��s�ł͍ō��z�̓��ꗿ���i50�K�A1�~�A1�~50�K�j�ł��������|�����ݒu������[�ݔ��̉ғ���p�́A�����250�~�����邱�Ƃ͂Ȃ������Ƃ���[36][36]�B
�@�Ƃ͂���1930�N�㔼�Έȍ~�ɂ́A�ꗬ�̐V���z�ق𒆐S�ɁA��g�[�������悤�₭�蒅���͂��߂�B��������ȂǑ�s�s�قǂł͂Ȃ��ɂ���A�����u�Z��s�s�v�Ɋ܂܂�Ă������s�s���ߑ㉻���A�l�X�̐������ȑO�������K�������߂����Ƃ͗e�Ղɑz���ł���B���̂Ȃ��ŁA�f��قɉ��K�������߁A�u�����v�ɂ���Ă���ϋq������邱�Ƃɕs�v�c�͂Ȃ��B�����ł�1930�N��ɂ����鋞�s�̎�������グ�����A���s�s�ɂ����Ă��ގ�����𐄑��ł��悤�B�܂��A1930�N�㔼����S����v�s�s�Ɍ��݂���͂��߁A���ꎩ�́A�V�����R���Z�v�g�ł���j���[�X�f���[37][37]�͌������V�z�ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��A��f�ɍۂ��Ắu�ŐV�́v�j���[�X���ŐV���̉f�ʋ@�┭���@���p���A�����ē��R�̂悤�ɍŐV�̐ݔ������g�[���������邱�ƂŁA���ꎩ�̂Łu�j���[�X�v�����Ƃ����̂ł���B
������1938�N�A��g�[�ݔ��́u�����ψ���v[38][38]�́u�����ʈψ���v�Łu�c�R�������嗤�̍����̒��ɗE�킵�Ă��ہA�e�㍑�����������v�Ђ����Ă��̂͂��������v�Ƒ��ʂɋ�����ꂽ�B�����ė��N�A���H�Ȃ��S�ʓI�ɏ��o�����u����ߖ�^���v�̈�Ƃ��āA�S���́u�s�v�s�}�v�̗�[�ݔ��͔p�~�������n����A�Ȃ��ł��f��ق́u�S�p�g�v�̃g�b�v�ɖ��w�����ꂽ[39][39]�B����䂦���s�̑命���̉f��قŗ�g�[�ݔ�����ʓI�ɂȂ�A�f��ق��ϋq�́u�����n�v�ɂȂ�̂́A��͂�u���܁Z�N�㏉���܂ł܂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v[40][40]�̂ł���B
�@������ɂ���1930�N��ɂ������g�[�ݔ��́A�s�s�̋ߑ㉻���ے����A�����ɉ��K�������o���͂��߂��l�X�����߂����̂ł������B���̂Ȃ��ʼnf��قɂ������g�[�ݒu�͔���Ȕ�p��v���A�o�c��̑傫�ȓq���ɂȂ������Ƃł��낤���A�f��ϗ��Ƃ�����y�ɂ����K�������߂͂��߂��s�s�̊ϋq�ɂ͍ō����̃T�[�r�X�ł���A���̎����A�S����v�s�s�̋��s�X�ł͂��̐ݒu�����������̂ł���B
3.3.
3.3.
��f�挀��ƒn���i��
�@���������f��ق̓����\�����z���g�[�̐ݒu�́A�ϋq�̋C�y�ʼn��K�ȉf��ϗ����\�ɂ����ł��낤�B����������Łu��������v���}�����f��E�ɂ����Ă͉f��l���̑���Ƃ�����������Ă������B1920�N��㔼�̃A�����J�ł́A���L�V�[����i1927�N�J��j��W�I��V�e�B�E�~���[�W�b�N�E�z�[���i1932�N�J��j�Ƃ������A��K�͎��e�A�����ؔ��̉f��{�a�i�s�N�`���A�E�p���X�j���j���[���[�N�ɓo�ꂵ���B�f��ϋq�̑���Ɖf��Y�Ƃ̈��艻�ɂƂ��Ȃ��A���Ђ̈АM�������Ă����Ȃ�ꂽ���̐ݔ������́A�������ɐ��E���Q�Ɍ������A�����͔���Ȍo��Ɍ����������̎����������炷���Ƃ��ł��Ȃ������B���܂��܂Ȗ��i�u�АM�Ⓤ���Ƃ̐M���̖��A���A�u���b�N�E�u�b�L���E�V�X�e���v�j����ȒP�Ɏ�������Ƃ�����ł������f��{�a�̑��݂́A�A�����J�̉f��Y�Ǝ��̂���@�Ɋׂ�A�����̐l�X�́u�������܂���ɉf��͂������߂��ƒf���v����[41][41]�B���̊�@�I���~�����̂́A�g�[�L�[�f��̓����ł���B�A�����J�̉f��w�҃��o�[�g�E�X�N���[�́A�u���ϓI�ȕ��苻�s�̃T�C�����g�f��ɂ����ۂ������͂��߂Ă����f��t�@���́A���Ƃ��������͂˂������Ă��A�g�[�L�[�Ȃ�Ή��ł����悤�Ƃ��Ă߂������v�ƁA�g�[�L�[�����ɂ���Đl�X���ēx�f��قɎE�������l�q���q�ׂĂ���[42][42]�B
�����A���{�ł͂���قǒP���ȉ����͖]�ނׂ����Ȃ������B��ʑ�O�ɂ���������҂̐l�C�┭���@��̕s��A�����ē�����`���̍��v�Ԕ~�Y���u�O���f��̒��A�����f��͉���Ƃ��Ă����t���킩��Ȃ����狻�����������E����ė��Ӂk�����l�����f��͔����ׂ̈ɑ�O�������ЁA�������ꂽ�q�݂̂��c��v��v[43][43]�ƕ��͂����悤�ɁA�O���f��ɂ����錾�t�̖��Ȃǂ���A�g�[�L�[�f�悪�������Ɋ��}���ꂽ�킯�ł͂Ȃ��������A�����������{�ł̓g�[�L�[��������f�挀��̌��z�ɐ旧���Ă����B���̍��̓��{�ɂ�����f��ٌ��z�u���b�V���v�ł͒����K�͂̏�݊ق������A���傷��f��l�������e����匀�ꌚ�z�v��́A1930�N��O���̕s�i�C�ɉ����A�f��Y�Ƃ��u���Ԉ�ʂɊ�ƂƂ��Ă̊m�������^�v���Ă���A���Ă���Ă͗��������ɂȂ���̂��قƂ�ǂł�����[44][44]�B�A�����J�Ɣ�r���ē��{�ł́A�f���i�Ƃ����\�t�g�ɂ͌o�ϓI���l��u�����A�f��قƂ����n�[�h����Y�ƑS�̂܂ł������n���L������͂��܂������Ă��Ȃ������ƌ��킴������Ȃ��B
�B��A���{���ꂪ���{�ɂ�����ŏ��̉f��{�a�Ƃ��āA1929�N�ĂɋN�H���ꂽ���A�������H���͂������~����A�u�S����ԎK���炯�ɂ��Ċ[������Ƃ܂ňٖ������A���v������̂��S�������݂������Ȃ������v[45][45]�B���̌�A���{���ꂪ�悤�₭�J�ق��ނ�����̂�1933�N��A���̂��ƂŁA���̎��e�l����5,000�l�i���́j�ɂ̂ڂ�A�f���f��̂ق��ɁA�_���X�z�[���A�ӂ��̑�H���A�����Ēn���ɂ͂̂��ɓ��{���̃j���[�X�f��قƂȂ���n�����ꂪ�J�ق���B����ɋq�Ȃ����ł͂Ȃ��L����֏��ɂ�����܂Œʂ��Ă�����g�[���u�║��Ƌq�Ȃ�S���Ŏd��h�ΐݔ����������Ă���A�����Ƃ��ɓ��{�ŏ��̉f��{�a�ł�����[46][46]�B
�@���邢�͋K�͂Ƃ��Ă͓��{����ɗ�邪�A1,500�l�����e�������J�f�挀��������u�匀��v�Ƃ���1934�N2���ɊJ�ق����B1930�N��̉f��j�A�Ȃ��ł��f�拻�s�j������Ō��������Ƃ̂ł��Ȃ�����В��̏��ш�O���肪�������̌���́A����܂ł̒��֎q���ł͂Ȃ���l��r�̍��Ȃ�h�����u�����˂��J�[�y�b�g��~���߂��D��Ȃ���ŁA�d�C�ݔ������S�Ȃ��̂ł������B���̈���A�o�c���j�Ƃ��Ă�50�K�ψ�A�Z���ԃv���O����[47][47]���f���A�ϋq�Ɏ�y�ȉf��ϗ��������炵��[48][48]�B
�@���̂悤�ɔ���Ȕ�p��v���A�u���_�[���E���l�b�T���X���v�u���s�Ȃ錚�z���v[49][49]�ƌ`�e������f�挀�ꌚ�z�̌X���́A�f�悪�o�ό��ʂ������炷�Y�ƂƂ��ĔF������͂��߂��Ƃ����f��ٌ��z�u���b�V���v�̑�O�̗��R�ɑ���������̂ł��낤�B�����A����͈ꎞ���́A��������s�s�Ɍ���ꂽ���s�ł������B�s�i�C���������1933�N�����肩��i�C�㏸���[�h�������Ě��ʂȑ匀�ꌚ�z�͐����邪�A����ȑO�ɂ́A���������������d�����ׂ����Ƃ̎咣�������邵[50][50]�A����������āA1937�N12���ɂ́u��펞���z�����߁v�ɂ����750���ȏ�̉f��قȂǂ̐V�z�͒��~����A�����m�푈�������ƂȂ�ƁA1944�N2��25���Ɋt�c���肳�ꂽ�u������[�u�v���v���āA���N3��5���ȍ~�A�������s��͈ꎞ������邱�ƂɂȂ�[51][51]�B���̒��ɂ͓��{������܂܂�Ă����B
�܂����̍������ɂ��S���e�n���u�������v���Ă��錻�݂Ƃ͈قȂ�A�����̓������͂��߂Ƃ��邲���ꕔ�̑�s�s�̕����I�͂���߂ē���Ȃ��̂ł������B�����̍ŋߍx�s�s�̉��l�̉f��X�ł���1930�N�㏉���ɂ́A�u���y�ق̑O�ɂ͏\�����l�ʂ̗V�q�̖�����y�����������ă��a�I���āv����A�u�̗l�Ɋe�ق����ӂăl�I���E�T�C����C���~�l�[�V�����ɋ����|���Ă��ق͈ꌬ���Ȃ��v�Ȃ̂ł���[52][52]�B
�܂�����A���̎����̒n�������f�Ƃ������s�`�Ԃ́A�f��̋���I�@�\����j�I�ɏؖ�����d�v�Ȍ����ۑ�ł��邪�A�{�e�̎˒����z���Ă��܂����߁A�����ł͓��{�̓s�s���ƒn���̕����I�i��������ɂ���A1940�N��O���̃G�s�\�[�h���ЂƂ����Љ�邱�Ƃɂ���B
�����R�⓹������Ă�������ӂ̉f�ʉ���݂Ă����V�k���f�ʉ�ς�ł�������ɗ�������͂��āA�܂�ŕ��l�ł��q�ނ悤�Ȋ��D�Łu�܂����Ă���v�Ƃ��ǂ��ǂƗ���ł��p�����ڌ�����[53][53]�B
�u��y�@�ւ̖w��ǂȂ��v�n�����͌�y�f�����Ɋ��}���A�u�]���̎U���I�ȁv�����f������u�_�ƋZ�p�w���f��v�ɑ傫�ȊS���Ă����Ƃ����B
���E���Q�̉e����ւ�Ȃ�����A���������̈ڐA����悤�₭�������{�����Ƃ��ĊJ�Ԃ����͂��߂��l�X�������I������搉̂��Ă���1930�N�㏉��[54][54]�A�f��ق͈֎q�Ȃ̓������g�[�̐ݒu�ȂǓ����\���Ɖf���f�`�Ԃ���ς����A�ϋq�ɋC�y�ʼn��K�ȉf��ϗ������悤�ɂȂ�B�܂������ɂ́A�s�s�l���ɔ�Ⴕ�Č�������u��������v�̉f��l�������e���ׂ��A��f�挀�ꌚ�z�����s����B�����͂�������A�l���̑�����ʋ@�ւ̐����Ȃǂɂ�鐶�����̐v�����Ƃ������s�s�̋ߑ㉻�v���Z�X�����ڂɉe���W�������Ă���B�����Ă܂��}���ɋߑ㉻��i�߂�s�s���ƁA���ꂪ�i�܂Ȃ��n���Ƃł́A���퐶���݂̂Ȃ炸�A�����I�Ȋi���܂ł����L�������ł��������Ƃ��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
4.
4.
��`����
1930�N�㏉���A�o�ϊw�I�ϓ_����f�挤����W�J���Ă����Ί��Ǖv�́u���̕n�x���f�掖�Ƃɋy�ڂ��e���͑傫���v�Ƃ����^�����Ȏw�E�����Ă���B���̎����A���{�̐l����l������̔N�ԏ�����218�~�ł������B����͈�l������1,272�~���҂��o���A�����J�͂������A���̐�i�����̂���ɂ������y�Ȃ��ł������B����ɓ��{�S���̎��ƎҐ���1929�N����30�N�ɂ�����47.2�����̋����ׂ��������������Ă���B����͂̂��Ɂu���E�勰�Q�v�ƌĂ��1930�N��O���A���{���܂����\�L�̕s����ԂɊׂ��Ă����Ƃ��������������Ă���B�������Ă݂�A�u�@��������{�l�ɂ͉f���p�ɂɌ��邾���̗]�T���Ȃ��v�͂��ł���[55][55]�B���������̌�A�f��l���͊ɂ₩�Ȃ�������債�Ă����̂ł���B
�} 3�@
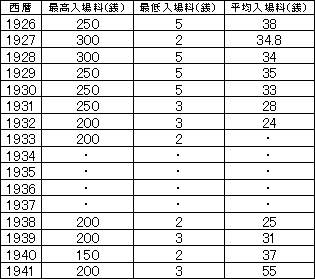
�}3�Ɍ�����悤�ɁA1920�N�㖖����30�N�㏉���ɂ����āA��ٕ݊��ϓ��ꗿ���͊ɂ₩�Ȓቺ�X���������Ă���[56][56]�B����ɉ����đS���e�n�Łu�������s�v�Ȃǂ̊������s������Ȑ�`��^�C�A�b�v���킪�J��L�����A�s�����ɂ���l�X���f��Ƃ�����y�i�����ɕs���Ȃ炴�����́j�Ɏ䂫���邽�߂Ɋe�f��ق��z���������܂��`����Ă���B1930�N�㏉���̎�v�Ȑ�`���@�́A�҃r���A���ŔA�|�X�^�[�ɂ����̂ł������B���������A�N�e�B���Ȃ��̂Ƃ��Ă̓`���h��������������������A��`�L�����f�����������Ԃ�o�X�����s���A����ɋ�ɂ͐�`������f������s�D��C������ь������悤�ɁA�e�n�ł̌�������`�A��������̗l�q���V���A�G���ɋL����Ă���[57][57]�B�܂����̎����A��s�s�̍��ȉf��قł͗�g�[�ݔ�����ȃT�[�r�X�Ƃ��Č��`���͂��߂邪�A���̐ݔ���L���Ȃ��n���̉f��قł��\�Ȃ�����̃T�[�r�X����Ă����B����������ƁA�u�Č͂ꎞ�v�̕X�������╕����̓��߂���J�����_�[���Q�ɂ�銄���[�u�ȂǁA�e�ق̋�S�A�H�v�̂��Ƃ�������[58][58]�B�Ȃ��ł��u���}�������ԁv�͒����s�̓d�C�قɂ��T�[�r�X�̎���ŁA�u��l�ܐl���L���ϗ�����ꍇ�ɁA���ق֓d�b��������ƁA�����Ɋe���̑�܂Ŏ����Ԃ��}���ɗ��āA�ق܂Ŗ����ő���͂��Ă����v�Ƃ������̂ł�����[59][59]�B�s�s�̋ߑ㉻�ɂ���Đ����ɉ��K�������߂͂��߂��l�X�ɂƂ��āA�����f��ق܂Őg�̂��^��ł����u���}�������ԁv�͓����̉f��ϋq�̃j�[�Y�ɉ������͂��ł���B
�����Ă��̎�������ɂȂ����A�������`�^�C�A�b�v�̗�Ƃ��Ắw�Q���̓V�g�xThe Blue Engel�i�W���Z�t�E�t�H���E�X�^���o�[�O�ēA1930�j��f�ƃ��R�[�h��Ѓr�N�^�[�̃^�C�A�b�v���@����������B�����ł͎剉���D�̃}���[�l�E�f�B�[�g���b�q[60][60]�����������R�[�h�̔����ɍۂ��āA���R�[�h�ԍ��A�f�敕�؊ٖ��A��f�����L�ڂ̃��[�t���b�g��|�X�^�[�̑�ʔz�z�A�嗧�Ŕ̐ݒu�͂������A���R�[�h�X�́u�V���E�E�C���h�E�����̋����v��f��ϗ��҂�Ώۂɂ������ܖ��ŏܕi�̋�i�𑈂킹�Ă���[61][61]�B
����������݊يԂł̐�`���������𑝂��A�e�ق����|�ꂷ��n������������[62][62]�A�u�f��t�@���v�ɂƂ��Ă͔��Ɍb�܂ꂽ���ł���A�������������{�ł��܂��܂ɉԊJ�����̎������ł�搉̂����̂͑��ł��Ȃ��ނ�u�f��t�@���v�ł�������������Ȃ��B�܂����Ǝ폤�i��R�[�h�ȂǑ��̃~�f�B�A���ƌ��т����邱�Ƃɂ���āA�f��̏��i���l���N�̖ڂɂ����m�ɂȂ����̂ł���B
5.
5.
�f��قƌ��
�} 4�@
[1][1] �c������Y�w���{�f�攭�B�j�T�x�i�������_�ЁA1968�N�j�A100�ŁB��݂ł͂Ȃ������s��ɂ��������ϗ��҂̓��v���ʂ��܂������[���B�������������s��Ƃ́A�u�ꃖ���Ԃɏ\���ԔT���\�ܓ��Ԉȏ�̋��s�̏o���Ȃ��ق��]�Ӂv�Ƃ�����`���Ȃ������̂ł��邪�A1930�N��㔼�ɂ��Ȃ�ƁA�����ł͂킸��3�فA���s����ł�7�A8�ق������݂����A�S����v�s�s�ł��卷�͂Ȃ��B�������L��Ȍ����i����k�C���ł͏��61�قɑ��āA78���̉����s�ꂪ���݂��A�u��݊وȊO�̋��s��ɂ��������ϗ��Ґ��v��2�ʈȉ���傫�������������v���ʂ��݂���i�w�f��N�Ӂx���a16�N�ŁA52�|55�Łj�B�����������ٓI�ȓ��v���ʂ��ʼn߂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�k�C���̉f�拻�s����Ȃ�тɉ����s�̌����Ɋւ��Ă͕ʂ̋@��ɏ��肽���B
[2][2] �Ȍ�e��̐}�\�́A�e�����̋ƊE���L�ڂ̓��v����ɁA�V����f��G�����瑊�ΓI�ɐM�ߐ��̂��鐔�l��₢�A�M�҂��Ǝ��ɍ쐬�������̂ł���B���̂��ߌ����Đ��m����ȓ��v�ł͂��肦�Ȃ����Ƃ�f���Ă����B�}1�Ɋւ��ẮA�H��3���ِ݊��̍��v�������ƐH���Ⴄ���A����͓����̓��v�̂܂܍̗p�����B
[3][3] �w���{�f�掖�Ƒ����x���a5�N�ŁA48�|49�ŁB
[4][4] ����A54�|55�ŁB
[5][5] ���E���̖{�i�I�g�[�L�[�f��ł���w�W���Y�E�V���K�[�xThe Jazz Singer�i�A�����E�N���X�����h�ēA1927�j�Ɏg�p���ꂽ���[�i�[�E�u���U�[�Y�Ђ́u���@�C�^�t�H���v�́A�T�E���h�����R�[�h�ɓ���������f�B�X�N���g�[�L�[�ł������B����A����ɑR����20���I�t�H�b�N�X�Ђ��J�������u���[���B�[�g�[���v�́A�t�B�����[�̃g���b�N�ɃT�E���h���L���ϊ���������̂ł���iEphraim Katz, The Film Encyclopedia, 3rd ed., rev. Fred Klein and Roland Dean Nolen [New York: Harper Perennial, 1998], p.985�j�B�Ȃ��A1927�N10���ȗ��t�H�b�N�X�Ђ����Â���u���[���B�[�g�[���E�j���[�X�v�́A�����ʂ�ڍׂȉ�������L����j���[�X�f��Ƃ����u�V�W�������v���g�[�L�[�Z�p�̎����ł��邱�Ƃ������Ă���B
[6][6] �w���{�f�掖�Ƒ����x���a5�N�ŁA53�|54�ŁB�Ƃ͂����A�����i7�فj�Ƒ��i6�فj�Ƃ�����s�s�̉f��ق����̔����ȏ���߂Ă����B
[7][7] �c������Y�w���{�f�攭�B�j�U�x�i�������_�ЁA1968�N�j�A69�|72�ŁB
[8][8] �G���w�L�l�}����R�[�h�x�̓��l�ł������A�R���������̒��S�l���ŁA��ɃA�����J�f��Ŏg�p����Ă���f��Ǝ��̎�@�i�J�b�g�o�b�N�A�N���[�X�A�b�v�A�����O�V���b�g�Ȃǁj��������邱�Ƃ�V�i���I�̓����A���`�̔p�~�Ȃǂɂ���āA����܂ŋ�����V�h���̓`�������������Ă������{�f��̉��ǂ��咣�����^���B
[9][9] �����������ł́A�u��燁v�͂��������y�̓I�Ȍď̂ł���A���������āu�َm�v���炪�u�f������ҁv�𖼏�����Ƃ����S�������̐��i�䉀�����w�䉀�����y�����x[���ƔŁA1999�N]�A11�Łj������A���̐^�U�̂قǂ͂��܂��ɂ͂����肵�Ȃ��B
[10][10] �A�[�����E�W�F���[�u�َm�̐V������\�\�吳���̓��{�f����`����v�i��������T��A�w�f��w�x��9���j�A55�|73�ŁB
[11][11] ����A65�ŁB
[12][12] �l���c���F�w�f��j�ւ̏��ҁx�i��g���X�A1998�N�j�A137�|138�ŁB
[13][13] ����A145�|146�ŁB
[14][14] ���������̓��v�Ɋւ��ẮA�u���������͍̂������w���ƒ��x�ȉ��̂��̂ŁA���w�Z���ƈȏ�̂��̂͋p���đ������A���ꂾ�������҂̊w�͂͌��サ���v�Ƃ������l������i�w���ۉf��N�Ӂx���a9�N�ŁA110�Łj�B
[15][15] �w���{�f�掖�Ƒ����x���a5�N�ŁA55�ŁB
[16][16] �W�F���[�A68�|70�ŁB
[17][17] �l���c�A140�ŁB
[18][18] �w�f��N�Ӂx���a16�N�ŁA16�|17�ŁB
[19][19] �w���{�f�掖�Ƒ����x���a5�N�ŁA55�ŁB
[20][20] �y�t���c���S���I�ȘJ�����c�ւƔ��W���Ă������o�܂Ɋւ��ẮA�c������Y�w���{�f�攭�B�j�U�x�A204�|205�ł��Q�Ƃ̂��ƁB
[21][21] �w���{�f�掖�Ƒ����x���a5�N�ŁA56�ŁB
[22][22] ����A53�ŁB
[23][23] �����Y�u�����B���̍����v�i�w�L�l�}�{��x1931�N5��11�����j�A35�ŁB
[24][24] �w���{�f�掖�Ƒ����x���a5�N�ŁA52�|57�ŁB
[25][25] 1930�N��㔼����A�قږ����̂悤�ɒԂ�ꂽ�Ð샍�b�p�̓��L�́A���̎���̕��������ɂ͌������Ȃ������ł���B�{�����ɑ����Ăق�̈��������ƁA1937�N7��10���A�܂�u�x�ߎ��ρv�u�����Ɍ�����̋��s�ɑ؍݂��Ă������b�p���u�߂��̋��s�j���[�X�f�挀��֓���B�p���}�E���g�̃X�|�[�c���C�g�̈�сA�����w�Z���ƂĂ��ʔ��������v�i�Ð샍�b�p�w�Ð샍�b�p���a���L�E��O�сx[�����ЁA1987�N]�A326�Łj�ƒԂ邪�A�����̓��L�̂Ȃ��ł́A���́u���ρv�Ɋւ��Ă̔ߊϓI���y�͂قƂ�nj����Ȃ��B�̂��Ɂu�������R���S�ɒ����Ȃ��̂������͎����Ă��ȁv�i���A�풆�сA160�Łj�ƁA���b�p�������m�푈�u���ɐS�����������A�����1�K��2�K�����낤��ƍs��������l�q�Ɣ�r����A�u�x�ߎ��ρv�����قǏd��ɑ����Ă��Ȃ����b�p����͂̔������_�Ԍ����ċ����[���B
[26][26] ����܂Ŋϋq���f���i�ɑΖʂł���B��̏�Ƃ��ĉf��ق̑��݈Ӌ`��̌n�I�ɐ[���₤����s�����͊F���ł��������A���z���Ƃ��Ẳf��ٌ����͂������Ƃ�1930�N��ɂ͂�����x���݂����悤�ł���B�ؑ��h�O�Y���w����y�f��فx�i��֏��[�A1934�N�j�Œ����ȏ�̊ϋq��z�肵�����ꂨ��щf��ِݔ���������A����c��w�̌��z�u�`�ł́A�f��ق��Љ�w�i�ɉ��������z�◧�n�`�ԁA�ϋq�ƃX�N���[���̗��z�I�Ȉʒu�W�Ȃǂ��c��ɋ����Ă���i����Y�w����y�f��فx�i����c��w�o�ŕ����ŁA1942�N�j�B
[27][27] �w���{�f�掖�Ƒ����x���a5�N�ŁA104�ŁB
[28][28] �u���{�S������f�掏��s�r�v�i�w�L�l�}�{��x1931�N3��21�����j�A115�ŁB
[29][29] �R�{���Y�u�V�و�ہ\�\���s�鍑�فv�i�w�L�l�}�{��x1935�N1��21�����j�A11�ŁB
[30][30] �w���s���o�V���x1934�N12��28���t�B
[31][31] �u�f��ٌi�������v�i�w�L�l�}�{��x1935�N2��1�����j�A24�ŁB
[32][32] �������Y�u�f��قƊϋq�̗��j�\�\�f��s�s���s�̐��v�i�w�f���w�x��55���j�A45�|46�ŁB
[33][33] �u���ɂ悢�Ƃ��v�i�w�f��t�@���x1937�N10�����j�A140�ŁB
[34][34] �u�f��ٌi�������v�i�w�L�l�}�{��x1935�N2��1�����j�A24�ŁB
[35][35] �u�f��ٌi�������v�i�w�L�l�}�{��x1935�N1��11���j�A13�ŁB
[36][36] �w���s���o�V���x1936�N8��10���t�B
[37][37] �j���[�X�f��قɊւ��ẮA�٘_�u�j���[�X�f��ف��a�������̋��s�Ƃ��̋@�\�v�i�w�f���w�x��68���j�A28�|46�ł��Q�Ƃ��ꂽ���B
[38][38] �u�����ψ���v�͒��������ψ���ƒn�������ψ���ɕ������邪�A���̏ꍇ�͒��������ψ�����w���B���������ψ���̉�͏��H��b�ł���B
[39][39] �w���s���o�V���x1939�N7��9���t�B
[40][40] �����A46�ŁB
[41][41] �A�����J�̉f��{�a�Ɋւ��ẮA�W�F�C���Y����i�R�w�f��̋��ȏ��x�i��{��������A�t�B�����A�[�g�ЁA1996�N�j�A206�ł����o�[�g��X�N���[�w�A�����J�f��̕����j�i��j�x�i��؎�Ŗ�A�u�k�ЁA1995�N�j�A292�|299�ł��Q�Ƃ����B
[42][42] �X�N���[�A301�ŁB
[43][43] ���v�Ԕ~�Y�u�q�͗V��ł��v�i�w�L�l�}�{��x1930�N9��11�����j�A14�ŁB
[44][44] �w���ۉf��N�Ӂx���a9�N�ŁA5�|6�ŁB
[45][45] ����A6�ŁB
[46][46] ���{�ɂ������f�挀��́A1933�N9���J��̑�����O���m����������Ě���Ƃ��邪�A������͗�5���ɂ͑������j�Y���A���|����������ɂ���đ�㌀��Ƃ��ē��N8���ɊJ�ꂳ�����i�c������Y�w���{�f�攭�B�j�U�x�A210�|211�Łj�B
[47][47] �]���A�f��ق̈��̋��s���Ԃ͒Z���Ҍ����Ă�4�A5���Ԃ���ʓI�ł������B�����ŏ��т��f����2���Ԃ��������̋��s���Ԃ́A�����Ƃ�����s�s�����҂̃j�[�Y�ɉ�������̂ł������͂��ł���B����Ɍ�ɂ́A�u��{���ċ��s�v�Ƃ������z���o�ꂷ��B
[48][48] �w���ۉf��N�Ӂx���a9�N�ŁA8�|9�ŁB����J�f�挀����߂��鏬�т̍ł��ڗ����������Ƃ��ẮA�J�ّO�Ɂu�M�����Ⴕ�{����̎x�z�l�Ƃ��Č}�ւ�ꂽ��Ƃ��Δ@���Ȃ�����o�d��������T��H�v�ƈꓙ200�~�̌��܋��������āA���s�A�C�f�B�A���f��G���̍L����ő�X�I�ɕ�W���Ă��邱�Ƃ���������i�w�L�l�}�{��x1933�N9��1�����A44�|45�Łj�B
[49][49] �w���ۉf��N�Ӂx���a9�N�ŁA7�ŁB
[50][50] �w���{�f�掖�Ƒ����x���a5�N�ŁA108�ŁB
[51][51] ��̓I�ȑS���̕��ق͓c������Y�w���{�f�攭�B�j�U�x�A387�łɋL�ڂ���Ă���B
[52][52] �����Y�u���l�f��X�W�]�v�i�w�L�l�}�{��x1931�N3���P�����j�A41�ŁB
[53][53] �w�e�{�A���a�\���N�^���a�\��N�^���a��\�N�f��N�ӌ��e�x�i�t�B�����Z���^�[�����A�Ő��s���j�B
[54][54] 1939�N�A�u�f��@�v�{�s���̎G���w���{�f��x�ɂ́A�u���̍����͉f��قɍs���A�����ăJ�t�F��K�ӂ��Ƃ͊y���������B���p�����������ʑn�ӂƊ��C�Ƃ�����������B�l�X�͐����̔��Ɨ͂ƐV�@���Ƃ��H�v���悤�Ƌ����Ă��₤�Ɍ������k�����l�����Ƃ����̍��́A�f��ӏ܂̐������Ɖs���Ɗϋq�ւ̎w�����Ƃɂ����āA�����͗�芎�S�̂ɎG���̒��q�̂��邱�Ƃ͑��͂�Ȃ��v��1930�N�O��̎��R�ŗ͋����A�₢�����͋C�����Â��铊�e���f�ڂ���Ă���i�q�c�S�O�u���َ���̎v�Џo�v[�w���{�f��x1939�N10����]�A162�|163�Łj�B
[55][55] �Ί��Ǖv�u�f��̍w���́v�i�w�L�l�}�{��x1931�N4��21�����j�A53�|54�ŁB
[56][56] ���̎����A���ꗿ���͑S���I�ɒl�����X���ɂ������ɂ�������炸�A����ɉۂ��������ŗ��͕ς�炸�A�[�łɋꂵ�ދ��s�҂����͑S���e�n�œ���ł̌y���^�����N�������i�w���ۉf��N�Ӂx���a9�N�ŁA51�Łj�B
[57][57] �f��̐�`�L���Ɋւ��ẮA���̎����A�����̋L�q�������邪�A���̂ЂƂƂ��āw�L�l�}�{��x�Ɍf�ڂ��ꂽ���̂������Ă������B�����ł́A�o�X�̍Ō㕔�A�C���A����̒g���A�}�b�`���𗘗p�������̐�`����A1931�N�̎��_�Łu�s���l��v�Əq�ׂ������ŁA�f����̂̃��R�[�h�쐬��W�I�̗��p�Ȃǁu���̐�`�v���u�V��p�v�Ƃ��ď��コ��Ă���i�����Y�u�f��قɂ������`�̐V��p�v[�w�L�l�}�{��x1931�N11��1����]�A17�Łj�B
[58][58] �u�n���f��E�n�K�L�ʐM�v�i�w�L�l�}�{��x1931�N9��21�����j�A85�ŁB
[59][59] �u�n���f��E�n�K�L�ʐM�v�i�w�L�l�}�{��x1931�N11��11�����j�A95�ŁB
[60][60] Dietrich, Marlene�i1901�|92�j�B�x���������܂�̏��D�B1920�N��A�h�C�c�ʼn����␔�{�̉f��o�����o�āA�W���Z�t�E�t�H���E�X�^���o�[�O�Ɍ��o�����B�n�Č�̓p���}�E���g�Ђƌ_�AMGM�Ђ̃O���^�E�K���{�i1905�|90�j�Ƃ��̂������(Katz, p.369)�B����E�����A�i�`�X����h�C�c�f��E�ւ̏��v�v�����邪��������ہB
[61][61] ��c�����u�^�C�E�A�b�v��B�v�i�w�L�l�}�{��x1931�N6��1�����j�A21�ŁB
[62][62]�w�L�l�}�{��x��̍��k��ł́A���̋��|���h�����߂Ɂu�����ٓ��u�����k���āA�������������藧�āT���Ƃ��ӋC���v�⋻�s�g���ݗ��������n�߂��ƕ���Ă���i�u�S���f��E�s�r���k��v[�w�L�l�}�{��x1935�N1��1����]�A59�|66�Łj�B
[63][63] �O�c���u�����ɉf��ق��ł����v�i�w�u�����{�f��1�@���{�f��̒a���x[��g���X�A1985�N]�j�A354�ŁB
[64][64] �u�\��K�v�Ƃ́A�֓���k�Ђœ|�����_�t�̌ď̂ŁA�ቺ�ɋg����]�݁A���{���̃G���x�[�^�[��푈�G��i���A�����������A�L�����Ƃ��Ă��@�\�����B�u�\��K�v�Ȃǖ������̍��w���z�Ɋւ��ẮA���ܐa��w�����̖��{�s�s�@�����E���̗V�y��ԁx�i���}�ЁA1994�N�j�A61�|96�łɏڂ����B
[65][65] ���c�r��u�����ƌ�ʋ@�ցv�i�w�L�l�}�{��x1935�N3��21�����j�A34�|35�ŁB
[66][66] ������u���s�w���ہv�i�w�L�l�}�{��x1935�N5��11�����A10�|11�ŁA1935�N5��21�����A24�|25�Łj�B�f��ٌo�c�Ɋւ��邱�̘A�ڂł́A��ʖ��̂ق��ɉf��ق̗��n���`�@���͂��߁A�ϋq�z���@�Ƃ��đ薼�₻�̌�b�̂����炷���Y���ɂ܂ŁA���ꂼ�ꐔ�����̎��Ⴉ����ʊW���o���A�u�Ȋw�h�v����̏ڍׂȌ����͋����[���B
[67][67] �ڋ߂ȗ�������A���݂ł����s�s���ɂ���f��فA���s�݂Ȃ݉�ق̃��r�[�ɂ͍Ŋ��̋ߓS�����w�̎����\���f������Ă���B