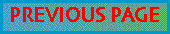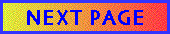CMN! no.1(Autumn.1996)
田中登監督ロング・インタビュー
「優美なる死骸遊び」に魅せられた作家、プログラム・ピクチャーの遺産
1.助監督時代、デビュー、日活製作中止、映倫検閲、『秘(まるひ)色情めす市場』
−−本日は『秘(まるひ)女郎責め地獄』、『女教師・私生活』の2本立を御覧いただきまして、田中登監督をお呼びしました。私の方も改めて、今回の上映やビデオで監督の作品を拝見いたしまして、映画の血がきわめて濃いとでもいいますか、そういった作品が多いことに驚きました。
さっそくお話をうかがいたいと思います。
田中 おはようございます、監督の田中です。どうぞ宜しくお願いします。
−−さっそくですが、まずそもそも映画に入られたきっかけは何ですか。
−−僕は大学時代はちょっと散文、小説を書いていたんですが、それと詩をやってまして、言葉で詩をやってると、詩の言葉には一言一言の喚起力が非常にありますから、それをだんだんやっているうちに、なるべく言葉を費やさないで理屈をこねないで感覚的に分かるものが何だろうかと思ったら、やっぱり映像だったんですね。
それで散文よりも詩を書いて映像をやってみようかなと思いまして、シナリオ研究所ってありますけど、それの僕、4期生なんですけども、そこで大学4年の時にシナリオを少しやりました。その後現場に出たいということで、東宝撮影所で黒沢明さんの『用心棒』なんかですね、あれの時に現場で美術の、セットの柱を磨いたりですね、それから今でも忘れないんだけども、キャメラの横に「がんから」っていって炭で火を起こすんですけれど、キャメラをあっためる時にそれを何十個と起こすんですよね。そういうアルバイトをやったりして、そしてアルバイトの特権で『用心棒』なんかキャメラの横で、監督が飲むお茶を汲みながら横で威張って見てるわけだ(笑)。
それから、『モスラ』。本多猪四郎さんがいましたね。それから『ゲンと不動明王』だ。それから川島雄三さんの『特急にっぽん』とかね、堀川弘通さんの『別れて生きるときも』かな。シナリオ書きながら、アルバイトの特権でちょっと現場を見ようということでね。
卒業の前に、助監督試験に通る前に入って、『用心棒』の時に合間に薪を焚きながら三船さんなんか話をしてて、「おいお前たち、助監督だけにはなるなよ」なんていって三船さんにからかわれてね(笑)。「助監督になると大変だぞ。奴隷に等しいぞ」なんて言われてね(笑)。冗談でね、撮影の合間に言われたんだけども、やってると面白いんだよね。映像でシナリオをやってると映画はやっぱりいいなあと思ってね。それで助監督試験を受けたら奇跡的に通りましてね、それでこの道に入ったんです。
−−同期にはどういう方がおられたんでしょう。
田中 同期はですね、1200人ぐらい来て4人採ったのかな。その時、小沼勝さんとね、小原宏裕さん、それから僕と、今プロデューサーやってる結城(良煕)さんとかね。一人はすぐ辞めました。だから5人で映画界に残っているのは4人です。
−−補足しますと、結城良煕さんというのは監督の『秘(まるひ)色情めす市場』、『実録阿部定』のプロデューサーです。監督の曽根中生さんはもっと後ですよね。
田中 曽根ちゃんは僕と一緒に助監督試験を受けて、その時はちょっとね、彼ダメだったんですよ。翌年また・・・曽根らしいんだけどね、もう一回受け直して入ってきたんだよね。結城と曽根くんは東北大学で同期生なんですよ。だから結城が先に一年早く入って、その後曽根ちゃんが一年遅れで入ってきて。だから助監督室では僕が7期生で、曽根ちゃんは8期生ですか、ということですかな。一年早いも遅れるも関係ないけどね(笑)。
−−助監督で日活に入られてつかれた監督、あるいは作品というのにはどういったものがあったのでしょうか。
田中 キネマ旬報にも自分の助監督時代っていうので書いた記憶があるんですけど、僕はほとんどの監督をやりました。野口博志さん、山崎徳次郎さん、最初の一本目は山崎徳次郎さんという監督さんでね、小林旭さんの『風に逆らう流れ者』っていう作品なんですよ。卒業する前にね、卒業式に出る前に地方ロケに引っ張られちゃったことあるんです。「もう助監督試験通ったから、卒業式あとでいい」って言われてね(笑)、「とにかく現場行け」って言って引っ張られてそのシャシンをやって、卒業式やった記憶あるんですよ。
それから亡くなった中平康監督、蔵原さん、今村昌平さん、鈴木清順さん、熊井啓、小沢啓一、西河克己、それから・・・まあほとんどやりましたね。
熊井啓さんの最初の『帝銀事件死刑囚』、西河さんだと小百合ちゃんの『伊豆の踊子』、清順さんだと『肉体の門』をちょっと応援でやって、その後『春婦伝』なんかもやりました。
それから亡くなった中平監督は『赤いグラス』っていうのをやってます、アイ・ジョージでね。中平さんが晩年はもうぐでんぐでんに酔っぱらってね、ロケーションの現場に行くとね、これから撮影するトラックの運転台に乗って酔って寝てるんですよ。これから撮影するトラックの真ん中に乗ってライトがバンバン当たってるのに運転台で寝てるんですよ。それでチーフ助監督やってた村田さんていう人がいてね、全部ライティングできたから運転台のとこ行ってドア開けて、「中平さん、ちょっと準備できましたから降りてください」って言うとね、中平さんはこうやってやりながら、「ヨーイ……、ヨーイ……」ってやってんだね(笑)。
中平さんは、僕一本しか付き合ってないけど、すごく可愛がってくれてね、僕が新人賞取ったときの試験委員かなんか、中平さんが、後で聞いたんだけどやっててくれたらしい。清順さんもいたらしいんだけどね。中平さんの晩年の、これだけ徹底して自分が撮影する運転台に乗ってヨーイハイかけられる監督になりたいなあと思ってね、晩年はね。畳の上で死ねなくてもいいから、「監督、ライティングできました」って言ったら目を覚まして、「ヨーイ……、ハイ……」と言って死ねたらいいなあ、と思ったぐらいね(笑)。中平さんにはね、そういう思い出がありますよ。どっちかっていうと天才肌の人でね。増村保造さんていたでしょう。「俺が賞を取ろうとすると増村がみんな持っていくんだ。増村の奴、あいつ」って言うんだけどね。でも中平康監督というのはね、『月曜日のユカ』とかね、やっぱり素晴らしい監督でしたね。ああ、斎藤武市さんもつきましたね。
−−今のお話の通り、一つの撮影所のシステムというのは大変強固でして、田中登監督もまさしくそういった60年代の日本の撮影所から出てきたという監督の一人なんです。補足しておきますと、「新人賞」とおっしゃられたのが日本映画監督協会新人奨励賞、これを73年に今日の上映作品『秘(まるひ)女郎責め地獄』で受賞されてます。
田中 プリントがちゃんとしてればいいんだけど。
−−今日のは16ミリへのブローアップですので、トリミングなど問題もあるので残念です。
さて、田中登監督が登場された背景である当時の日活の状況をおさらいしておきますと、70年にダイニチ映配というのが発足しました。つまり大映と日活が合併で配給を始めた時代でして、『野良猫ロック』とか、いわゆる日活ニュー・アクション・シネマというのが出てきた。
田中 それの直前ですね。ロマンポルノが始まる直前ですわ。パキさんの、藤田敏八さんの『八月の濡れた砂』なんかもありましたね。
−−『八月の濡れた砂』が翌71年の8月、これを最後に日活が一度製作中止をするわけです。
田中 そうなんだよね。これだけ助監督やってきてね、あのとき忘れもしないんだけど、日活、映画製作をストップって言うんだよね、辞めるっていうんだよね。
いやあ、みんな大変でしたよ。蔵原さんの弟さんも撮ってたのかな、パキさんとね。映画会社が映画を作らなきゃしょうがないからね。ストーンと目の前で映画をやめるってことがあったわけですよね。
−−それで11月にロマンポルノが第一作『団地妻・昼下りの情事』を西村昭五郎監督のメガホンで製作する。あと『色暦大奥秘話』ということで、これでロマンポルノが確立されて、以降88年までずうっと十数年にわたるプログラム・ピクチャーとして咲き誇ったわけです。田中監督というのは日活ロマンポルノの第一期生、まさしくロマンポルノとともに登場した監督でして、その頃はいわゆる日活のロマンポルノ裁判とかそういった時代でした。その中で田中監督が初めて撮られたのが『花弁のしずく』。このデビュー作で何か思い出深いエピソードとかありますか。
田中 これは『燃え上がる私』というのが原題なんですよね。ちょっとトリュフォーばりだなあと思ってね。本当は『燃え上がる私』の方が好きなんですよ。難しいとこなんだけども、会社は勝手にタイトルつけるんですよね。タイトルだけはちょっと抵抗できないところがあるんでね。
『秘(まるひ)色情めす市場』って自分で舌を噛みそうなタイトルをね、あれも『受胎告知』ってのが原題なんですよ。僕は『受胎告知』にしてくれって言ったんだけどね、重役が寄ってたかって一つ一つタイトルをつけて、舌を噛みそうなタイトルもあるんだけど、どの辺で、これは聞かなきゃしょうがないかなってとこもあるんですよね。つまりタイトルってのは映画にとって非常に大事ですけども、むしろ作ることによって会社側をリードしていくってようなことをやって、あとは内容の勝負だっていうところもありましたね。
それと日活っていう大会社がね、日本の映画会社で一番古い会社が18年間に渡って一つのジャンルだけ突き詰めるっていうのは、ある意味では稀有なことでね、やっぱり日本映画がいままでエロスの表現ということに関してはいびつだったわけですよね。その部分だけが欠落していた部分をようやく一般に認知させてですね、やっぱり表現の上では時にはエロスも必要なんだというようなことを18年かかって作り上げた。で、最後は狂い死にして会社が潰れちゃった。
日活ってのは面白い会社なんですよ。歴史を調べてみるといつもそういう連続でね。その後ロッポニカっていうのになったんですけど、ロッポニカも12、3億円の製作費、最初用意したんですよね。一つ1億円ぐらいでとにかく作ろうと、それで作ったら金使い切っちゃってこれもダメになっちゃったんだよね。
だから日活っていうのは面白い会社なんですよ、そういう点ではね。ある意味では非常に純粋化できて、変に商売が下手なところがまた楽しいわけで、そのくせして一番日本映画で伝統のある会社でね。ある意味ではロマンポルノを撮った連中ってのは、その前のいわゆる日活のニューアクションから何から全部ほとんど助監督ですごした連中が監督になったわけですから、自分の表現を引っ提げて、エロスならエロスっていう分野で自分なりに表現するんだと、そういうやつだけが残ったわけですよね。それでそれに肌合いが合わないのは辞めていったということもあるわけですよね。
僕が当時助監督室の幹事やってて、「このジャンルのシャシンはできない」って言って辞めてく人もいたし、「いや、これこそ映画が純粋に表現できるんだ」って言って、幹事という立場で引き止めたこともあるんですよね。
村川透なんかもそうですよ。辞表胸にして、最初「辞める辞める」って言ってたから、「村川さん、こんなに映画の表現ができる時にもったいない。とにかく一回戻ってこい」って言ってね、殴り合いの喧嘩でもして戻したことあるんですよ。あの人、一回辞めて故郷に帰ったことあるんだよね。でもね、僕は助監督室の幹事って立場でね、絶対表現する場合があるはずだから、そういう形で本当、映画と直に向き合える時代、そして自分の映画に志した選択を自分でギリギリで決着つけなきゃいけないっていうのがロマンポルノが始まった直前だったんですよね。それまで10年近く、みんな助監督、曲がりなりにもすごい倍率突破して、それだけの映画をずうっとやってきてこれから撮れるっていう時にパタンと止めたってなったわけだから、これはちょっとやっぱり死ねないね。やっぱり自分の表現するものを何としてでも何か表現しないかぎりは死ぬに死ねないっていうか、映画が好きだからね。
−−それはもう刺し違えるというか・・・。
田中 最初からみんな刺し違えるぐらいのハートでみんな進んでいったわけですよね。映画撮ると警視庁が摘発するという、つまり日本文化が長年かかってきてもっとも隠そうと思ってきたことを初めて暴こうっていうところなんだよね。だから体制側はそれを摘発しようっていうのは当然なことでね、そういうこともあったわけですよ。僕なんかも含めて警視庁の取調室へ呼ばれてね、廊下にいるとあの辺に三浦朗がいたりね。取調室へ行くと大体警部クラスが取り調べるんだよ。窓を見ると皇居の松がウワーッと見えてね、ロマンポルノ裁判ってのはそういう連続でしたから。結局、日活が勝訴しましたけどね。勝ちましたけど。
−−そういう経緯についてはいくつか文献残ってますけども、凄まじい歴史です。そういった中で例えばプロデューサーの三浦朗さん、日活ロマンポルノ五百数十本のうちほぼ五分の一ぐらいは三浦さんじゃないかと思います。
田中 今、日本で活躍しているプロデューサー、岡田裕、結城、亡くなった三浦朗さん、僕の『秘(まるひ)女郎責め地獄』やってる松岡明くんだと、今、ユニオンでテレビのプロデューサーになってますけども、ほとんどロマンポルノをプロデュースした連中が今、独立してるような形ですね。
−−裁判の話になりますけども、そういった時代背景の中では三浦さんの苦労なども大きかったんですね。
田中 いや、三浦朗に限らずにね、みんなあれですよ。だって監督から言えば、撮った画がその前に、摘発される前に映倫ってのがあるわけですよ、日本では映倫がチェックするわけですよ。映倫はあくまでも映画会社が時の権力なんかの介入を許さないっていう形で映画倫理委員会を作って、そこを通ったシャシンは原則としてなるべく警視庁、権力の介入を許さないっていう一つの防波堤の意味もあったりして業界が作った団体なんですよね。それでも映倫の委員が来るわけだ。で、上映すると見てて、「あそこの部分はボカしてくれ」とかね、「あそこの部分は何秒カットしてくれ」、ワンカット、ワンカット、全部やられるわけです。警視庁もさることながら、その前に映倫との対決があるわけですよ。で、映画が試写されると、必ず表現に関して、「あそこの部分はボカしてくれ」、そういう連続でしたね。それと同時にロマンポルノ裁判も平行してあったわけだから。だから表現を確保してゆくためにそれを両方こなしながら、しかも自分で撮りたい映画を撮っていくっていう凄まじい制約があってね。会社自体も細かいこと言わなかったね、ある意味ではね。とにかく自由にやってくれと。だからある意味ではもっとも映画が純粋化できた時代だと思いますね。
−−そういう苦渋の中でのパートナー、田中監督に縁の深いシナリオライターなんかのお話をお聞きしたいと思うんですけども・・・。いどあきおさんをはじめですね、田中監督と仕事をされたシナリオライターはそうそうたるメンバーがたくさんおられます。 そうですね、いどさんとのコンビのお話をお願いします。
田中 いどさんはね、最初テレビの脚本を随分書かれてましてね、日本テレビの作品随分書かれてますよ。それで日活のロマンポルノが始まったら、こんなに純粋に書けるものがあるのかっていうところでね、こっちに移ってきたんですね。
で、僕はいどさんと、『秘(まるひ)色情めす市場』、『実録阿部定』、『江戸川乱歩猟奇館・屋根裏の散歩者』、『発禁本「美人乱舞」より・責める!』、それから『ピンク・サロン 好色五人女』、この5本やってるんですけどね、1年に1本ずつ、5年かかったんですよね、いどさんとね。で、他のみんな、5本か6本、多い人は8本ぐらい作れたんだけど、僕はいどさんと1年に1本しか作れないのが5年続いたんですよね。それでもいいから、1年に1本でもいいから納得のいくものをとにかく作ろうと。それでいどさんにはそういう注文を出して・・・。
このシナリオ作りはほんとに凄まじかったね。『実録阿部定』の台本なんてのは54ページしかないんですよ。最初はとても厚かったんだけどね。どんどん削れてくわけですよ、削ってくわけですよ。
−−それは具体的にはセリフですか。
田中 セリフもそうだし、シーンもそうですよね。あ、これも削れるな、これも削れるなって削っていったら、54ページになっちゃったんだけども、その裏に張り付いているものは凄いわけですよね。いどさんとの仕事は『秘(まるひ)色情めす市場』もそうだったんですけども、そういうホン作りでしたね。
『秘(まるひ)色情めす市場』もやっぱり今の西成に、僕はシナリオハンティングで十回前後行きましたかね。ハウスへ行って泊まると、寝てる枕に垢がびっしり、テカテカに光ってるんですよね。ジャンパー着込んで帽子をかぶってそのまま寝ないとね、気持悪いぐらいな、やっぱりそういうところへ潜り込んで夜寝てると、向こうで廊下の隅で石持ってきて火焚いて御飯出すんだよね。向こうでは喧嘩してるしね。それから布団に火をつけて窓から投げるしね、そんなことが連続で毎日目の前で起こっているわけだけだ。
それから西成の警察署ね、保安課。シナリオが出来上がってここで撮影したいって言ったら、この警察が禁止した箇所が全部シナリオに入ってるわけ。赤線引いて保安課長が指し示すんだよね。「君、ここの中で撮影したら、何か暴動あったら責任取れるかね。何かあったら逮捕するよ」って言われて。逮捕するよって言われたって、シナリオ見たら禁止されたところで全部ホンが書かれているからね、これはここでやるしかないなあと思ったんだよ。それで覚悟決めてね、それで撮影所帰ったら、今度は撮影所長がそばに寄ってきてね、「おい田中、おまえ大丈夫か」って言うんだよね。「何かあったらどうするんだ」ってね。その前に西成の暴動なんかたくさんあったでしょう。どうするかって言ったってね、そこへ入ってキャメラ回すしかないからね。それはもうスタッフ全員でやりましたよ。あの中で、花柳幻舟さん出てるでしょ。花柳幻舟さんキャスティングして、幻舟さんとその時初めて会ったんだけどね、僕はね、お寺の庫裏に泊まってたんですよ。で、遥か30畳か40畳の広い、だだっ広い庫裏でね、幻舟さんがなんかうっすらとした無垢で座ってね、こうやって手をついて挨拶したの覚えてるんですよ。幻舟さんとの出会いはそれなんですよね。
あのシャシンは萩原朔美も出てるけど、芹明香くんももちろん出てるんだけど、(宮下)順子、このシャシンは登場してもらう人物は全部がそういう人生張り付いてる人じゃないとキャスティングしたくなかったんですよね。全部そういう引きずりやってる人。芹明香くんだって体張ってずっとやってきたわけでね。ほんとに町田あたりの肉屋の店員やったり、流れ流れてストリップ小屋でいろいろやったりね。あらゆる生きてることをそのまま張り付いた連中しかあそこに出てないんですよね。ほんとはそういうキャスティングであのシャシンは撮りたかったってことがあってね、だから警察も含めて全部、例えばあそこの中に通天閣を延々上がっていくシーンがあるでしょ。
−−ラスト近くのカラーの部分ですね。
田中 ええ。通天閣の最初の展望台の高みだと僕ちょっと嫌なんで、一番上まで上がりたかったんですよね。通天閣の社長さんがOKしてくれるかどうかね(笑)。現場ではいつもそういうことがあるんだけど、キャメラが構えられるか。とにかくキャメラを構えるまで努力しなきゃね。そしたらね、これがね、なんていうか強運ていうか、幻舟さんが通天閣の社長さんと友達だって言うんですよ(笑)。天の配材だよ。で、幻舟さんにね、「お礼どうしたらいい」って言ったら、「お礼なんかいらない」って言うんですよ。で、結城と一緒にね、「じゃあ悪いから一升瓶1本だけ持ってこうか」って言ってね、それで許可取ったら撮れたんですよ、あそこキャメラ上がれて。
それから何気ないショットですけど、幻舟さんと芹明香が三角のホテルでね、幻舟さんが妊娠して、あそこで「そのぐらいおかあちゃんいじめたらええやろ」っていう、なんか母娘で言い合うシーンがある。あのアパートのOKを取るのにね、大阪の街を結城プロデューサーと西瓜一つ提げてね、何軒歩いたことか。あのアパートの持主をね、こうでもない、こうでもない、この人持ってる、この人持ってる、西瓜提げて炎天下をさあ、ずうっと歩いていってようやく辿り着いたら、その人のところへ結城と二人でもって正座してね、「あのアパートがどうしても欲しいんですけど、撮らして貰えますか」って言ったら、今でも忘れないけど、ステテコ着てね、将棋打ってるんですよ。ひょっと見たら指がない、そのおっちゃん。そして、こう、こっちの撮りたいことを「とにかく撮らしてくれ」。そしたらその人、「良かったな。まあ、ええやろ」、一言、「まあ、ええやろ」。ウーッ(笑)。こういう連続でね。
それとね、もう一つそんな話をするとね、あの夢村四郎くんね、天象儀館の、荒戸源次郎くんとこの夢村四郎くんなんだけどね、あれはね、キャスティング今から考えると、夢村四郎くんとね、山本晋也がよく使ってた、「未亡人下宿」に出てたボクサーの彼、死んじゃった彼……。
−−たこ八郎さん。
田中 たこ八郎さん。あの二人、最後オーディション残ったんだよ。たこ八郎くんを日活の演技課へ呼んできて最終面接したんですよ。で、たこちゃんと話してね、ちょっと一回会ってくれるか、「たこちゃん、一番怖かったことなんだ」って聞いたらね、仙台かなんか向こうの出身なんですね、「艦載機に追われて田んぼの中逃げ回ったことが一番怖かった」って言うんだよ、たこちゃんはね。たこちゃんどっちかの耳悪いんだね、「たこちゃーん」って言うと直ぐに返事しないんだけどさ。で、こう見てたら、たこ八郎さんの感性の中にも狂気はあるんだけどね、夢村四郎と会ったらもっと凄いんだよ、これが。それでその夢村四郎に芹明香の弟をやっていただいたんですけど。あの、大阪の、最後になんか首を吊る、死ぬことがこう、なんか感覚的に地上の上で死なせたくなかったのね、彼には。何かね、ちょっと高みへ上がって、ちょっと高いとこへ上がって空中へ下がってもらいたいっていう感性が、感覚が凄くあってね。それでそんなことが鶏を連れて大阪城の石垣を歩いていったり、通天閣を上がっていくっていう感覚になったんだけども。
最終的にそれが丼池ですか、あそこの街が全部立ち退きでね、ほとんど誰も住んでないんですよ。あそこの街行ってね、パッと見たらね、誰も住んでない街に全部シャッターが閉まっててね、人っ子いない時に風がこうパーッと渡っていくとね、シャッターがカタカタ、カタカタ、カタカタと鳴ってる。「あ、この街しかない」と思ったんですよね、彼の死場所はね。それであそこの場所を選んだんですよ。それで彼には電柱をこう上がってもらって、軒庇を歩いてもらって、こういう軒庇から出ている天幕のあの紐で首を吊ってもらってるんですよ。あれで首にかけてもらって、上からポーンと飛び下りてもらって、風が渡ったシャッターの通りへボーンと入ってもらって・・・。
−−すると、あれは映画を見てますと、全部シャッターが降りてて、朝方にでも撮ったんだろうかと思ってたんですが、本当のゴーストタウンだったんですか。
田中 そして、あそこで首吊りのOK取るの大変なんですよ(笑)。今でも忘れられない。あそこの組合長さんだけが頑張って残ってたの、「立ち退き、ヤダ」って言ってね。それがね、大阪の日活の関西支社の社員で、またその辺の詳しいのがいるんだ。「監督、これです。ここです」。その残ってる会長さんの家の前、OK取りたくて。その人のOK取れないとあそこで撮影できないんですよ。それでね、そのシャッターを抜けてダーッと奥へ通っていってその社長さんの家の裏へパッと出たらね、庭がバーッと荒れててね、立ち退きで雑草がぼうぼうと茂っててね、そして夏の雲がこう青空にバーッと広がってて、天水桶に水が満々とたたえられていてね、で、立ち退いた跡に水溜まりができてたんですよ。そこに金魚かなんかがぽわぽわと泳いでるわけ。そしてこの組合長さんのOKを取らないとこの撮影できないなあと思った。で、組合長さんとそこの横に座ってね、二人で座って石をポコッポコッて投げながらさ、段々その組合長さんの気持ちをほぐしていってね、ほぐしてほぐしていってこの話しなきゃいけない。で、ようやくOK取れてね、あのシーンが撮れたんですよ。
だからどの映画にもそういう現場の苦労はありますけど、特に『秘(まるひ)色情めす市場』は、まああのシャシン撮ってる時に自分の娘も死んじゃったからね。セットのシーンは撮影所帰ってから、葬式出してから撮った思いがあるんですよ。だからあのシャシンにはそういう形ですべてぶち込んで、映画作るってのはこんなに残酷なものかなあと思ったけど。やっぱりそうやって作ったシャシンなんですよね。だからどのシャシンもそういう思い出はありますけども、そういうものが映画の画面に、たぶんスタッフもそれを感じてね、出してくれてるんじゃないかなあと思うんですよね。
−−『秘(まるひ)色情めす市場』はモノクロの、正確に言うとパートカラーですけども、ほぼ全編モノクロです。ある意味で風景の映画っていう言い方ができるんですけども、風景の映画の中でも日本映画で、大阪・西成の風景というものを、映画的なリアリズムで切り取ったっていう凄まじい例だと言っていいと思います。時代も違うし西成も変わりましたが、例えれば阪本順治の比ではないと思います。今のお話がなんかそれを裏付けているんじゃないかなという気がします。
田中 そういうエピソードは無尽蔵ですよ。芹明香の部屋へ入っていくと、洗濯物だらけね、あんまり外へ干せないから部屋の中へベタベタとパンツが飾ってあったりね。もう毎日そういう連続でしたね。西成の三角公園を芹明香が横切るカットがあるの。キャメラは俯瞰で窓にかかったのれんの裏から狙ってるんだけどね、三角公園でみんな火を炊いてるから彼女が通り過ぎるだけでヤバイわけ。スタッフが全部散らばってた。
それから最初のタイトルバックになってるシャッターが上がってくカットあるでしょ。あの時のヨーイハイのサインを僕はね、あそこで浮浪者になって道路の上に寝転んで出した。キャメラがワゴン車に構えて。僕はシャッターの一番いいところで道路の上ひっくり返ってね、ボロボロの衣装着てね、寝ながら、「ヨーイ、ウーッ、ウーッ」ってやった。あいりん地区の中の寄りの画はね、安藤庄平さんがね、キャメラを構えられないんですよ。胸から提げてレンズだけ出して撮ったカットなんですよ。ものに関してもデリケートですけど、あいりん地区の人たちは音に関して素晴らしい。シャッターのシャカッ、シャカッとか、シャーッて音に関してはバーッと一斉に反応する。タイトルバック撮ってる飛田の階段あるでしょ、あれ、キャメラ回ってる横で酔っ払いのオッチャンがみかん箱頭へゴーンとぶつけてね、血流しながら、「お前たち、ここへ来て映画撮るの十年早いぞ」とかなんか言ってわめいてる(笑)。写ってませんけどね。それで安藤さんとこうやって撮ってる、芹明香が座ってて、絵沢萌子さん降りてくるカットね。あそこのカットはそういう連続ですよ。
−−ファースト・シーンですね。恐ろしいエピソードばっかり・・・(笑)。
1996/8/30