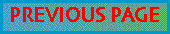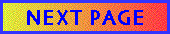CMN! no.1 (Autumn 1996)
 書評
書評
『アンゲロプロス 沈黙のパルチザン』
著者ヴァルター・ルグレ 奥村賢訳 フィルムアート社 1996年
映画学の基本姿勢としてのモノグラフィー
石田美紀
『アンゲロプロス 沈黙のパルチザン』はギリシアを代表する映画監督テオ・アンゲロプロスの本格的な研究書であるばかりでなく、監督研究・映画研究に何が必要かを私たちに教えてくれる、映画研究方法のあるべき形態の一つである。
アンゲロプロスと彼のフィルム群に対して、ヴァルター・ルグレはフィルムの細かいテクスト分析からアプローチを開始する。アンゲロプロスのフィルム群の中核をしめる1974年に完成した『旅芸人の記録』の全ショットを記述したシナリオが、資料として付けられているのだ!この労作のショット表は、各ショットの持続時間、登場人物のセリフ・動き、そしてカメラの動きと、ショットサイズが記載されている。ショット表を読むことは、フィルム自身を見ることとはまったく異質な体験である。しかし、映像を文字に置き換え、読み込んでいくことは、フィルム体験を損なうどころか、フィルム体験とフィルムの理解を深化させることに大きく貢献するのである。ルグレは、前書きで「映画の図書は映画の代わりをすることはできない。書物には書物なりの利用価値がなければならない。(中略)本書は、映画を体験できる場を用意したいと思っている。また、映画体験を広がりのあるものにする手助けをしたいと思っている」と述べているが、その言葉を裏切らない充実した分析を読者に披露してくれる。
『旅芸人の記録』の冒頭約10分、3分ほどの長回しがある。旅芸人の一座がホテルに到着し、荷をほどき、芝居の稽古をはじめる場面である。カメラはゆっくりと移動し、視点を変えていく。静かでありつつも、スリリングなシークエンスである。ルグレは、このシークエンスのカメラの動きと俳優の動きを、アンゲロプロスが検閲当局に提出した概要にしたがって、徹底的に記述・分析する。ルグレの分析から、カメラの動きと視点の変化によって、4時間にもわたるフィルムの中を放浪する一座の中の人間関係と物語の展開が、冒頭にすでに提示していることが明らかにされる。フィルムが進むにつれて売国奴であることが判明するアイギストスが、稽古の場からひそかに立ち去るのを、カメラは逃さない。アンゲロプロスは、ワン・ショット=ワン・シークエンスの中で、モンタージュをほどこすことなくとも、多層的な意味をもたらす。時間すら、再構成してしまうのである。『旅芸人の記録』では、冬枯れの風景を黙々と歩く芸人達を捉えたワン・ショット=ワン・シークエンスのなかで、10年という時の隔たりは飛び越えられる。映画では時間の再構成、非・連続化、省略が可能となる。
アンゲロプロス以前には、ワン・ショット=ワン・シークエンスにおいて映画内の時間と撮影された事物の時間が一致すると考えられていた。しかし、ワン・ショット=ワン・シークエンスの中で、カメラの動きが音声と絡まることで、時間の飛躍が行われることが、ショット表から理解される。ルグレのショット分析は、アンゲロプロスがムルナウ、ウェルズ、溝口といったワン・ショット=ワン・シークエンスの監督たちの直系であると同時に、革新者であることの説得力ある論証となる。
ショット分析の次に読者に用意された軸は、歴史である。アンゲロプロスのフィルムと接する時、ギリシア現代史という視点を欠くことは、致命的な手落ちとなる。というのも、アンゲロプロスは、過去に起こった事件と彼が映画を撮影する現在を結びつけることで、母国ギリシアの歴史・政治との抜き差しならぬ関係に身をおくからだ。なぜ、ワン・ショット=ワン・シークエンスの中で、時が飛び越えられ、異なった二つの年代が併置されなければいけないのか。その答えは、1939年-1952年のギリシアが経験した歴史にある。ルグレはフィルムのテクスト分析を、フィルムの外側の文脈と関わらせることを忘れない。本書には、1821年-1992年までのギリシア史が収録されている。こういったギリシア史年表を収録するルグレは、非常に啓蒙的である。近代・現代とギリシアがどのような政治状況にあったのか、極東に住む私たちは、残念ながら敏感ではない。何世紀ににもわたり、外国に支配されてきたギリシアは、第2次世界大戦中は、ドイツ・イタリアといった枢軸国の攻撃および占領を受け、戦後もイギリス・アメリカに後押しされた軍事独裁政権に苦しむ。
ショット・ナンバー41、1952年秋に芸人達は港を歩いている。パパゴス元帥に投票するようスピーカーからがなり立てる三輪オートバイが、彼らのそばを通り過ぎる。しばらく静寂が訪れたのち、三輪オートバイが過ぎ去った道を、黒のメルセデスベンツがやってくる。ドイツ兵が検問を行っている。このショットで、戦後の1952年秋から第2次世界大戦中の1942年冬に移行するのである。1952年は極右のパパゴスが不正選挙により政権を取る。その後12年間、反共産主義とヒステリーの恐怖政治がギリシアを支配する。1942年は、周知のごとくナチスの脅威がヨーロッパを覆っていた年である。ギリシアもナチスの占領下に置かれた。10年も隔たったこれら2つの年代は、ギリシアにとって等しく困難の年である。アンゲロプロスは、ナチスと戦後の極右をワン・ショット=ワン・シークエンスの中に併置させることで、彼自身の歴史観に言及する。
このワン・ショット=ワン・シークエンスは、単に美的な表現や映像言語の進化であるばかりでなく、政治的な言説として機能しているのだ。フィルム全体を覆う曇った色調、冬枯れの様子。牧歌的なギリシアのイメージが視覚化されているのは、旅芸人達の出し物である芝居『ゴルフォ、羊飼いの少女』の舞台装置である背景幕の羊の絵だけである。牧歌的な背景幕の前で繰り広げられるこの芝居が上演されようとする度、空襲や侵入者によって中断を余儀なくされるが、これはギリシアの政治的不遇さのメタファーであることが解る。『旅芸人の記録』というフィルムを、歴史の中においてみるなら、このフィルムは、れっきとした政治的なアクションである。ルグレが掘り起こすスリリングな逸話の数々は、『旅芸人の記録』の製作が、検閲を始めとする政府の暴力的な映画への介入との闘争であったことの証言となる。軍部のシナリオを承認をやりすごすため、大学時代の友人であった閣僚に根回ししたり、デモ隊が行進するシーンでは、国歌を唱わせたり(完成したフィルムで、デモ隊が唱うのは左翼の歌である。ダビングによってデモ隊のシーンは完全な形を取ることが出来たのである)等々。
『旅芸人の記録』の撮影は1973年に開始されたが、軍部による学生デモの弾圧という流血事件に撮影隊は巻き込まれ、中止となる。暫定軍事政権の崩壊した後、1974年に撮影を再開するが、軍事政権下では、資金不足のため撮影できなかったショットナンバー74が撮影される。このショットは、赤旗への信頼がスピーチとして流れるのである。『旅芸人の記録』の撮影再開は、非常に象徴的な事実であろう。1974年、正常な政党政治が復活し始め、北大西洋条約機構からギリシアは離脱するのだ。『旅芸人の記録』は、国民の圧倒的な支持を得た。ギリシア国内の映画祭サロニキ映画祭で9つの賞をもらい、35万人の観客を動員し、74年度最高の興行成績をあげたのである。4時間にもわたる上映時間、だがショット数はたったの131というこの非・商業映画が、大衆レベルにまでいたる支持を獲得したのは、たぐい希なことではないだろうか。この支持の理由は、フィルム自体の美しさはもちろんであるが、フィルムの外側の歴史・政治との関わりもあるだろう。
『旅芸人の記録』というフィルムの様々な側面を、ルグレは洗い出す。細かい資料を提供しつつ、フィルムを出発点とし、歴史・政治に至り、またフィルムにもどるその手法は、説得力があり啓蒙的である。映画監督という一個人と、彼を取り囲む歴史的・社会的・文化的な関係を論じることは、重要な切り口といえる。フィルムにとっては絶対である創造主たる映画監督ですら、彼を影響下に置き、ある時には有無を言わせず彼を翻弄する歴史の流れから身を引き離すことはできないからである。フィルムのみのテクスト分析にとどまらないルグレの丹念な研究は、フィルムの外側の歴史とフィルムの関わりを明確に提示してくれる。本書は単なる感想を書き連ね、フィルムへの個人的感情をぶちまけるだけの書物ではない。読者と客観的な知識を共有しようとする姿勢は、映画研究、映画学を発展させるためには、基本となるものである。本書のような堅実なモノグラフィが、映画研究の新しい局面を開いていくのである。