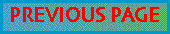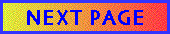CMN!BookReview'Joseph Losey'
CMN! no.1 (Autumn 1996)
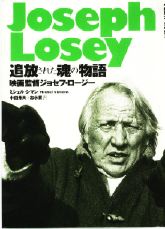 書評
書評
「追放された魂の物語 映画監督ジョセフ・ロージー」
著者ミシェル・シマン 中田秀夫・志水賢訳 日本テレビ 1996年
性的な魂の物語
大野裕之
ジョセフ・ロージーと言えば、赤狩りでハリウッドを追われ、その後一度もアメリカに戻ることもなく、ヨーロッパで、映画をとり続けた骨太な映画作家として知られているが、残念なことに、わが国ではまとまった資料も少なく上のような紋切り型以外は、我々の知る所はほとんどなかったと言ってよい。
折しも、彼の友人であったニコラス・レイら50年代アメリカ映画の再評価の機運が高まる中、ようやく、ミシェル・シマンによるインタビューが届いた。まさに待望の書物というべきであろう。
しかし、数少ないジョセフ・ロージーの総合資料と思って、勢い込んで読み始めた読者は、はじめから大胆な構成に少々面食らう。すなわち、著者の物も訳者のも含めて「注釈」が一切ないのだ。
とりわけインタビューのような、話者の主観で構成された書物では、それを補い、読者の理解を容易にしてくれるところの周到な注が必要ではなかったか? 注もない書物が一級の資料として成り立つのか? だが、読み進めていくうちにそのような不安は消えていく。というのもミシェル・シマンのインタビュー(その誠実な批評精神は特筆すべきである)に答えるロージー自身の知的で緻密な語り口はそれ自身注を必要としないほど明晰であり、いわんや、時にみせる知性を突き抜けた激情的な箇所など、凡百の百科事典的な知識など果たして必要とされるだろうか。
たとえば、オーソン・ウェルズについての描写。「私はウェルズの作った映画でだめだった箇所は一フィートもないと思っている」「が、その一つ一つのシークエンスがつなぎ合わされ一個の優れた作品とは言えない。」また、彼は「市民ケーン」に対して、一般に言われているほどの魅力をおぼえないとしつつも、同時に「映画史上の非常に重要な突破口であり、多大な影響を与えた映画だということには間違いはない」と認めている。このユニークでかつシャープなウェルズ評に、ありきたりの注釈は蛇足というべきであろう。
そのウェルズをはじめとして、同世代のカザン、レイ、そしてロージー自身、もともとは舞台出身という共通のキャリアを持っている。彼は他にも「食べていくために」ラジオ(彼はここから「音について学んだ。」)、テレビ、コマーシャルなどの仕事をする。また、資金難のために思うように映画が撮れない。この辺の体験も彼らに共通の物だろう。
さてロージーと言えば、赤狩りでアメリカを追われたわけだが、彼は共産主義への共感を随所ににじませながらも「入党は誤りだった」と語る。彼が入党したのは「私生活のスキャンダル」の話題しかないハリウッドに嫌気がさし、文化的な勉強がしたかったのだとしている。このように後になって当時の行動を否定するのを、よくある左翼知識人の転向と見るのはたやすい。だが、そこにあるのは、逆に、彼の比類なき誠実さであり、事実彼はこのインタビューの時点でも、あの不条理な赤狩りはもちろんのこと(ソ連でも同じようなことが行われていた、と指摘するミシェル・シマンに対して、ロージーは「あれ以上にひどいものはなかった」と答えている。)、あらゆる反動的なものへの嫌悪をあらわしている。
特に読者は、彼が良質のフェミニストであったことを証明する箇所にしばしば出くわすだろう。彼は「ジョン・ウェインのように」「男っぽさ」を売りとする俳優たちは、メイクアップで「自身にも女性的な要素があるという恐怖心」を隠していると非難し、理性的な人であれば女性解放運動に影響を受けているはずだと断言する。「鱒」のなかで次のような台詞がある。「異性愛、同性愛といった区別はもうないの。あるのは、ただ性的かそうでないかの違いだけ。」
この言葉と共に我々はもう一度ロージーの映画にたち戻る。ファシズムの不条理に対する怒りをこめた名作「パリの灯は遠く」の冒頭はどうだろう。ユダヤ女性が唇をむかれ,鼻にものさしを突っ込まれ、屈辱的な「身体検査」うけるというショッキングなシーン。カメラはクロースアップでユダヤ女性のおびえと医師の冷淡さをむきだしにする。画面の奥で不安定な斜めの軌跡を描いて歩く女性の裸体は少しもエロチックではなく、むしろ吐き気を催させる陰惨なヌードだ。性的であることが許されないファシズムの残酷さを彼は陰鬱な画像で描く。手持ちカメラのフレームは小刻みに揺れ、不安を増幅させる。
同じく反戦映画といえば、彼の事実上のデビュウ作である「緑色の髪の少年」がある。これも、全体的に陰鬱なトーンが目立つ中で少年の髪の色が緑色になるときだけは違う。バスルームで突然気づく髪の色の変化。少年のきめこまやかな白い肌の裸体。鮮やかな緑色の髪。(「この映画で鮮やかな色はあの緑色だけだ」ロージー)そして、鏡に向かう少年の笑顔。唯一色彩とよろこびに満ちあふれるシーンだ。ロージーは「創造力に富んだ人」と「性的な人」とを同一視する。この子どもは緑色の髪の毛で大人たちに平和のメッセージを伝えるというアイデアを思いつき、天使のように街に駆け出していく。風に揺れる鮮やかな緑の髪。創造の天使。性の未分化なはずの子どもが、実はもっとも性的なのだという逆説。
ジョセフ・ロージー。この性的な魂はアメリカや共産主義、そして性別などあらゆる枠組みをそのつどラディカルに突き抜けた。ブレヒトやビリー・ホリデイらとの交遊。そして異国の地で、実は最後までアメリカに戻ることを夢見ながら映画をとり続けたロージー。その姿は20世紀精神史の重要な記念碑であることに、もはや何の注釈も必要ないだろう。